読了目安:5分
オーナー企業の出口戦略①
立場上、多くの「オーナー経営者」からご相談を受ける。しかし、「経営者」と「オーナー」としての悩みを混在されているケースがとても多いように感じている。論点が整理されないまま「場当たり的」な対応をすることで、出口戦略(EXIT)が望ましいかたちで実行できないケースをたくさん見てきた。経営者として、株主として、それぞれの立場で「失敗しないオーナー経営者の出口戦略」を10回のシリーズを通じてお伝えしたい。
「オーナー企業×PEファンド」

若い創業者がPEファンド(プライベートエクイティファンド)に株式を売却したと聞けば、どのような状況を想像するだろうか?
最大価値での売却、創業者利益の確保、アーリーリタイアメントなど、創業者が手にする経済的な対価と譲渡後の悠々自適な生活、あるいは手にした利益を基に新たな事業を立ち上げる、いわゆるシリアルアントレプレナーを想像される方も多いのではないか。
ファンドの社会的役割は認知されてきた。しかし、オーナー社長からは未だに「転売目的」「役職員がリストラされる」といった、ファンドに対する否定的なコメントが返ってくることも多い。
イメージ先行で、一面的な捉え方しかされていないのは残念だと思う。
ファンドの機能や役割を正しく理解し、「出口戦略」の選択肢から排除せずに自社にとって有効であるかどうか検討する機会を持つことを勧めたい。
あるレンタル業者の売却事案

昨年、30代で自ら起業した会社(以下、A社)を売却するオーナー経営者のアドバイザーとして、ファンドへの譲渡を支援する機会があった。
自社サイトを通じてレンタル事業を行っている企業で、年率30%を超える成長を続けており、利益率は高く、金融負債もない。一見すると今すぐM&Aをしなければならない理由は見当たらない。
プロセスに入る前に、社長から現状の課題やパートナーとなる相手先に期待する点等を伺ったところ、極めて明快な答えが返ってきた。要は、急速に事業規模が拡大し、1人でマネジメントするのは限界に達しているということだ。
マーケットシェアは高いが、大手の参入もあり、競争を勝ち抜くために成長プランを実行するため投資資金が必要だった。
具体的に実行する必要がある主要施策として、以下を計画していた。
① 社屋の増築
② 物流拠点の拡充
③ バーコードやICタグを活用した在庫管理と業務フローの改善
④ 顧客データ分析とリピーターの囲い込み
⑤ スマホアプリの開発
⑥ 多様な顧客ニーズに対応した取扱商品の拡充
⑦ 法人営業の強化
この若い経営者は当初、ファンドをパートナーとすることにネガティブだった。しかし、複数の事業会社と、ファンドからの提案を比較検討した結果、結果的にファンドが設立したSPC(特別目的会社)に譲渡の上、自ら再出資するスキームを選択した。
事業会社からの提案も、譲渡対価において納得感のある条件提示だった。
しかし、最終的な判断基準は成長に必要となる適切な経営資源をスピーディに得られることに加え、企業の成長(=株式価値の向上)を目指す「同じ船に乗る」というファンドの提案に賛同できた点だ。
これまでの企業価値は創業者の取り分(=今回の譲渡対価)、取引実行後の企業価値向上は役割に応じてシェア(=社長は再出資した株式価値の向上、主要役職員へのストックオプションで享受)という合理的な考えもファンドから示されたことで、ネガティブなイメージも払拭された。
社長は引き続き経営を委任され、①~⑦の計画実行はファンドが派遣する社内外の人材から全面的にサポートを受けている。
まとめ

本件のポイントは「社長自身が成長計画を描いていたこと」「経営が好調なうちに次のステージへの準備を始めたこと」と言える。
好業績で成長のポテンシャルはあるが次のステージに進む踊り場を迎えているような企業にとっては資金・人材・ネットワーク等のファンドの機能を活用することで、計画達成の確度やスピードを上げる有効な手段と考えられる。
今回は成長ステージにある企業の事例だが、本来のポテンシャルが発揮できていない低成長企業、事業再生の局面など、企業がステージを大きく転換する局面においてファンドという外部の機能が果たす役割は大きい。
第2回は『売れにくい「無借金」企業』を予定しています。












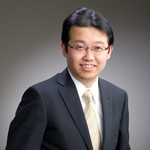

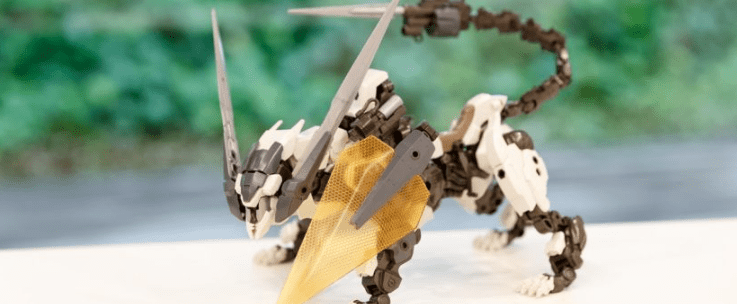
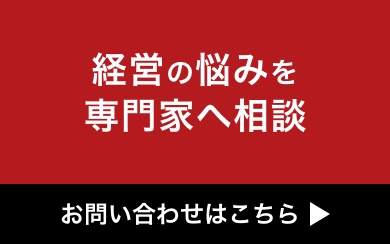
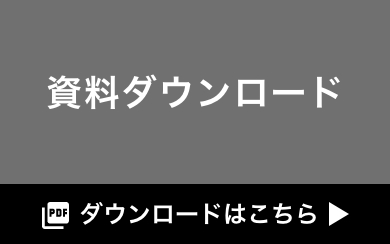



コメントが送信されました。