読了目安:16分
【回想録】 内側から見た経営コンサルティング(MC)の歴史 (中編)~コンサルティングの認知拡大、そして突然の「組織解体」
前編は、会計事務所系(総合系)ファームが混迷期を迎えるところで終了。また、アクセス数やランキングから見て、中程度に関心を持っていただいたことも確認した。 今回はコンサルティングが多様化、専門化する時代を経て、日本経済が最悪期を迎えるまでを描きたい。 なお、前回に引き続き、個人的所感であるため、ファーム名等の固有名詞の使用は、極力避けさせていただいた。
戦略コンサルティングファームへ

自身が身をおいていた会計事務所系ファーム。同社社長は、買収企業となるIT企業の元No.2であったという経歴の持ち主だ。
外資系でありながら業績低迷していた同ファーム日本法人において、“働き方”を含めた組織や業務の大改革を実践。その記録としての著書も出版され一躍有名となった。大手ファームや企業では当然となっている“フリーアドレス制”も同業界で初めて導入したとされている。
さらに、同ファームは中途採用、特に、業界経験者を中心に採用を強化し、組織を急拡大させていた。後に株式公開を果たす競合ファーム“戦略グループ”とも対峙しようとしており、1990年代終盤にはビッグ5の他のファームと経営統合。ファーム名・ロゴ並びに全社組織を再編するとともに、部門名・サービス名も改訂し、戦略コンサルティング部隊を立ち上げる。
対外的には、クロスインダストリー戦略グループと呼称。私は、同経営・事業戦略サービスライン(またはチーム)へ所属することとなった。サービス名は、アルファベット三文字で表していた。
“クロスインダストリー”とは、業界にとらわれず、広くさまざまな業界を担当する意味である。サービスラインとして、組織・変革戦略、IT戦略も提供。同戦略グループの人員は、100~150名体制であったと記憶している。
同グループでは、中途採用者向けの上級トレーニングとして、海外ビジネススクールのケーススタディ教材を使用した合宿形式の研修も存在した。私が海外MBAホルダーであったこともあり、複数名からなる講師陣の1名としても抜擢された。
一方、同ファームの営業アプローチは“ビジネスコンサルティング”に近く、“戦略グループ”が後続フェーズ(業務やIT案件)の“プリセールス”(先兵)部隊という考え方が主とも聞いていた。
同ファームはIT企業に買収されることとなり、独立性の問題として「競合から、コンサルティングサービスを受けるわけにはいかない」と言われた逸話も前編で話した通りである。戦略コンサルティングでは、“視座(PoV)”の高さや客観性も重要となる。同じ“想い”を持った同グループの仲間たちは、次々とファームを去っていった。私もその一人である。
コンサルティングの認知拡大、人気就職先に

当時の一つの潮流は、コンサルティングの多様化もしくは専門化であろうか。
例えば、海外または外資系企業の中には、MC(経営コンサルティング)部隊を内包する企業が多く存在していた。知り得る限り、乗用車、商用車、製薬、生命保険などの業態だ。
他には、本来定性的な価値である“企業ブランド力”を数値化またはランキング形式にするという動きもあった。そのためか、世界的な広告代理店グループが保有するブランドコンサルティング会社が、日本法人としても強く認知され始めていた。
日本の大手広告代理店が、海外業務提携により同ファームブランド名を使い始めるなどの動きもあった。国内大手広告代理店が自身の社名を付したコンサルティングファームも、2000年代初頭に登場する。
元々、広告代理店に組織や機能として存在するStrategic Planning(戦略プランニング)や、マーケティング手法、消費者動向調査などの分析力を活用したものではないかと推察される。
組織・人事を専門に行う外資系を中心としたファームや製薬・医薬品等の業種に特化したファームなども現れた。コンサルティングが一つの業種として企業、学生からも認知され、新卒・中途の人気就職先として上位にもランクされるようにもなっていた。
新興戦略ファームへの移籍

某電機メーカー(格好良く言うと、グローバルコングロマリット企業。主事業の他、エンターテイメント、ファイナンス事業を展開)が、企業グループ内に戦略コンサルティング会社を持つこととなる。国内系としては、初の試みであり、知る人ぞ知るという存在であった。
当時、戦略ファームの国内一大クラスター(集積地域)であった、東京の赤坂・六本木・神谷町地区(アークヒルズ、現・城山トラストタワー、現在の麻布台ヒルズ周辺)の某ビル高層階にオフィスを構えた同社。その特異性と、同メーカー製品が個人的に好きであったこと、戦略ファームに強い人材エージェントからの紹介を受け、この国内独立系・新興戦略ファームへ私は入社することとなる。
本来であれば、このままファ-ムが存続し続け、勇退までを迎えることができれば御の字ではあった。
だが、そう上手く運ばないのが人生である。
プリンシパルクラス(またはシニアマネージャークラス)であったため、ケースインタビューは、さすがに実施されず。これまた偶然だろうが、私を含めたプリンシパルクラスの4名の苗字が、アルファベットで皆Mであったのも印象深い。
今でも覚えているのは、最終面談のCEOからの質問である。「これから、何をどんな風にやっていきたいか、今の心境を表すとしたら?」という漠然としたものだった。
私は、即興で「真っ白なキャンバスに、色々描いていきたい」と答えた。
また、そのCEOから聞き、耳に残っている言葉として、「経営者は孤独である。その経営者に寄り添うのが、MCの役目」がある。なぜか、この言葉が今でも鮮烈に思い起こされる。
この頃、米メジャーリーグでは、イチローが活躍中。私も、「グローバル市場を舞台に、経営のプロ=MCとなりたい」と、意気揚々としていた。
同ファームメンバーは、仮説思考で有名な外資系戦略ファーム、金融や自動車業界、戦略的コスト削減に強いと言われていた外資系戦略ファーム、会計事務所系戦略グループなどの出身者が多勢を占める構成となっていた。トレーニングプログラムも、これらのファームに準じた内容だった。
私が属していたファームの戦略グループ出身者は、後にも先にも私一人。採用面接で複数回課されていたケースインタビューの難易度は非常に高く、海外MBAホルダーであろうと通過率は低かった。
同ファームはメディアとの関係も太く、有名雑誌社が経営論や論理思考などの経営テーマを特集する、和製季刊ビジネス雑誌(既に廃刊。海外で言うHBR= Harvard Business Review=と同等とは言い過ぎか)では、カナダの戦略論大家であるH.ミンツバーグの著書であり、戦略を10の“宗派”(School)へ分類し総括した「戦略サファリ」(原題“Strategy Safari:A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management”、1998年刊)の紹介記事を掲載していただいたこともある。
最盛期、同ファームは総勢20名を超える規模となった。ブティック系(小規模のファーム、特に、海外で使われる用語)の中では、中規模に分類される。
初の業務は提案活動だった。同ファームの特徴は、ワークプラン構築と独特のピッチ(スライド)作り(同ファーム出身者・OBネットワークが、その後のコンサル人生、縁によるつながりを深めた、といっても過言ではない)。メッセージの重要性と、スケルトン(雛形)スライドを何枚も連ねて上手くストーリーが流れていくことを、非常に重視していた。
さながら、漫画家と編集者が協業して作り上げる漫画の“コマ割り”である。当時、私の一大“傑作”(?)は、教育サービス企業への顧客戦略や法律事務所の成長・組織戦略の提案書であった。
事業再生コンサルティングの登場と「事業デューデリジェンス」の到来

2000年代中盤から2010年代にかけ、日本経済は低迷を続けた。不良債権、債務超過が問題となり、廃業、倒産に至る企業数が増加し、企業経営は最悪の事態を迎える。
国内で99%を占める中小企業のみではなく、バブル崩壊直後の山一証券や北海道拓殖銀行の経営破綻に匹敵する大企業の破綻懸念が増大したのもこの時期である。
そこで登場したのが、当社(フロンティア・マネジメント)の祖業とも言える事業再生や企業再生サービスだ。そしてその旗手役となったのが、官民共同組成の投資ファンド(再生機構)である。
倒産寸前の企業を復活・再建させるというもので、窮境の原因究明から施策導入までを一貫して行う。具体的には、財務や業務・組織に至るリストラクチャリングにはじまり、経営陣総退陣、莫大な負債の免除(金融機関による債権放棄)、新たな株主(スポンサー)探し、または、法的整理・清算処理である。化粧品メーカーや小売業の再生が有名だ。
思い起こすと、この機構ができ、事業デューデリジェンス(BDD)という言葉もこの頃生まれていた(正確には、概念が海外から持ち込まれた)。通常、デューデリジェンス(DD)と言うと、財務DDを指すことが多かったのではないかと想定される。前職の会計事務所系ファームでは、海外拠点絡みの案件でBDDをやっていた記憶がある。海外留学から一時帰国した際に知ることとなった。私も「デューデリジェンスって何?」という感じであり、無論、関心もない頃である。
前後して、ITバブルが弾けるとともに、有名経営者のITベンチャー企業事件(インサイダー取引疑惑)も発生。「金融検査マニュアル」の発行(現在は廃止)やそれに基づく「実抜計画」(実現可能性の高い抜本的な経営再建計画)が言葉として使われ始めるのもこの頃である。
この機構が募集をかけていることも知った。関心を持った私は非常に悩んだ。戦略ファームへも入社し、プリンシパルというそれなりの職位に就いたにもかかわらず、「転職するのか?」と自問した。
要件や採用基準も厳しそうであったし、どう見ても有名な外資戦略ファーム出身者、「地頭」を重視している採用にしか見えない。実際、どうサービスを提供していくのか、知る余地もない。
この頃、事業再生・企業再生は、言葉としても浸透していないし、関連書籍としては、当時、「ターンアラウンド・マネジメントー企業再生の理論と実務」(原題“Corporate Turnaround”、スチュアート・スラッター、デービッド・ロベット、1999年、邦訳は2003年)しかない。結局、戦略ファームに踏みとどまることになる。
「ネーミング」の逸話

事業再生のカテゴリーも米国発。こうなると、コンサルティングや経営(学)の世界は、発祥も進展も米国が中心となる。英語では、Turnaround(TA)となり、ターンアラウンド・マネジメント協会(TMA)日本支部(TMA-J)が、「事業再生」、「企業再生」という言葉を当てたということだ。
うまいネーミングだと思う。直訳すれば、“転回”にしかならない。この逸話を知ったのは、同協会で認定する事業再生士(CTP)を取得し、会員となったことがきっかけである。
時の政府から妙訳を頼まれたそうだが、実際のところは不明である。また、TAの某トレーニング講座にて聞いた話では、西日本の地銀(数年前に持株会社化)が、日本における事業再生の方法論化やアプローチを主導したとのことである。
そのトレーニング講座の講師と、TMA-Jの直近セミナーにて「コロナ禍後の事業再生、金融機関の在り方」といった講演を行った再生実務支援者もこの地銀(さらに金融庁)の出身者である。
TMAアジア会合(香港)へ、コロナ禍の数年前に出席した時のことだ。参加した日本人は私一人。会合で感じたのは、事業再生の仕組みにおいて、海外では法的処理が多いことに対し、日本では私的整理が独自の発展を遂げたのではないかという点である。TAは、所属していた新興戦略ファームで新たに展開しようとしていたサービスの一つだった(実現には至らなかった)。
突然の組織解体

国内不況のあおりは、所属ファームの親会社である電機メーカーにも及ぶようになっていた。
親会社のCEO(故人。引退後、ベンチャー育成機関創設)は、文系出身(通常、製造業は理系出身者が多い)であり、斬新なアイデアを次々に世に出した。今で言う、“バーチャル組織”(ネットワーク組織、稲盛和夫氏の“アメーバ経営”に類似か)のような構想も打ち出していた。
サービス業へも進出するなど多角化経営も行った。グループ内に戦略コンサルティング会社を保有するのも、その一環。ただし、その概念は当時、「斬新過ぎた」ことと、ネットワークインフラ自体も低品質・低速度、ギガ通信・光通信技術もなく、普及することはなかった。
親会社である電機メーカーは、「選択と集中」を行い、「本業である製造業へ回帰」することとなり、突然、ファームは親会社の管轄役員により、即日、組織解体されてしまうことになる。
猶予は、翌3月末までの1カ月。私がプロジェクトマネジャーを担当していた執行中の案件は、法人契約から個人契約へ切り替えられることとなる(後で語るが、フリーランス=個人事業主による業務委託契約と同義)。
親会社の人事部が、組織解体の決定した我々のオフィスを訪ねてきた。親会社社内または関連会社への異動の斡旋のためだ。実際、異動したジュニアクラスも数名いた。
ところが、ミドル・シニアクラスとなると勝手が違う。報酬体系が全く異なり、プロパー(正社員、叩き上げ)が好まれる当時の風潮から、異動は希望通りには叶わない。
個人契約が続く場合は良いが、その後が大変であった。労働市場が活性化していなかったのである。自身の意思とは全く違い“フリー”となった私は路頭に迷うこととなる。
「居候先」で戦略コンサルティング
結局、所属していた“戦コン(戦略コンサルタント)”つながりで、多くのメンバーの所属元であった、外資系戦コン出身のブティックファーム社長のオフィスへ転がりこみ、“居候”することになった。同社長とは思考や作業の進め方で嗜好が合い、意気投合。今でも連絡を取り合う仲である。
大手・中堅企業向けの戦略コンサルティングを手伝っていくことに。先般の会計事務所系に続いて国内次点と恐らくなるであろう、BDDの案件を手掛けることとにもなる。
2000年代の中盤である。相手は、有名なアクティビストファンド日本法人。報告書のコア部分は私が手掛けた。
現在の一般的なBDD報告書とは構成が全く異なっていた。このDDの過程で、寡占度を示すHHI(ハーフィンダール・ハーシュマン指数)も知ることとなる。
(後編へ続く)
【回想録】
前編
続きはこちら
【回想録】 内側から見た経営コンサルティング(MC)の歴史 (後編) ~世界を巻き込んだリーマンショック フリーランスを経て、再びファームへ















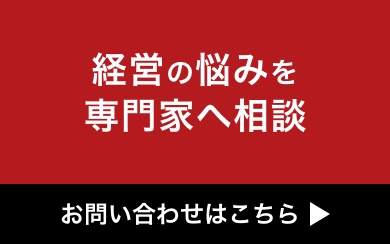
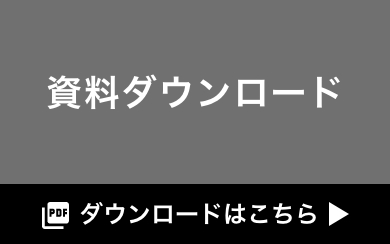



コメントが送信されました。