読了目安:23分
【回想録】 内側から見た経営コンサルティング(MC)の歴史 (特別編・下) ~異なる文化での経験が現在の糧に
特別編・上では、私の海外ビジネススクールへの挑戦までの軌跡を語らせていただいた。今回は、実際にどのような日々を送ったのか、そして私がその経験から得たものについて、紹介させていただく。
実際のビジネススクールでの授業

さて、私が入学したカナダのビジネススクールの特徴は特別編・上で先述のように、“ケース・スクール”だったこと。その点で良かったのは、常に、“経営者”の視点で、2年間で合計600以上のケースを取り扱ったことだ。
1日に3ケースずつ、週15ケース、年間420ケース(2年目は選択科目となり、科目数も減る)。定期試験は授業数を減らさないよう週末土日に実施という徹底ぶりだった。
さらには、ケーススタディの解法について、スクール独自の小冊子が存在したことも良かった点だ。別名“フレームワーク・スクール”と言われるように、ケース分析で使う独自の“枠組み”や“ひな形”、加えてレポート(英語では、Paper)やケース試験(Case Examと呼称)で回答に使う、フレームワークまで存在した。
逆に難点は、単元で必要となる基礎知識はすでに保有していることが前提となっていたことだ。通常のスクールでは、1年目の必修科目であるビジネス経済学やビジネス統計学(または定量分析)、財務会計の授業が存在しなかった。
会計学は、いきなり管理会計(初回単元は、BEP=損益分岐点)から開始された。私自身、商社経験からの簿記、コンサルティング経験からの簡易な財務会計・管理会計の知見があったため助かった。
一般的な海外留学生には、こうしたビジネス英語による知識がないこともあり、9月入学前の1カ月間は“サマースクール”として簿記・財務会計の補講が実施されていた。
私が通ったビジネススクールは大学学部のキャンパス内に所在し、同大学の一学部であった“統計学部”の夏期講習を1カ月程度受けることにした。英語で受ける統計学はかなり高度ではあるが、系列大学院在籍のため、安い授業料で受けることができたのである。
ケーススタディの実際
ケーススタディによる授業の進め方には“定番”がある。
まず、教授が教室(各スクールで異なるが、50、60名程度か)の中で、学生一人を指名し、論点を説明するように求められる。すなわち、誰がDM(意思決定者)であり、その人物が置かれた経営、事業上の環境や課題は何なのか。その解決策を導出していくにあたり、何をどう分析していくべきか、などを述べていく。
教授は最初の発言(状況・課題特定)を要約し、議論を進めるために、他の学生に対して問いかけを続けていく。すぐさま、多くの学生が再び挙手、発言の指名を求め、眼力やジェスチャーで“当ててくれ”とアピールする。
議論がいくぶん進んだ時点で、教授は議論を中断し、そのケースで教えるべきテーマについて、要点を黒板に総括していく(今では、プロジェクターで要点のピッチを投影か)。
ところで、教える側の教授は、すべての生徒の名前を記憶しているのか?
そんなことはない(無論、成績優秀者など、“お気に”の生徒がいれば別だが)。討議が行われる、馬蹄(Horseshoe)型と呼ばれる湾曲したテーブルの前側には、細い溝があり、その溝へ各生徒は自分のネームプレートを差し込むようになっている。

出所:Richard Ivey School of Business, the University of Western Ontario
https://www.ivey.uwo.ca/mba/academics/curriculum
スクールにより特徴があり、同スクールでは、伝統的に見えやすくするため、黒背景に白抜き文字としている(この逆もあるらしい)。また、溝で隠れるプレート下部には、持ち運び用に、3連リングフォルダーへバインドできるよう穴も開いている。写真をよく見てみると、ネームプレート自体が当時よりも縦長になっており、少しは進化しているようだ。
このネームプレート。私は当初、下の名前を短くし、“Kazu”としていた。ただ、このスペルでは、uを発音するため、“Kazoo”(カズー)に近い発音となり、文字通り、“おもちゃの笛”となってしまう。
2年度目からは(実際には1年度目からも黒テープでu を隠して、おもちゃ感は払しょくした)、作り変えた “Kaz”とした。ネームプレートを失くしたと嘘をつき事務局へ別途お金を支払い作っていただいたのだ。こんなことは実際に体験してみないとわからないものだ。
ケース教材では、「実際どうなったか」の結果までは書かれていない。また、当時の鉄則ではインターネットでの“事実”の検索は“ご法度”となっていた。あくまで、ケースに書かれた内容に基づいてのみ、分析・提言を行うのである。
場合によっては、“続編”となるケース(Case B、Case C・・・と続く)が配られ、議論を進展させていく(次回授業へ続くこともある)。
学生が躍起になって挙手し発言をするのは、この“Class Participation”(議論参加)が成績(Grade)の大半を占めるためである。
学期初めに配布される科目毎の “シラバス(講義要項)”には、その比率が記されている。発言70%、期末・中間筆記試験結果30%、などだ。
留意したいのは、発言すれば“ポイントが稼げる”のではないという点だ。議論を発展させるような内容であれば加点されるものの、“的外れな”内容の発言では、逆に減点されてしまう。
“シラバス”の別紙(科目毎要項)には授業毎に議論を行うための数問の質問も記載されていた。質問に基づいて、前日またはそれ以前に予習を行っておかないと大変なことになる。
そうでなくとも、当日議論がどの方向へ進んでいくのかは予想できないため、いくつかのパターンを準備して授業に臨んだ。とは言え、当日の授業では、議論の流れを読み取りながら、挙手・発言を試みるのだ。
1日当たり3ケース(授業)あり、1つのケース、ページ数にして20~30ページの予習には、最低2時間を要した。そのため、1日で対応できるのは2ケース程度であり、不足する分については、週末の土曜日・日曜日にまとめて行っていた記憶がある。祝日は授業もなく予習に充当できたため、大変喜ばしかった。
工夫(特に1学年目の後期)は、自らの発言の点数をつけ管理していったことである。
全授業で毎回発表できる確率は低かったため、発言ができていない科目については、ケースの予習も念入りに行った。一方、発言がある程度できており、かつ、評価が良さそうな科目については、予習を含めて数回“手を抜く”、といった“濃淡”をつけた。
こうした工夫や管理をしたことで、ある程度の成績を維持し無事“生存”(卒業)できたのかもしれない。振り返ると、楽しい思い出など全くなく、まさに“サバイバル・ゲーム”であった。
1年目は、予習のための“スタディ・グループ”を組成しチームワーク力向上を図ることは、どのビジネススクール(BS)でも一般的ではある。ただ、特色として、チームワークを強みとして持つスクールもあれば、そうでないスクールも存在する。
私が選択したスクールはどちらかというと後者であり、日本人は私一人の“超マイノリティ”(人種や国籍)であったため、スタディ・グループを作ることにも苦労した。グループで行う予習が成績に直結すると皆わかっていたためである。すると、利口そうな者同士が“集まる”のだ。
留学生の比率は全学生数の30%程度であったが、カナダは “移民大国”であり、当時、中国人、インド人、他は中南米出身者が多かった。
私は“学生ビザ”で入国していたのだが、中国人の大半は“移民権”を取得していた。「卒業後、ビジネス大国である米国で仕事を得るため」という。
NAFTA(北米自由貿易協定)経済圏=カナダ・米国・メキシコでは、移民権を持つと就労が可能となっていた。私もカナダ“移民権”取得申請に動いたが、北米での採用通知が必須条件となっており、獲得はならなかった。
標準的な日本人学生と比べると、中国人学生は外資系企業に勤務経験がある、すでに工学で修士・博士号を取得している、富裕層の子女であるといった背景の違いも見受けられた。
言語的な構造や発音(母音数の多さ)からか、TOEFL、GMATは高得点者が多かったことも特徴である。全般的に彼らの会話は聞き取りにくかったが、国際都市である香港や上海在住者は英語の発音は綺麗であった。
様々な種類のケース教材

どのスクールでも必ずといっていいほど使用される日本関連のケースは、生産管理(Operations Management)科目における、トヨタの“カンバン”システム(JIT)である。
逆にその科目で、当時日本人にはほぼ知られていない教科書的読本があった。
The Goal。著者はイスラエルの物理学者エリヤフ・ゴールドラット、原本は1984年に出版。専門書ではなく、物語風の内容である。
確か、工場長である主人公が自身の工場を救う話と家庭の危機の話とを重ね合わせていた。いわゆる、“(業務)プロセス”の“ボトルネック”の話である。何でも、これを日本人に読ませると、世界的な競争力を上げてしまう、といった危機感から、著者が和本の出版を長年許さなかったそうだ。
1年時、それもかなり早い段階でレポートを書く宿題が出されたのだが、私一人を除き、皆読んだことがあるとのことだった。これも帰国後、2000年代初盤に和訳本が出版される。
私のスクールで秀逸だったケース教材は、当時、日本へ進出して2年と間もない“スターバックス”。恐らく世界初の制作ケースだ。
他、欧州の1年制で有名なスクールが作成した“会計系トップファーム戦略グループ誕生”のケースを、総合経営(General Management、または戦略)の授業で使用した。
その科目の教授は、私がクラス(学年も意味するが、日本語の組の意)唯一のコンサルティングファーム出身者であることを知ってか、一番に指名し内容を説明させていた。日本では、新卒入社は珍しくないが、海外ではMBA卒業後初でファーム入社することが一般的なためだ。
最新の設備での授業と低仕様のノートブックPC

今では珍しくもなんともないワイヤレスWi-Fi。当時は有線ネットワークが主流だったが、校舎内のいたる所に無線LAN機器が設置され、北米でも数少ない最先端技術を誇るスクールだった。定期試験やレポートの回答は、Wordで作成した回答用紙を、ネット回線を通じて電子メールで提出するスタイルだった。
当時のノートブックPCは、重量もありHDD容量が数GBで30万円以上もした時代だ。記録媒体は数MBのフロッピーディスクもしくはスティック型USBメモリ。ビジネスモデルで有名となった米PCメーカー製を高額で泣く泣く購入し渡航した。
今以上に、PCはフリーズや故障を起こすことが多かった。大学近隣の同PCメーカーと提携している電器屋で“オンサイト修理サービス”を利用することもあったが、サービス品質は最悪・最低であった。
PC分解後、ネジが1つ残ることもあった。当時、英語でクレームを入れ、再組立させたこともある。同スクールのITサポートデスクに相談することも度々。デスクトップ・スクリーンへ映し出される日本語表記の文章や単語を英語で説明し、頻繁にサポートしてもらったことを覚えている。
参考書探しも楽ではなかった

思えば、留学前に参考書を探すのも大変だった。
今では、有名な“MBAシリーズ”の書籍が全科目にわたり存在し、単元毎に簡潔にまとめられている。だが、私の時代には皆無。“経営学史”のような経営学の古典的な書籍は存在するものの、学術・専門的であり、財務や管理会計、統計学、ビジネス経済学、生産管理(オペレーションズマネジメント)なども良い参考書などは見つけられなかった。
“MBAシリーズ”なる書籍を日本でビジネスにすれば、さぞかし儲かるであろうことも考えていた。残念ながら、1年次が終了する頃には、専門職大学院を開設した専門学校から出版が開始されていた。身の振りの早さはさすがである(創始者兼社長はケース・スクール出身)。
何故、海外のビジネススクールなのか(だったのか)?

なぜ、海外のビジネススクールだったのか。これには、大きな理由がある。
当時は、海外でしかビジネススクールは存在しなかったためである。厳密に言うと、老舗である私立の経営管理学大学院は国内に1校存在した。その他はいわゆる専門職大学院ではなく、学部の延長、よりアカデミックな(一学問としての、または研究分野として)内容に重きを置く修士課程(または博士前期課程)大学院しか存在しなかったためである。
留学から日本へ戻り、恐らく、2000年代初め頃であろうか。国内にも“専門職大学院”という制度ができ、社会人を対象とした実学を重視する大学院、ロースクール(法科大学院)と共にビジネススクールについても、国立・私立で多く設立された。
結局、私は国内2校と、英、米、カナダの合計20校くらいに出願した。国内のうち、1校は老舗の経営管理大学院、もう1校は日本に開校したカナダの日本校だった。カナダの日本校とは縁があり、卒業大学の校舎を使用、初年度待遇で給費制にも選抜された。
老舗経営管理学大学院は合格。経営学の内容に特化した英語試験もあったし、当時、すでに経営コンサルティング業界に身を置いていたことも、合格に役立ったとも思われる。
インタビュー(面談試験)も存在したが、コンサルティングに身を置いていたためなのか、同スクールが全日制(昼間の講義もあるため、仕事は休職もしくは退職する必要あり)のためなのか、教授陣からの質問はかなり辛辣なものであったことだけは覚えている。
また、米国のほか、英国の当時のトップ校にも合格をいただいた。ただ、英国の方は金融やファイナンスに強い講義中心のスクールで、自身の希望とは異なったこともあったが、同校が所在する首都ロンドンでの生活費が非常に高く、費用を捻出できず断念せざるを得なかった。英国はEUへはすでに加盟していたが、基軸通貨はポンドであり、当時はポンド高だった。
ここも人生の選択肢(分岐路)だったのかもしれない。英国には、珍しく海外留学生向けの留学費補填のサービスが存在(米国に海外留学生支援ローンは皆無)したし、外資戦略ファームの採用指定校の1つともなっていたようなので、その後の人生も大きく変わった可能性はある。
海外MBA留学が衰退した理由とは?

では、海外MBA留学が衰退した理由は何か。
これも、確認したわけではなく、個人的所感になるが、当時から「リターンは何?」という議論は存在した。
相当高額な学費、1年間の生活費も含めて1,000~2,000万円という割には、日本では、MBAを取得したからといって給与が上昇するわけではない。
当時は、1995年の円高傾向から円安局面にあり、130円前後の為替で推移していた。直近の140~150円前後からすると、似たような状況にあったともいえる。今以上に円安基調が継続されていくのならば、金銭面でより“リターン”を得ることは難しくなっていくのかもしれない。
また、企業派遣が中心のため、役職が上がる(または昇進が早くなる)わけではない。唯一あるとすれば、外資系の戦略コンサルティングファームや投資銀行へ転職しやすくなる、くらいである。
また、老舗の国内ビジネススクールや専門経営大学院でも、いまだに、卒業要件として研究論文を提出させる、アカデミックな色彩が残るところも多い。入学審査においても、研究計画書を提出させるスクールが多く残っているとみられる(これは、後編でも話したが、国内MBA留学予備校での講師経験による)。
欧米のビジネススクールでは、こうした研究計画書を入学時に課すことはなく、入学に比べて卒業要件は低い(履修単位を修得していれば良い)。スクール側も、PRや受験者数・入学者数(MBAランキング)へ大きく影響する、“就職先”(当時は、投資銀行か戦略コンサルティングファームが人気)しか気にしない。
国内大手企業による社費派遣は、2000年中盤以降、中止する企業も激増した。理由は、訴訟問題となることが増えたからである。
社費で派遣しても、帰国直後、戦略コンサルティングファーム等へ安易に転職してしまう人材が増えていた。年俸水準も転職により増えるからである。
敗訴し学費や同期間の給与の全額返済といった判例も多数出るようになった。これに対し、外資系投資銀行では、入社後その費用を負担するところも出たとか出ないとか。
もう一つの理由は、高額な学費を払うことのない、代替手段ができたことだろう。先述したが、国内のビジネススクールでは老舗のほか、国立、私立でも専門職大学院が好評となったことや、“MBAシリーズ”書籍出版で有名な、私設ビジネススクールもあり、卒業生や良い評判も増えたことではないか、と考えられる。
国内ビジネススクールの1年間の学費水準(海外の場合は生活費も含む)は、高額であったとしても欧米の1/4程度(私立の場合)、国立に至っては1/20程度である。
また企業としても、ビジネススクールより実学での経験、例えば事業デューデリジェンス、M&Aにおける企業価値算定(バリュエーション)、そのベースとなる財務モデリングなどを重視することになったからではないか。
無論、企業価値算定などは、MBAの2年間のコースのうち、1年目の必修科目である財務(ファイナンス)の一単元として教わるものの、財務モデリングの細かいところまでは習わない。
今では、財務モデリングに特化したトレーニングスクールも国内に存在するし、オンラインで履修するコースも存在する。わざわざ、お金をかけて海外へ学びにいく価値も薄れたということではなかろうか。
私が海外で学んだものとは何か?

時代と置かれた環境は全く現在と異なるため、参考にはならないかもしれない。
私が学んだものとは、当時一般的かつ平均点な回答であった「国際ネットワーク・人脈を広げる」といった単純なものではない。
私が通ったスクールでは、就職のための部活動も盛んであり、私も経営コンサルティング(MC)部へ所属していた。
また、2年目の選択科目のコースでは、経営コンサルタント育成コース(CDP: Consultant Development Program)が存在していたので、履修した。実際、“発明家”に対する事業化のコンサルティングも実施できた。
さらには、同国での経営コンサルタント協会(CAMC)主催の、CMC(Certified Management Consultant、認定経営コンサルタント)の試験を卒業後、日本からカナダに渡り西海岸で8時間のケース試験を受験した。
合格して登録後数年してから、日本の同等の団体にあたる全日本能率連盟(AFMO)へ移籍。マスター永久認定資格(J-MCMC)となった。こうした事例は初めてであったという。
こうした海外での経営コンサルティングの“やり方”を学ぶことができたのは大きな利点である。
休職していたコンサルティングファームのニューヨーク事務所へ転籍し、勤務する話も内々に進めてもらっていたが、最終的に話は消えてしまった。結局、卒業後、日本に戻ってくることになる。
その翌年、あの“9.11事件”が勃発する。同事務所はまさしくWTCビルに隣接するフィナンシャルセンター(地区)ビルであった。同事務所へ入所していたとしても、客先へ常駐していれば問題はなかっただろうが、難を逃れた感じではある。
英語で経営学を学ぶということ、あるいはそのケーススタディを体験することなど、細かい点で学んだことは色々ある。重要なのは、異なる文化において、仕事をすること、コミュニケーションを取ること、リーダーシップを取ることはどういうことなのか、などについて、全般的に学べたことが、経験として有意義であった。
そして、最後に
あえて現状と異なる海外のビジネススクールの話をした理由とは。
私がMCを生涯ワークとして志望した原点に近い“モノ”が、ケーススタディにあったから、と付け加えておこう。さすが、欧米のビジネススクールである。
「経営者」とは何か? 「経営者」になるための資質や素養とは何か?
昔と比べ起業する若手も増えた。起業すれば、形式上は経営者となる。見方によっては、フリーランスも(個人)経営者である。
そして、私が現在所属する「経営執行支援部門」は、「経営者」を派遣する部門である。差別化やブランド戦略のためか、志望される若手やコンサルティング経験者も多い。
「経営者の本質とは何か?」
今一度、原点に立ち返り自問していただきたい。
こちら、“特別編”も長々と語ってしまった。数カ月にわたり連載させていただいた【回顧録】はいったん終了とさせていただきたい。ご精読につき、深謝申し上げたい。















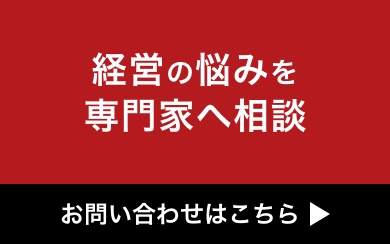
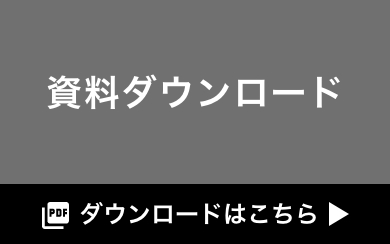



コメントが送信されました。