読了目安:18分
【回想録】 内側から見た経営コンサルティング(MC)の歴史 (特別編・上) ~海外ビジネススクール、当時の動向と現在の差
3編にわたり、自身の経験を交え国内外の経営コンサルティング(MC)の歴史を、企業経営動向とあわせて回想録風に語らせていただいた。
前編では、海外ビジネススクール(経営学大学院)が外資系の戦略コンサルティングファームへの登龍門であったことを伝えた。
本編は特別編として、現在とは全く異なる状況であったことも認識した上で、自身が海外ビジネススクールに挑戦した当時の様子を振り返らせていただければと思う。
企業からの派遣が全盛の時代

日本経済がバブル期だった1980年代中盤から2000年代初頭にかけ、大手企業、特に、都銀・証券などの金融機関、総合商社では、選抜を経た社員の、社費負担による2年間の欧米ビジネススクールへの派遣が全盛だった。
企業が派遣を行っていた理由の詳細はわからないが、優秀な人材を集めるための“道具”の一つであったのかもしれない。もしくは、それだけの収益力が大手企業には残っていたのだろう。同制度の有無は、私も新卒就職の際に企業選択の一つの判断基準とさせていただいていた。
それでは、海外または欧米ビジネススクールを目指す目的とは何だろうか。本来はここに焦点が当たらねばならない。
“昭和世代”は、“浪人”してでも志望大学を目指す、偏差値・合格偏重の時代。MBA(Master of Business Administration、経営学修士号)という学位取得自体が目的化してしまっていたのかもしれない。
では、本場米国のビジネススクール(BS)にその源流を辿ってみよう。
同国トップBSの一つで、事例をもとに課題解決に取り組むケースメソッドを主体とするあるスクールでは、General Manager(GM)、すなわち、“経営者”の育成を目的として位置づけている。
教材として使用するケース(企業事例)においても、“経営者”が“意思決定者”(Decision Maker)、または“問題解決者”(Problem Solver)として、ケースの導入部に登場。経営または事業上の課題または“壁”に直面し思い悩む場面から開始されるのが、一般的な構成となっている。
とは言え、ビジネス・スクール(運営)も “ビジネス”(事業)である。
BusinessWeek誌などの米国ビジネス雑誌では、隔年で国際化(海外留学生)比率、今で言うと、多様性(ダイバーシティ)なども含めた指標で、ランキングを公開している。真の目的は、ネイティブのためのネイティブによるGMの育成である。
実際、バブル崩壊後も、Japan as No.1の“神話”は受け継がれ、そこから“学び”を得るため、合格させる学生の国籍割当もあったという。
トップスクールでは、日本人の学生の多くを合格させていた。あるランキング上位のスクールの日本人学生数は、全盛期に30~50名にも上った。その後は経済成長を背景に、中国人の合格者数が激増したとも言われている。
私が実際に留学した1998年当時(中国は今ほど経済力・国際競争力を示しておらず、GDPも世界第2位ではなかった)、各スクールの日本人学生数は最大でも5~10名程度であった。
転職サービスのAXIOM(アクシアム)独自の統計によると、日本人の欧米MBA留学数は現在200名前後、2000年代初頭の300名からは減少傾向にあることが読み取れる。
バブル期前後は500~1000名と言われていた記憶があり、30年の間に半減以下、もしくは1/3~1/5程度となっている。
日本人卒業生の推移

※人数は私費・公費の合計、5カ年毎の表記、1年制スクールについては、2025年の人数表記なし
出所: 「日本からのMBA留学生数の推移」(AXIOM)https://www.axiom.co.jp/mba/table/table001
統計データを使い、有名な欧米スクール10校の日本人卒業生数を、2000年~2025年について分析を試みた。人数は私費・公費の合計である。
過去25年間(5カ年単位)で2割弱の減少(2000年比)となっている。有名スクールに関してMBAは根強い人気があるようにも見受けられるが、ひところとは異なり、1学年20~30人を超えるような日本人学生を抱えるスクールは一部に限られている。10名以下が主流のようである。
興味深いのは、各スクールの特性であろうか。経営全般(General Management)やマーケティングに強いとされるスクールについては大幅、または顕著な傾向とまではいかなくても減少しているのに対し、ファイナンス(財務)に強いとされる(ファイナンス関連の教授陣の高評価など)、特に欧州のスクールについては増加傾向にある(ただし、財務に強いとされるが、マンモス校かつ日本人数が多いとされた米国のスクールを除く)。
MCの歴史を顧みた結果からみると、M&A等に代表されるファイナンス系スキルが重視されるようになったため、高額な学費をかけてでも海外MBAを取得したいという意向が現象として現れている可能性もある。
また、欧州は1年制のスクールも多い。1年目には必修科目を履修、2年目には専攻科目、選択科目を履修する2年制のビジネススクールが一般的な中で、円安の影響により学費や生活費などの負担を下げるという意味合いもあるのかもしれない。
キャリアを模索、留学勉強を開始

私が強く海外留学を意識するようになったのは、新卒入社の商社において、取引先の担当者が、企業内選抜で派遣の“権利”を勝ち取り、TOEFL(トフル)やGMAT(ジーマット)の勉強を始めたことによる。
これらの試験の存在は大学時代から知っており、ゆくゆくは海外留学をしたい、と漠然と感じてはいた。
制度の存在を確認して入社したものの、じきにバブル経済は崩壊。同社の企業派遣はいつの間にか中断・消滅状態となっていた。ちょうど現業にも慣れ、海外駐在員の内示を待つか、それとも別の“道”を模索すべきか、自身の将来のキャリアを考えだした頃である。
上記の取引先企業の担当者へも相談し、本格的に海外留学を目指すかどうかを考え始めた。
海外留学のための試験勉強は独学(座学)でするものではなく、当時は、TOEFLやGMATの目標スコアを達成するために、MBA留学専門予備校に通うのが一般的であった。例えば、PBT(Paper-Based Testing=紙ベースの試験)において、日本人が目標とするスコアは、TOEEFL630点、GMAT650点程度と記憶している。
実は、TOEFLとTOEICの点数には相関関係があり、同じ製作元であるETSによって換算式が公開されている。CBT導入や問題内容が変化し、難易度が当時と違っているのかもしれないが、TOEFL(PBT)での630点は、当時、TOEIC(PBT)の970点前後に相当し、TOEIC満点に近い上位数%との位置づけとなっていた。
私の場合、大学で英語を専攻していたこともあり、TOEFLで600点や630点の“壁”を超えるのはさほど難しくなかった。筆記試験であるTWEも、ほぼ満点近いスコアを叩き出していた。苦労したのは、GMATである。
海外留学向けの有名な専門予備校は当時いくつか存在し、高い学費を自腹で負担(企業派遣は会社負担)。数えたわけではないが、全体の2~5割くらいが私費による志望者だった印象だ。
予備校へ通うことで、情報交換などもしていた。いずれにせよ、私費志望者もそれなりの比率がおり、そのくらい、MBA留学は一種の“ブーム”であった。
経験踏まえ、出願先を選ぶ

※JBCCの特別協賛として経営共創基盤(IGPI)やプラチナーパートナーとしてコーポレイトディレクションなど、コンサルティングファームが参加
出所:JBCC https://www.jbccex.com/about
ビジネススクールの特色は授業の仕方で二分される。講義形式、またはケースメソッドだ。
後者は、マサチューセッツ州ボストンにあるトップスクールやバージニア州の1校が有名。私が進学したカナダのビジネススクールは、世界で第2位のケース制作数を誇り、北米ビジネススクール間で開催されていたケース・コンペティション(チームで分析を行い発表、提言を競う大会)では、米国のトップスクールともわたり合い、たびたび優勝していた。
近年日本においても、この回想録でも登場した、TMA-J(ターンアラウンド・マネジメント協会日本支部)が発起人となり、NPO法人JBCC(日本ビジネススクール・ケース・コンペティション)が開催され、国内経営大学院間で“しのぎ”を削っている。
コロナ禍により、開催は一時中断されていたが、2023年実績では25校以上が参加する大きな“競技”となっている。
当時、私はすでに会計事務所系コンサルティングファームにも属しており、今更講義でもないと思い、出願はケース・スクールまたは、コンサルティングファーム就職に強いとされたGeneral Management(戦略を含む総合経営学)に強いスクールを選択した。
GMATは独特の試験

ご存じの方も多いと思うが、TOEFLは「外国語としての英語試験」(Test Of English as a Foreign Language)、GMATは「経営大学院入学試験」(Graduate Management Admission Test)の略である。
日本で、より有名なTOEICと同様、米国のNPO団体、ETS(イーティーエス、Educational Testing Service)やGMAC(ジーマック)などが試験問題の作成や試験の運営を実施している。
一般の大学院、法科大学院、医学大学院入学には、各々、GRE(ジーアールイー)、LSAT(エルサット)やMCAT(エムキャット)という試験を受験する必要がある。
欧米経営大学院への入学を望む非英語圏の受験者(英語圏の海外大学卒業者を除く)は、基本的にTOEFLを受験し、英語力に問題がないことを証明するため、上位5%以上に属する高得点を取らなければならない。
日本と異なっているのは、専門的な経営学や法学は、学部レベル(Undergraduate)では学問提供がなく、専門職大学院(Professional School)と呼ばれる大学院(Graduate School)での授業となることだ。
試験自体の難易度はTOEICに比べると高いと思われる。TOEICは、口語や仕事上での英語の運用能力(国際コミュニケーション力)を見る試験であるが、TOEFLはより、学術的な内容に特化しており、長文読解問題で出題される単語も、難解(日常生活ではあまり目にしない)であり、地震学、天文・気象学、考古学、人類学などに関するテーマが多く出題されていた記憶がある。
文系・理系の出身かどうかで得点に偏りが出ないよう、専門的な学問からテーマが選ばれることを何かで読んだことがある。
GMATはどちらかというと、私の感覚では知能試験に近い印象だ。運営母体によると、適性試験(Apptitude Test)の一種であり、その特性から一度の受験でよく、何回受けても点数は変わらない、というのが趣旨のようである。ただ、日本人は高得点を叩き出すために、何度も受験するのが一般的であった。
Verbal(言語領域)とQuantitative(数理領域)に大きく分かれ、長文読解(RC:Reading Comprehension)の他に、文法自体に間違いはないが、言い回しまたはビジネス文書として、あるいは論理的に最も適切な文章を選ぶもの(SC:Sentence Correction)、論理構成を問うもの(CR:Critical Reasoning)、日本で言う算数や初歩数学に近い計算問題(PS:Problem Solving)、十分条件・必要条件を問うもの(DS:Data Sufficiency)、さらには筆記試験(AWA:Analytical Writing Assessment)。
英語(欧米人にとっては国語)の問題のみではなく、論理思考力・数値計算力を問うものが中心となる。
日本人にとって、算術用語やパターンを覚えてしまえば解きやすいPS、SC、DSは得点しやすく、RCは速読力と、ある意味“慣れ”である。一番苦労したのは、CRだ。問題文を読み、論理構成を強める、または弱める条件(文章)、結論として推論できる内容を選ぶなど。
ただ、現在では、GMAT対策もネットで安く訓練ができると想定される。コンサルティングと同様、“情報価値”はかなり低下しているのだ。
出願に必要なものは、試験以外にも

Application(出願)には試験の他にも、基本的には、①社会人(企業勤務)経験、②上司や大学教授などからの推薦状を数通、③小論文、④学部のGPA(Grade Point Average、単位数で荷重平均された5段階の成績ポイント)、⑤インタビューが課されること、と点数一辺倒の日本の試験とはかなり異なっていた。
特に、小論文はエッセイ(Essay)とも呼ばれ、各大学院により、5問程度が課される。内容は何故志望するかといった単純なものではなく、100~300字程度の字数制限がある中で、人物としての入学の適性や個人の強み、クラス(学級)への貢献(Contribution)などを示す内容を、簡潔にまとめなければならない。
入学審査官(Admissions Officer)は、一人当りの候補者に対し、1つのエッセイの最初の数行しか読まない、とも言われていた。“これまでの仕事上での苦難に対して、どう対処したか”や、リーダーシップ力を示した事例、“社会的な理念に反した業務に直面した場合どうするか”といった問題解決、日常でのボランティア活動やコミュニティ活動等、社会的貢献を問うもの、など、経営者に必要となるであろう人格やコミュニケーション力、素養を問うものが多かった。
こうしたエッセイに対する添削サービスも留学予備校には存在した。添削料が非常に高かったことは覚えている。
今では、出願もネットで一発出願、出願料もカード決済やデジタルマネーではなかろうか。当時は、DHLやFedExで現物を出願締め切りまでに確実に到着するようビジネス便を使い、さらに、出願料は小切手を振り出し同梱するなど、出願手続も複雑であった。
大変だった過去問対策
日本での大学入試もそうだが、通常、大学の過去問対策を行う。大変だったのは、過去問が“アナログ”時代では入手しにくかったこと。上記のGMAC発行の公式問題集はペーパーバックで存在したが、問題数がさほど多くなく、実際の問題と比べると、難度は低くなっていた。
そのため、専門予備校に通い、費用を出し過去問を入手する(講義を受ける)のが常であった。
さらに大変だったのは、それまで、PBT(試験問題紙配布・マークシート回答)であった形式が、私が留学する直前の1997年頃から、CBT(Computer-Based~、デスクトップPCでのウェブ受験)へ変更されたことだ。
当時、真偽のほどは確かではないが、前半1/3くらいの問題数において、受験者回答結果を元に能力を判別。正答率に応じ中盤以降に出題問題のレベルが変わり、後半でいくら正答を出しても高得点にはつながらない、という噂が蔓延するようになった。
加えて、私の場合、最悪だったのは、CBTを受け、途中でPCがフリーズし、その受験回の得点は無効となってしまったことだ。得点はどうだったのか、知るよしもない。
結局、実際に留学するまでには、費用もそうだが、数年以上の期間もかけたことになる。若いからこそ出来たことだと、つくづく思う。
コンサルティングファームへ転職してからも、留学の勉強は続けた。抱えている案件の執行と受験勉強。“二足のわらじ”は難を極めた。それでも、予備校受講料、出願費、合格後の授業料を稼ぎ出すために残業もした(当時、ジュニア・ミドルクラスの場合、残業代もついたのだ)。
挙句の果てには、特に外資系コンサルティングファームで催される“アウティング”(遠足のような、宿泊ありの社員旅行)で海外渡航した際も、ビーチで休みながらGMATの問題集を解いていた。横にいたパートナー(マネージング・ディレクター)からは、「頑張るねー」と言われてしまった。
(特別編・下に続く)
続きはこちら
【回想録】 内側から見た経営コンサルティング(MC)の歴史 (特別編・下) ~異なる文化での経験が現在の糧に















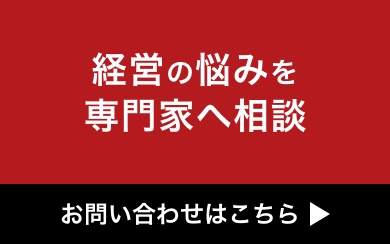
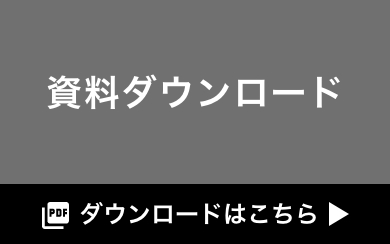



コメントが送信されました。