読了目安:21分
哲学とビジネス⑦ビジネスにも活用できるルネ・デカルトの「方法序説」
ルネ・デカルトは、17世紀のヨーロッパで活躍した哲学者であるとともに、数学、医学、天文学等の分野で方法論的な探求を重ねて活躍した。全てのものを徹底的に疑った後に生まれた「我思う、故に我あり」の言葉は有名だ。デカルトの『方法序説』(1637年刊行)は、この考え方のみならず、物事の本質的な考え方の方法論を示すもので、現在のビジネスにおいても役に立つことから皆様にご紹介したい。
はじめに
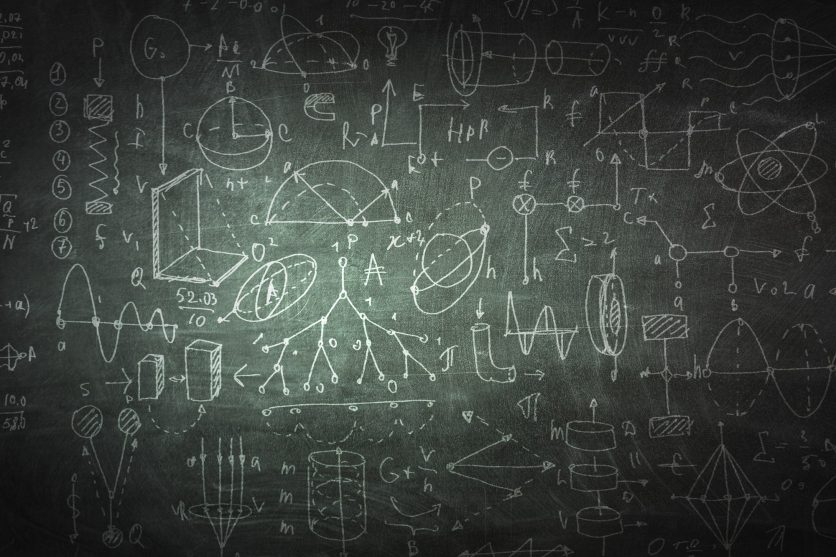
古代ギリシャ時代のギリシャ哲学(ソクラテス、プラトン、アリストテレス等)以降、中世(10世紀~16世紀)において、スコラ哲学が隆盛を誇った。
「スコラ」とは、ギリシャ語で学校を意味することからも明らかな通り、スコラ哲学は、アリストテレスを中心としたギリシャ哲学をベースに、神学を含めた内容を教育するものであり、新たな哲学を構築するものではなかった。(図表1参照)

近世になると、二つの異なる哲学流派が台頭する。本来人間の精神は生まれたときには白紙状態であったが、知識はすべてその後の経験から得られ、その経験の積み重ねで真理に近づこうとするイギリス経験論と、人間の理性(良識)は元々天性に備わっているため、絶対的真理から全ての法則を導こうとする大陸合理論である。
デカルトは、この大陸合理論を展開した最初の哲学者であり、哲学の歴史において大きな転換点をもたらした。
デカルトの生い立ち

デカルトは、1596年にフランスのトゥレーヌ州の医師の家系に生まれた。幼いころから病弱であったこともあり、1607年に入学したラ・フレーシュ学院では勉学に励む生活を送っていたが、同学院で教えられていた古代ギリシャのスコラ哲学に疑念を抱いた。
1614年(18歳)にはポワティエ大学で法学と医学を学ぶも、これまで学んだすべてのものを捨てて世の中の経験を積むべく、1618年(22歳)にオランダで志願兵として軍隊に入隊し、その翌年には、三十年戦争に参加すべくドイツに渡った。
軍隊を除隊した後は、約2年かけローマやパリに滞在し、1628年(32歳)からは、オランダに定住し、自らの使命として哲学に没頭した。
数学者でもあったデカルトは、哲学を数学のような厳密な学問へとアップグレードする意欲を持っていたため、絶対確実な第一原理を発見し、そこから演繹的にあらゆる学問の木の枝葉を打ち立てることを企図した。
演繹法とは、すでに知られている法則(一般論・ルール)や前提から、階段を登っていくように論理を積み重ねて結論を出す考え方である。デカルトは、自らが見つけた真理から、全ての学問の内容を導き出そうと考えた。
「方法序説」とは

1637年に出版されたデカルトの『方法序説』は、正確には「理性を正しく導き、学問において真理を探究するための方法序説」といい、『屈折光学』、『気象学』、『幾何学』の科学書三部作の序文として書かれた。
この書籍の冒頭に書かれている「良識はこの世で最も公平に分け与えられているものである。」は有名な言葉だ。
前述した通り、全ての人間は公平に良識(真偽を区別する能力)を持って生まれてきているため、人間間の意見の違いは良識によって違いが出るわけではない。意見の違いは、人間の思考の道筋(思考方法)の違いによってもたらされる、ということを述べている。以下、この『方法序説』から学ぶべき三つの考え方を述べる。
「方法序説」の教え①(既存概念の除去思考)

デカルトは、まず「自分がそれまで信じてきた諸見解全てに対して、自分の信念から一度きっぱりと取り除いてみること」を述べている。
その根拠となる例として、
ア 沢山の部材を寄せ集めて作り、いろいろな親方の手を通ってきた作品は、多くの場合、一人だけで苦労して仕上げた作品ほどの完成度が見られないこと
イ 多数の建築家が、別の目的で建てられた建築物を修復しながら仕上げた建物よりも、一人の建築家が請け負って作り上げた建物の方が壮麗で整然としていること
ウ 城壁のある村落が、その後の発達によって大都市になったとしても、一人の技師が思い通りに線引きした規則正しい城壁都市に比べると不揃いであること
を掲げている。
一方で、「町を美しく見せる目的だけのために、町の家屋を全部撤去すること」は、合理性がなく現実には起こりえないし、「学問の全体系や、教育のために学校で確立している秩序を改変すること」も理に反している。
これに対し、「立て直しのための家の取り壊し」や「倒壊の恐れや、土台がしっかりしていないときに家を取り壊すこと」については、いずれも合理的である。
それと同様に、「自分がそれまで信じてきた諸見解全てに対して、自分の信念から一度きっぱりと取り除いてみること」は合理的である。古い基礎の上だけに建設し、若い頃に信じ込まされた諸原理について、それが真かどうかを吟味することなく依拠するよりも、自分の中で、一旦、基礎も含めて取り除いてみて新たに考える方法が正しい、とデカルトは述べている。
我々がビジネスを行う場合にも、このような考え方が役に立つ場面は少なくない。会社の組織形態に少しずつ変更や追加を加えた結果、結果的に大変複雑な組織図になってしまい、機能別組織体制と事業部別組織体制というような、原点となるべきコンセプトが良く分からなくなってしまう場合がある。
このようなときには、一度、原点から、あるべき組織体制を一から構築することを念頭にシミュレーションしてみると、結果として、よりよい組織体制が見えてくる場合もある。
また、事業戦略についても同様の現象がある。小売業の例をとってみれば、総合スーパーで事業を行っていたが、各カテゴリー(家電、アパレル、ホームセンター、ドラッグストア他)の専門チェーンが台頭した後は、食品以外のカテゴリーにおいて競争力を失ったため、カテゴリーごとに赤字のスペースを外部の専門テナントに賃貸して埋めていくケースが散見された。
しかし、全体としてみると総合スーパーの延長線上の建物になってしまい、結果として、顧客にとっては魅力に乏しい店舗になってしまった企業も少なくなかった。
これに対し、新しく外部の競争力のあるテナントを中心としたモールを一から構築した戦略を採用し、不動産事業的な発想で運営することに切り替え、成功している小売企業も多い。自前の店舗を中心とした発想を捨てて商業不動産賃貸業に徹する考え方は、まさに、ゼロベースで戦略を見直しすることで成功した一例といえる。
事業戦略、事業ポートフォリオ、組織体制等、長年の企業経営の歴史的経過の中で微修正を繰り返した企業において、もし抜本的な経営改革が必要な局面にある場合には、このデカルトの考え方を念頭に、戦略等をゼロベースで再構築してみることをお勧めする。
もちろん、再構築を行った場合に、それがすぐに実現できるかという点は別問題である。しかし、事業の検討にあたっては、このような方法で、一度ゼロベースで思考してみることはとても有用と思われる。
「方法序説」の教え②(複雑な課題の解決のための思考方法)

デカルトは、「方法序説」において、複雑な課題を解決するための思考方法として、次のような四つのルールを示している。
-
1 「明証」のルール
-
自分が、明証的に真であると認めるもの以外は、真として受け入れないこと。注意深く即断と偏見を避け、疑いをさしはさむ余地が全くないほど明晰かつ判明に精神に現れるもの以外は、判断の中に含めないこと。
-
2 「分析」のルール
-
検討する難問の一つ一つをできるだけ多くの、しかも問題をよりよく解くために必要なだけの小部分に分割すること。
-
3 「総合」のルール
-
思考を順序に従って導くこと。即ち、もっとも単純でもっとも認識しやすいものから初めて、少しずつ階段を上るようにして、もっとも複雑なものの認識まで昇っていくこと。
-
4 「枚挙と全体の点検」のルール
-
最後に、完全な枚挙と全体にわたる見直しをして、なにも見落とさなかったと確信すること。
これらは、哲学書の内容にも関わらず、誰にとっても分かりやすい内容であり、我々がビジネスをするにあたっても、重要な示唆が含まれている。
「明証」のルール
まず、1の「明証」のルールは、デカルトの「我思う故に我あり」の言葉と同様の考え方だ。「我思う故に我あり」は、ほんの少しでも疑われるものは全部誤りとして廃棄し、その後に自分の信念の中に疑いがないと思うもののみを残した結果、「全てを偽と疑っている自分の存在」だけが最後に残った、といったことを表した言葉だ。
この思考プロセスは、「方法的懐疑」ともいわれており、あらゆることを極限まで疑ってそれでも疑うことのできないものが残ったならば、それが真理であるという思考法だ。しかし、「無罪推定原則」等がある刑事司法の世界ならともかく、ビジネスの世界で、このような極限までの明証性を求めるプロセスは現実的でない。
一方で、ビジネスの世界でも示唆があることは、「方法的懐疑」が正しいとする根拠の一つとしてデカルトが掲げている、「感覚は、我々を欺くことがあるので、疑われなければならない」という点だ。
ビジネスの世界で、正しいと思う根拠が明確でないにも関わらず、過去の経験又は先入観等から、感覚的に「正しい」又は「間違っている」と判断するケースは少なくない。これは、いわゆる「認知バイアス」の文脈で語られる多様な事象にも通じる内容であり、判断する人間(自分または他人)の「感覚」については、常に疑いを持ちつつビジネスを行うことが必要である。
「分析」のルール
2の「分析」のルールは、複雑な課題を、性質上の違い、前後関係や因果関係等から因数分解し、一つ一つについて検討を行う方法であり、実際のビジネスにおいてもよく用いられている。
例えば、企業がM&Aを行うかどうかの判断をする際に、通常、各種の企業調査(デューディリジェンス=DD)(事業DD、財務DD、法務DD等)が行われる。
その事業DDにおいても、各種事業・グループ会社別の検討がなされ、また、それぞれの事業毎に、売上高、変動費、固定費等に分けて課題を抽出する。これ自体は、課題を分解して一つ一つを検討する手法であり正しい考え方だ。
一方で、このようなM&Aを行わない場合には、自社の事業についてこのような分析的な手法での課題抽出、検討をすることはあまりない。しかし、外部のコンサルファーム等に依頼するかどうかは別として、デカルトが言うように、自社の組織や事業の課題抽出のために、自社の企業調査(特に事業DD)を実施してみることは有用である。
前述した「方法序説」の教え①(既存概念の除去思考)にも触れた通り、自社の今後の事業戦略を構築するにあたって、これまでの経営戦略を一度ゼロクリアした上で(思考プロセスとして)、客観的な視点から、自社の企業課題・事業課題を自社DDによって検証してみることは、今後の新たな企業戦略を構築する際に有効なのでお勧めする。
「総合」のルール
3の「総合」のルールも、課題を総合した上で解決する手法として、ビジネスの世界でも十分に妥当している考え方だ。2の「分析」のルールで因数分解した各種課題においては、簡単に答えを出すことができる経営課題から、簡単に答えを出すことができない経営課題まで存在するが、それらを順不同に検討していくことは得策ではない。
本ルールで述べている通り、最も単純で最も解決しやすい経営課題の解決策を順次固めていった上で、最後に残った若干難解な経営課題を最後に解決するという考え方は、大変示唆に富んでいる。
例えば、主要な事業が属する市場の縮小により、業績が下降傾向にある企業においては、新たな事業の柱を構築することを検討する場合が少なくない。その際、新事業を自社で立ち上げて進めていくのか、それともM&Aで他社を買収することによって行うかの検討を最初から実施しても適切な回答は出ない。
まず、縮小市場に属する事業を営んでいたとしても、今後の市場縮小レベルの予測や、既存の自社事業の改善策、特徴(差別化要因)を検討した上で、既存事業の業績に関する合理的な事業予測を行う(又は事業計画を策定する)ことを検討しなければならない。
これ自体は、勝手知っている既存事業に関する検討であるため、各企業が行うことは容易と言うことができる。
その上で、新たに柱とする新事業の内容の検討を行うことになる。通常は、得意な技術を生かした他の製品やサービスの展開から始める。
しかし、再生可能エネルギー事業等、得意な領域ではないが、市場が大きく成長すると見込まれ、社会課題解決に資するような事業の展開も選択肢となる。これについては容易な検討ではないが、専門家等のアドバイスも受けることにより十分に可能である。
最後に、当該新事業を自社で展開するか、M&Aで他社を買収するかの検討をするが、そもそもM&Aの対象となる他社が存在するかどうかを確かめる必要がある。
また、M&Aを行うにあたっては、自社で実行できる資金調達で買収可能な企業規模がどの程度かの検討も必要である。自社だけの情報や知識だけでの検討には限界があることから、M&Aや財務の専門アドバイザーの助力が必要である。この手順や相関関係の概略を示したのが下記の図表2であり、イメージを掴んでいただきたい。

このルールに従った課題検討のプロセスは、通常の企業で無意識に行われている場合も少なくない。しかし、迷った際には、是非このデカルトの「総合」のルールを思い出していただきたい。解決しやすい経営課題から難解な経営課題への手順を確認することで、解決のヒントが得られる場合もあるだろう。
「枚挙と全体の点検」のルール
最後に、4の「枚挙と全体の点検」のルールである。この「枚挙」という言葉は、一つ一つ数え上げるという意であり、前述した「総合」のルールで課題の解決策を検討した後に、改めて、漏れがないか一つ一つを検証してみるという意である。
企業においては、因数分解した経営課題を解決の容易性の観点から列挙した上で、最終的な解決策としての事業戦略を策定する。その課題の検討過程において、課題抽出や検討に漏れや誤りがないかを検証してみることは重要である。
「全体の点検」においては、全体感として整合性が取れているかの検証が含まれる。企業の場合、一定の検討の結果として出した経営戦略について全体的に検討するにあたっては、当該企業の経営理念やミッションとの整合性があるかの検証が必要である。
また、その戦略の内容が全体的にみて社員や取引先等のステークホルダーにとって分かりやすい内容になっているかの検証も必要である。
論点の積み上げによって出した検討結果としての経営戦略は、時として、経営理念やミッションに必ずしもフィットしない内容となっていたり、働いている社員にとって難解で分かりにくいものになっていたりするケースも少なくない。
4の「枚挙と全体の点検」のルールでの全体的な検証は、大変重要であるため、意識して行う必要がある。
「方法序説」の教え③(ビジネスを行う際の心構え)

デカルトは、自分が、堅固な哲学を築き上げるまでの暫定的な生き方の指針として、三つの「仮の道徳ルール」を定めて、その後の生き方の指針としたが、その内容は、次の通りであった。
-
1 自分の国の法律と慣習に従うこと
-
自分の国の法律と慣習は、良識ある人の意見や穏健な意見が反映され、実際に多くの人々が実生活において受け入れているルールである。現時点で最善と考えられるルールであるので、それに従って行動することが合理的と考えられる。
-
2 自分が一度決めた以上は、その決断が仮に疑わしいものであったとしても、それに一貫して従うこと
-
例えば、森の中で道に迷った旅人は、決して途中で引き返してはいけない。なぜなら、正しい道ではなかったとしても、必ずどこかへは行きつくだろうし、今いる場所で佇んでいるよりは合理的な判断と思われるからだ。
-
これと同様に、自分が一度決めた方針については、仮にその後の状況の中で当該方針について疑念を抱いたとしても、途中で安易に変更するのは得策ではない。間違った方針であることが明確になった場合に軌道修正をする場合は別として、途中で方針変更をしたことにより結果が出なかった場合に、何が問題であったかの検証が事後的に困難になるからだ。
-
3 運命に従うより自分に打ち克て。世界の秩序よりも自分の欲望を変えよ
-
自分の力の範囲外である世界のことは、自分が、それをコントロールすることは困難であり、これに執着するよりも、自分の考え方を変更して対応すべきという考え方である。
このうちビジネスにおいて参考になる考え方は、2と3である。企業経営において、経営者が新規事業を行う意思決定をした後、数年たっても結果が出ない場合に、当該新規事業の方針を変更するのか、それとも断念すべきかの判断を迫られるケースがある。
この際に大事なことは、新規事業における赤字垂れ流しによって、会社の経営自体が存続できなくなるような場合は別として、そうでない場合には、あまりに早期に新規事業の方針等に変更や撤退判断を行うことは得策ではない、ということだ
そのように早期で判断を行う場合、新規事業の戦略自体が間違えであったのか、新規事業浸透するまでの期間が予想よりも長かったのか、戦略等は正しいものの実行を担う経営人材に問題があったのか、等の課題検証ができないからである。
無期限に新規事業を行うべきではないが、一定の時間軸(イメージ的には5年以上のスパーン)をもって新規事業に取り組むべきである。新規事業において、十分な時間の業務実績がなければ、様々な課題を検証できず、新規事業に取り組んだプロセス自体が企業にとっての経験値にならないからである。
また、3の「道徳ルール」は重要だ。全ての企業経営は、世界や国の経済環境によって左右されることになるが、当該環境変化を企業が防ぐことはできない。このような変化に対しては、企業がそれを所与のものとして、自社のビジネスモデルの変革等を検討することが重要となる。
また、カーボンニュートラルの浸透する世界のように、将来の環境変化が予想できるような場合には、それに備えた自社のビジネスモデルの変革等を進めておくことも、当該ルールに沿った考え方だ。
最後に
ルネ・デカルトは、近世において活躍した大陸合理論の代表的な哲学者であるが、「我思う故に我あり」という著名な言葉以外にも、我々がビジネスを遂行する際に参考となる有益な考え方が存在し、本稿はその一部をご紹介した。
哲学者は、現代のビジネスを想定した上で、それにも通じる内容で学説を展開しているわけではないが、ビジネスを行う我々が、哲学者の有益な考え方の一部を選択して、自らのビジネスに生かすことは正しい思考方法だと思う。
哲学者にとっては、哲学こそが全ての学問の前提となる第一原則であり、これはビジネスにおいても同様のはずだ。学問としての難解な哲学において正しさや網羅性を追求するのではなく、皆が理解できる範囲で分かりやすい哲学を学び、これを実生活に生かしていくことも、哲学者が想定していたことではないかと個人的には考えている。
参考文献
-
方法序説 (デカルト著/谷川多佳子訳:岩波文庫)
-
デカルト入門講義 (冨田恭彦著:ちくま学芸文庫)





















コメントが送信されました。