読了目安:10分
「安すぎる日本」で国民は苦しむか? 最低賃金引上げの合理性を問う
最低賃金引上げが叫ばれている。日本の賃金は国際的に見て安いらしい。一般消費財でも、スターバックスコーヒーやマクドナルドなどグローバルブランドの商品が日本では先進国中で最低価格となっており、「安すぎる日本」として話題になっている。最低賃金引き上げは、本当に筋のよい政策なのだろうか。
相次ぐ「安すぎる日本」への批判

どうやら我々は「安すぎる日本」に住んでいるようだ。最近も、『週刊ダイヤモンド』2021年8月28日号で、『安すぎ日本 沈む給料 買われる企業』という特集が組まれた。同誌によれば、日本の平均賃金はOECD加盟国35カ国中22位であり、1位の米国の56%の水準に留まっている。
一般消費財も日本は安い(らしい)。マクドナルドのビッグマックの値段は、ニューヨーク776円、ロンドン531円に対し、日本では390円。スターバックスコーヒーのラテ(トールサイズ)も、ニューヨーク542円、ロンドン571円に対し、日本は380円だ。
前述の週刊ダイヤモンドの特集では、多くの識者も「安すぎる日本」を批判している。「アフリカ化」する日本。才能ある人は棄国する。最低賃金を引き上げないから、生産性が上がらない。商品の値上げをして賃上げすべきだ。「日本はギリシア化」する、等々。
生活満足度が上昇する「安すぎる日本」
「安すぎる日本」批判は筋が通っているように見える。
しかし、内閣府が行う世論調査によると平成の30年間で「現在の生活に関する満足度」は一貫して上昇トレンドにあり、我々は「安すぎる日本」と呼ばれる状況を積極的に受け入れ、満足度を上げている。
「円ドル」レート次第で「安すぎる日本」は霧消する
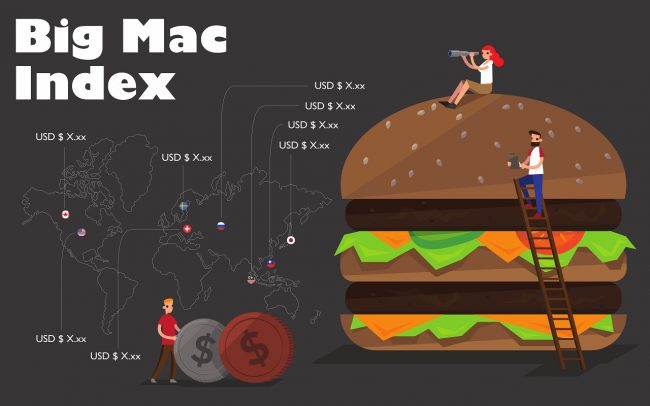
清潔な環境、治安の良さ、“安くて”美味しい食べ物。一般的な日本人が棄国する理由は見当たらない。不衛生で、治安が悪く、食べ物の値段が高い国で、(時として日本人として差別されながら)生活したい人は多くなかろう。「安すぎる日本」議論は極めて奇異だ。
冒頭に日本の平均賃金は米国の56%と記した。ビッグマックの値段は米国の50%、スタバのラテの値段は同70%だ。日本では名目賃金が低くても、ビッグマックやラテを買うのに困らない。名目賃金自体が低いことは生活者としては大きな問題とは言えない。
日本の賃金が低く見えるのは、アベノミクス以降の円安による部分が大きいのではなかろうか。現在は1ドル=110円という水準だ。これが1ドル=80円となれば、日本の名目賃金も、ビッグマックやラテの価格もドルベースで37.5%ほど上昇することとなる。
円ドルレート次第で、「安すぎる日本」は瞬時に霧消する。「安すぎる日本」なるものは、実態がないのだ。本来は円ドルレートの問題にもかかわらず、日本の経済構造自体が問題を抱えているような言説には既視感がある。1989~1990年に行われた日米構造協議だ。当時の日本は、名目的な賃金やモノの値段が“高い”と断罪され、構造改革を迫られた。今はその逆だ。「安すぎる日本」が問題らしい。
最低賃金の引き上げは、企業の設備投資を誘発しない

「安すぎる日本」の象徴として、最低賃金の引き上げに焦点が当たっている。推進派の論理はシンプルだ。最低賃金の引き上げは、企業の設備投資行動に影響を与える。企業の生産性を引き上げることで、マクロ経済全体を成長させる、という論理だ。
我々個々人が提供する“労働”も、経済学の時空では商品の一つだ。コメに代表されるように、商品の価格規制が、社会全体の厚生を引き上げるという話は寡聞にして聞かない。労働以外の経営資源の価格が不変で、労働の価格だけが政策的に上昇すれば(=最低賃金の引き上げがなされれば)、各企業は労働投入量を減らし、生産量は減少する。
地方の企業、高齢労働者はかえって苦しむ
最低賃金の引き上げに耐えられない企業は退出を余儀なくされる。生き残った企業は、生産性の引き上げのために、設備投資を行うのだろうか。長年のゼロ金利でも投資しなかった経営者たちが、最低賃金が引き上げられたからといって設備投資を行うのかどうかは定かではない。他国の最低賃金引き上げの成功事例を強調する識者もいるが、我々が生きている今の日本はゼロ金利がずっと続いている時空なのだ。
コンビニのオーナー、地方のサービス企業などは、最低賃金の引き上げで大きな打撃を受けるだろう。失業者が職業訓練を受けて他の産業に移動するというのは机上では分かるが、地方の中高年労働者にとっては非現実的なシミュレーションだ。日本がこの種のハードランディングを、政治的に受け止められるかどうかは疑問だ。
労働生産性は生産性指標の一つに過ぎない
我々が無自覚に使っている「生産性」という言葉は、多様な生産性指標のうちの一つである「労働生産性」の場合が多い。これは各企業、各産業、各国家が生み出す付加価値を労働投入量で除した値である。生産性には、設備生産性、エネルギー生産性など、様々なバリュエーションがある。労働生産性はその一つに過ぎない。
労働生産性は、多くの労働投入を行う国では低くなる。労働投入を少なくする国では、労働生産性は高くなる。それだけだ。労働生産性と国民の幸福度にリニアな連関性はない。
労働生産性の高低は、企業や国が置かれた環境における労働と非労働(設備や土地)という異なる経営資源の価格差によって決定される。価格差は外生的に決定される。例えば、日本の繁華街を代表する銀座と地方都市での経営資源の価格差を考えてみよう。
銀座では労働という経営資源が割安になる

坪当たり家賃を銀座は50,000円/月、地方は5,000円/月とすると、銀座の家賃は地方の10倍だ。一方、飲食店で働く人の時給を銀座は2,000円、地方は1,000円とすると、銀座の人件費は地方の2倍に過ぎない。銀座では、地方との相対価格という観点から、家賃(地方の10倍)に比べて人件費(同2倍)が割安だ。
銀座で事業を行う経営者の合理的判断は、割高な経営資源である設備の使用を最小化することであり、割安な経営資源である労働の投入量を極大化することだ。結果として、銀座における労働生産性はそれほど高くないが、設備生産性は高くなり、経営者は必要十分な収益を獲得する機会を得る。
このアナロジーは、人口密度の低い国(米国や北欧など)と日本全体での比較でも同じだ。人口密度の低い国々に比べて、人口密度の高い国日本では、銀座と同様の状態となる。このため、日本の経営者は合理的経営判断として、労働投入量を多くしてきた。
元々低かった日本の労働生産性

日本生産性本部の「労働生産性の国際比較2020」によると、2019年の日本の労働生産性は世界26位と芳しくない。しかし、日本が高いGDP成長を続けていた1970年の日本の順位は20位、1980年は20位とさほど今と変わらない。
日本の労働生産性が世界で上位に継続的にランクインした事実はない。それでも日本はかつて高成長していたし、バブルが発生するほどマクロ経済が良い時代があった。日本の労働生産性が低いのは、日本全体が銀座のように労働を大量投入することが合理的だったからだ。これは、日本の経営者の合理的な選択の結果なのだ。
歴史的に日本では地方から都市部が人口を吸収し、それを産業界が活用することでマクロ経済成長を実現させてきた。家賃など設備費の高い都市部において、地方からの低廉な労働力の供給こそが経済を押し上げてきた。都市部と地方はこの文脈でエコシステムを形成する共生関係なのだ。
増田悦佐氏が『高度経済成長は復活できる (文春新書)』など複数の著書で指摘しているように、東京の人口増減と日本のマクロ経済成長率上下は連関性がある。東京の人口増加率が高い時、マクロ経済成長率も上昇する。最低賃金の引き上げを行い、労働の価格を人為的にいじる事で、日本経済のエコシステムに害を与える可能性はないのだろうか。
銀座と比べた相対価格で見ると、地方はもともと人件費が高く、家賃が安い。地方で最低賃金の引き上げを行えば、地方企業における雇用は更に縮小する。都市部への人口集中が更に進む可能性があるので、それが日本全体のマクロ経済を引き上げるというシナリオも一応あるにはあるのだが、地方の人々が望む未来とは異なる絵姿になろう。
悲観シナリオ:失業率上昇、ヤミ労働、フリーランスの抑圧
最低賃金の引き上げで雇用が縮小する国で生じうるネガティブな現象は3つありうる。
①失業率の上昇・高止まり
②ヤミ労働の横行
③フリーランスや自営業者という最低賃金の適用から外れる格好での低賃金労働(②の一種)の増加である。
移民が多い国では①や②が増加するだろう。世界的に見て自営業者の比率が低水準にある日本では、③の現象が起こると筆者は予想する。(『国による「中小企業いじめ」の社会的リスク』2021年6月11日を参照)
人為的賃金引き上げは産業界の活力を奪う
人為的な賃金の引き上げは、失業率、ヤミ労働、フリーランスの抑圧といった社会問題だけでなく、産業界の活力低下のリスクもある。その是非、あるいは実行のスピードなど、慎重な議論が求められる。






















コメントが送信されました。