読了目安:16分
哲学とビジネス⑨カントの哲学 (哲学者カントの「コペルニクス的転回」をビジネスに生かせ)
イマヌエル・カントは、近代哲学の祖と言われ、近代哲学において重要な役割を果たした著名なドイツの哲学者であり、人間の認識の構造において、「コペルニクス的転回」と呼ばれる画期的な考え方を提唱したことで知られている。本稿では、カントの哲学を紹介するとともに、ビジネスの世界でカントの哲学の活用方法についての私見を述べる。
はじめに

イマヌエル・カント(1724年~1804年)は、1724年にプロイセン王国のケーニヒスベルクに出生した。幼少期から聡明な少年であり、1740年にはケーニヒスベルク大学に進学し、哲学、数学、自然科学を学んだ。
カントは、生家が経済的に恵まれていなかったことから、学業を継続するために家庭教師をして生計を立てて暮らしていた。31歳となった1755年には、「自然界の一般的な自然史と理論」の論文により修士学位を取得した。
その後にケーニヒスベルク大学で講師の職に就いたが、同大学で論理学・形而上学の正教授に任命されたのは、1770年3月。カントが46歳の時だった。カントは、その後に哲学者としての功績を本格的に積んでいったことから、遅咲きの哲学者とも言われていた。
カントの著作として有名な、「純粋理性批判」、「実践理性批判」、「判断力批判」の三書籍(三批判書と呼ばれている)は、いずれもカントが50歳以降で記した著作だ。
カントは、これらの著作において二大哲学理論である経験論と合理論の折衷的な考え方を提示し、両理論の良い点を生かしながら矛盾を解消し、統合した。なお、二大哲学理論(経験論と合理論)は、以下のような考え方である。
1経験論(イギリス経験論)
経験論は、ロック、ヒューム等の哲学者が提唱した理論であり、人間の全ての認識は経験に基づくという考え方である。「すべての観念は経験から。生まれつきは白紙。」という言葉に示されているように、科学の知は習慣的な思考の産物であり、絶対的に正しい世界像はないという立場である。
2合理論(大陸合理論)
合理論は、デカルト、スピノザ等の哲学者が提唱した理論であり、人間は経験によらずとも、知性によって理詰めで物事を突き詰めることで、合理的に客観的世界の秩序を認識できるという立場である。
カントは、これらの両理論を踏まえた折衷的な考え方を提唱したが、具体的には以下の通りである。
人間には、生まれつき持っている先天的な知識と、経験から得られる後天的な知識の二種類の知識がある。前者は、時間や空間に関して「前後」「左右」「過去と現在」といった感覚であり、これ自体は生まれつき持っている知識と整理し、その他の知識は、後天的に経験から得られる知識と整理した。
そのうえで、「人間は、基本的な枠組みを生まれつき持っているが、その枠組みに経験をあてはめて物事を理解している」と考え、経験論と合理論を組み合わせた理論を構築した。
カントの認識・判断の構造とは(「コペルニクス的転回」)
カントは、人間の認識・判断の構造を、次の3ステップで捉えた。
第一ステップ:「感性」
「感性」とは、人間の五感によって感覚的に認識することだ。カントは、従来とは真逆の議論を展開している。カントの考え方は、
「人間が直観できる(見えている)物は、事物そのものではない。」
である。このようにいきなり言われていても分かりづらいが、私たちに見えている物は、私たちの心に主観的に思い描かれている物にすぎず、客観的な物自体を見る(認識する)ことは不可能という考え方だ。
花瓶の例(図表1参照)でみてみる。従来は、私たちは花が活けてある花瓶を見ており、他の者が見ても同じように見えている、と理解していた。
しかし、カントは、実際に存在する物は、形も色もない単なる物体であり、その物体自体を我々は客観的に認識することができない、と考えた。
我々は、五感で見ている対象について、何等の意味づけがない単なる物体として認識しているが、物体自体ではなく、あくまで見る側が主観的に認識した物体である。花が活けてある花瓶と認識するのは、次のステップ「悟性」の段階になる。

第二ステップ:「悟性」
「悟性」とは、五感によって感知した対象をさまざまな概念によって整理し、それに対する意味づけから対象物の内容を確認・判断することをさす。
「悟性」は「感性」とは対比関係にあり、自分の経験に基づいて、論理的に物事を概念的に整理したうえで判断する能力を意味する。
「悟性」には、人間が先天的に備わっている判断能力と、後天的に備わる判断能力の両面がある。前者は、物の概括的な数量の把握や物事の肯定・否定等の判断、原因と結果等の因果関係の認識や可能性や必然性等の概念の把握などをする能力だ。後者は、物の名称やカテゴリー、具体的な性質等を判断する能力だ。
人間はそれらを同時に駆使しながら物体が何であるかを理解・判断すると考えていた。ここに、カントが経験論と合理論を折衷した哲学者であると述べた要因が現れている。
先ほどの花瓶の例(図表1参照)で言うと、我々は、「感性」によって認知した物体に対し、「悟性」の力によって向日葵の花、花が活けてある花瓶という意味を理解し、対象の物体を「向日葵の花が活けてある花瓶」と判断することができるのだ。
これまでは、「認識が対象に従う」と考えられていた。特定の対象物が客観的に存在し、それを皆が同じように認識する、という意味だ。
それに対してカントは、
「対象が認識に従う」と考えた。特定の対象物が客観的に存在するが、それ自体の意味は誰も認識することができず対象物自体は、各自の経験等に基づく「悟性」によって主観的に認識するものであり、皆が同じように認識するものではない、という意味だ。
このようなカントの考え方は、従来の考えを逆さに捉えていることから、「コペルニクス的転回」と称されるに至った。
第三ステップ:「理性」
「理性」とは、「悟性」による意味づけによって認識された対象に関して、推論を行うことを意味する。人間は、「感性」によって空間・時間を伴う直観により対象を認識し、「悟性」によって対象の意味づけを理解し、「理性」によって、その理解から更なる推論を行うのだ。
具体例(磁石の例)で述べると、人間は、まず「感性」によって「磁石に鉄粉が近づいて動いている状態(二つの物体のうち、一方の物体が動いて他方に近づいていること)」を感知している。
「悟性」によってその現象が「磁石が鉄粉を引き寄せた」という意味を持つものと理解。最後は、「理性」によって、当該現象は「磁石の持つ磁力が鉄粉を引き寄せた」と推論する。
先ほどの花瓶の例(図表1参照)で考えると、カントは、①「感性」によって感知した物体を、②「悟性」によって向日葵の花が活けてある花瓶であると理解し、③「理性」によって花瓶に活けてある向日葵の切り花は1週間程度しかもたないと推論する。
ビジネス界で活用可能なカントの考え方(「コペルニクス的転回」)
ビジネスの世界では、この花瓶の例のように、単に物体を見ているという単純な図式は少なく、もっと複雑な事象が認識・判断の対象となる。ここでは、分かりやすい例として、企業(A社)が、M&Aの候補先として紹介を受けた対象企業(B社)の買収の検討事例で考えてみる。
カントの考え方によると、人間(個人)の判断は、
「感性」(五感による認識)→「悟性」(類型判断)→「理性」(推論判断)
という経過をたどる。ビジネスの世界の主体は、個人ではなく法人であることと、法人は、さまざまな個人の集合体であることが、個人の判断の場合とは異なるので、カントの判断過程を次のように読み替えて考えてみた。(図表2参照)
「感性」(企業に関連するデータ等の調査)
→「悟性」(調査結果にさまざまな分析を加えることによって出た分析判断)
→「理性」(各種分析結果に基づき、総合的に結果を導く推論判断)

1「感性」(企業に関連するデータ等の調査)
企業(法人)は、商取引を行う際の法的な権利義務を負うビークルであり、個人の集合体として組織的に活動する社会的実態だ。したがって、物体のように五感でその実態を把握することは難しい。以下に記すさまざまな情報を収集することで、対象企業の社会的実態を把握できる。
- 会社の概要(設立年、本店所在地、役員、沿革、経営理念等)
- 会社の業績データ(主として財務データ)
- 会社の業界情報、会社の技術力に関連する情報(特許等の取得、業界の技術評判等)
- 会社のガバナンス(経営者、取締役会、経営会議等に関する情報)
- 会社の企業風土(社員のモチベーション、帰属意識等)等
なお、この把握する情報の内容(開示を受けた情報の中から、何を分析の材料と捉えるかという趣旨)は、買収を検討する主体毎に異なるため、結果的に、対象企業の評価は根本的に検討主体毎に異なる。カントによる、「誰もが共通する認識で対象物を見るということはない」(対象が認識に従う)という教えは、対象法人の調査段階において最も適用される。
2「悟性」(当該調査結果にさまざまな分析を加えることによって出た分析判断)
上記①の過程で得られた情報(開示情報から取捨選択した後の情報)を材料として、財務分析や業界分析、技術力・商品力の評価や財務的・法的問題点の有無の検証、経営者の評価と組織としてのガバナンス構造の評価や企業風土の評価等が実施される。
ここでは、「理性」判断の手前の段階で、集めた情報のテーマごとに分析が行われる。当然ながら上記①と同様にカントの教えは、ここにもあてはまる。仮に、上記①で集めた情報が、他の買収を検討している企業と全く同じであっても(そのようなことは通常はないが)、分析手法としてどのような手法を採用するかは各社の判断によって異なるため、「悟性」に基づく企業の各テーマの評価結果は、買収を検討する企業毎に異なるのである。
3「理性」(各種分析結果に基づき、総合的に結果を導く推論判断)
上記②の過程で得られた各種テーマごとの分析結果を用いて、買収を検討するには、A社と買収対象企業であるB社のシナジーの有無とそれをも踏まえたB社の修正事業計画を策定し、B社の価値評価を行ったうえで具体的な買収価格を算出する。そのうえで、B社の経営者やガバナンス上の課題、従業員における課題等を整理したうえで、B社に対するPMI方針の検討も同時に行うことによって、上記の修正事業計画の妥当性を確認する。
更に自社の資金調達方法をも加味したうえで買収の判断をするのが通常である。ここでも、買収側の企業にて強いシナジーがあれば上記の修正事業計画もより積極的な内容になりうるし、買収側の財務内容が良く買収資金調達が容易であれば、前向きな買収の判断を行う方向に影響を与える。
カントの教えである「対象が認識に従う」は、①情報調査段階、②情報分析段階、③総合判断段階の全局面で、主体毎に認識内容や判断内容が異なる以上、自社の事業戦略や財務内容、組織能力や企業風土等に照らして買収判断をしていく姿勢が重要ということを示唆する。
昨今、専門のDD(デューデリジェンス)業者で行っている画一的な各種DDや、FA(ファイナンシャルアドバイザー)等が実施する一般的な価値評価の手法を適用して買収の是非を考える企業は少なくない。確かに、投資ファンド等が行う投資としてのM&Aは、その後の売却が想定されている以上、EXIT価格の試算のために一般的なDDや企業価値評価を実施する必要性はある。
これに対し、事業会社が行うM&Aの場合は、転売を予定していない企業同士の統合であるため、買収先企業をどのように調査をして、どのように評価して、買収後のシナジーや成長をどう予測するかという点において買収側の企業が主体的に考える能力を身につけることが重要である。
私は、カントの教えから、各企業が、このようなM&Aの原点に立ち戻って考える必要性を感じた。
ビジネスでも重要なカントの道徳法則

「コペルニクス的転回」に加えて、カントの道徳法則もビジネスで重要となる。カントの道徳法則は、「定言命法」と「仮言命法」という言葉の対比で表現されている。
「仮言命法」は、「もし~ならば、~せよ。」という仮定的な考え方だ。、例えば、「あの人は金持ちなので、助けた場合にはその後の見返りが期待できる。だから、助けよう。」というような、見返り付きの善行を意味する。
カントは、このような善行は道徳的ではなく、見返りを求めることなく善行を行う「定言命法」(無条件に「~せよ。」)を道徳的な行為として推奨している。
カントの教えによるなら、現在、上場企業の規制がコーポレートガバナンスコードによって年々厳しくなっている中、ESG等の道徳的な行動は、規制への対応や開示義務の履行、市場評価の向上といった見返りや事実上の強制に基づくのではなく、本来は企業自身の倫理観に根ざして自発的に行われるべきものだ。
カントは、行動原理について、以下のように述べている。
「汝の採用する行動原理(格律)が、常に同時に普遍的な立法の原理としても妥当するよう行動せよ」
自分で作り出したルール(道徳法則)が、理性を持つ人たちの国家ルール(普遍的なルール)として成り立つのかをよく自分で考えて行動すべきという行動原理を推奨している。
道徳的行動は、国家や他者から強いられて行うものではなく、また、対価としての見返りがあるから行うものではなく、あくまでも自らの自由意志で実施するものである、と述べている。
我々の企業活動においても、ESG等の道徳的行動は世の中から求められている側面は少なくない。だが、「他社が行うから追随して実施する」「やらざるをえないから実施する」「投資家から評価されたいから実施する」のではなく、「自らやるべきだと思うから実施する」という考え方が重要ではないか。企業のESG等の活動が会社の自発的な議論の上に成り立っているのかを、カントの教えを踏まえて今一度検討する必要がある。
最後に
前にも述べたように、私は、哲学という学問の素人にすぎない。したがって、哲学者が、ビジネスの局面で本当にそのように考えるかを保証するものではない。私は、哲学者の考えから類推して、私見として述べているにすぎないのだ。
ただ、ビジネスにおいて、哲学を理解して行動することが重要であり、哲学は、人々やその集合体である企業の活動において活用されて初めて意味があるものであると考えている。哲学をテーマとして原稿を作成しているのは、上記のような考えがあるからだ。
そのような中で、ビジネスに当てはめやすい哲学理論を勝手に拾い出したうえで原稿を作成していることをご容赦いただきたい。本稿を読んで、少しでも、哲学に興味を持つ方が出てくるのであれば本望である。
参考文献
- 答えの出ない問いはどのように問われるべきか? カント 純粋理性批判(西研著:NHK100分名著books)
- はじめてのカント『純粋理性批判』(竹田青嗣著:講談社現代新書)
- カント入門講義 超越論的観念論のロジック(冨田恭彦著:ちくま学芸文庫)



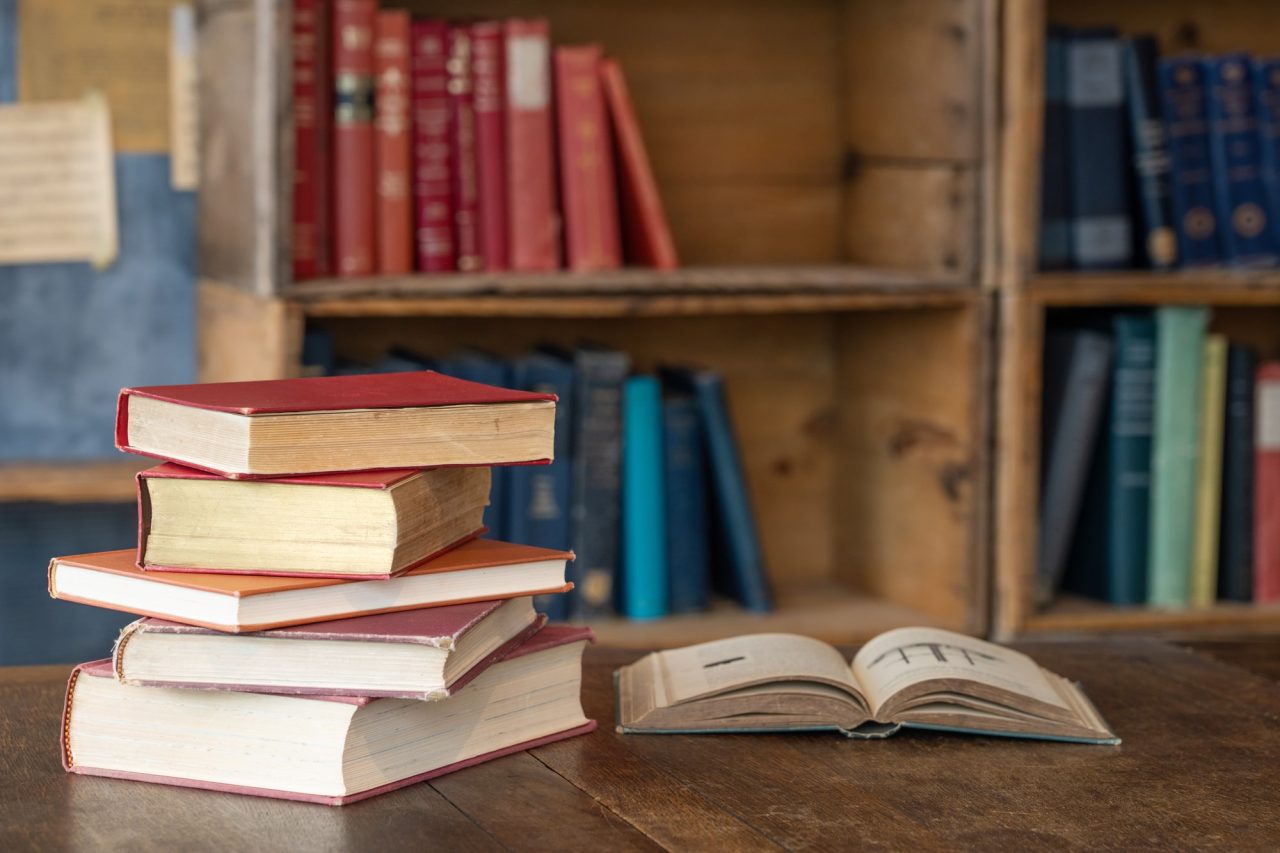

















コメントが送信されました。