読了目安:9分
今こそ女性目線の都市再興が必要な理由
近代以降、「都市」と呼ばれる社会空間は男性目線で構築されてきたようだ。少なくとも、女性の一人歩きを前提とした都市構築は進んでいないように見える。女性の社会進出が進んだ20世紀、女性は都市が持つ暴力性との対峙を余儀なくされた。そんな現代の都市を彼女たちの目線で再改造する必要はないだろうか?その再改造に伴う投資が増えることで、マクロ的な経済浮揚効果も期待できるかもしれない。
女性目線で再構築した「新しい都市社会論」とは

2023年5月、法律文化社より「ガールズ・アーバン・スタディーズ:『女子』たちの遊ぶ・つながる・生き抜く」が発刊された。これは社会学者15人の論文集であり、女性視点のユニークな都市社会論である。
筆者は長年、個人消費に関するリサーチやコンサルティングに従事してきた。社会学を専門に学んだ経験はないが、個人消費の分析の中で都市や社会を語ることも少なくなかった。
同著の主張は、筆者が都市・社会を語る際に保持していた座標軸を大きく揺さぶった。本稿では、その内容に触れながら、新しい都市社会論の可能性について議論していきたい。
古い町並みへのノスタルジーは男性目線が土台?

資本主義の隆盛と、それに伴う古き良き文化の衰退。この対立軸を下敷きにした物語は、洋の東西を問わず、産業革命以降の文学や芸術における主題の一つだった。
特に19世紀に開花した「ロマン主義」は、産業革命後の工業文明を「グロテスク」と批判した。フランスのユーゴーやドイツのシュレーゲル兄弟、イギリスのワーズワースたちだ。
ロシアでもプーシキンらが登場した。20世紀末までに至るまで、折に触れてこのテーマを手掛ける小説家さえいた。「土台穴」で穴を掘り続ける労働者を著したプラトーノフが好例だろう。
「資本主義の隆盛」と「文化の衰退」という対立軸では、郷愁とともに後者への恋慕が強くなりがちだ。山崎貴監督の「ALWAYS 三丁目の夕日」など、日本における映画での扱いも同様だ。
駅前の一杯飲み屋街が取り壊される。
無機質な駅ビルが林立する。
商店街がシャッター街になる。
幹線道路沿いにモールがオープンする。
前述書の社会学者らは、これら「懐古主義」をナンセンスであると喝破している。「古い街並みへのノスタルジーは、男性目線によるバイアスを受けている」と。
女性の一人外出が一般的ではなかった19世紀の欧州都市

現代の都市は女性の一人外食を前提に構築されていないという。懐古主義の対象である一杯飲み屋は、若い女性が一人で気軽に行ける場所ではないだろう。
外食産業は主に男性を対象として成長してきた。
例えば、江戸時代は参勤交代で独身男性が江戸に多く、彼ら向けの外食産業やその他サービス業(遊郭などを含む)が成長した。
19世紀の欧州ではカフェ文化が成長した。代表例は「カフェに囲まれた街」と呼ばれるオーストリアのウィーンだろう。作家のツヴァイクや画家のクリムトなどが集った。
一方で、女性はカフェへの入店を禁じられていた。当時は女性の一人外出さえ、一般的ではなかった。目的もなく一人外出をする女性は娼婦と認識されていた時代だ。
一般女性の一人外出は「買い物」という消費行為と紐づいた場合に限られていた。女性にとっての消費行為は、自立や解放を獲得するための数少ない重要な術だったのだろう。
そうした構図は現代も大きく変わっていないのではないだろうか。郷愁の対象である古き良い町並みは男性目線で成立している。無機質に見えるモールや駅ビルこそが、一人外出を欲する女性を自由にする面を持っているように思える。
アフタヌーンティーはなぜ流行した?

同著の中で、相模女子大学教授の中西泰子氏は、牛丼チェーン店における女性の一人外食を紹介している。女性が牛丼チェーン店に一人で入ると、男性から不躾にジロジロと見られるのだという。
場合によっては、「居酒屋に行かない?」と声を掛けられることもあるらしい。一人外食をする女性にとっての避難場所・安全圏としてスターバックスが発展したと中西氏は分析する。
シンクロして社会に浸透した「産業革命」と「資本主義」は、均質な労働力の集合を必要とする。つまり、見知らぬ他人同士が知り合って、新しい組織を構築することを前提にしている。
見知らぬ他人同士の会話をスムーズにするため、男性の場合、古くはカフェやパブが発展し、近年では居酒屋が成長した。
女性の場合は「お茶」だ。19世紀の欧州の女性は、カフェへの出入りは禁止されたが、ティールームへの出入りは自由だった。「お茶」は女性の自立や解放のシンボルだった。
ここ数年、アフタヌーンティーが日本で盛り上がっている。女性の一人外出、友人とのおしゃべりなど、女性目線で創造可能な新しい市場はまだまだ存在する。
都市の空気は自由にしない?

中世ドイツには「都市の空気は自由にする」という格言があった。農奴や手工業者が都市に来て一定程度(1年程度)を経過すれば、身分が自由になるという意味だ。
しかし、女性目線で見ると「現代の都市は十分に自由ではない」というのが同著の主張だ。外食だけではない。サービス業全体を見ても同様のようだ。
女性が買い物をする限りにおいて、都市は女性に優しい。しかし、休息や滞在を所望した瞬間、都市は個室ビデオ店やカプセルホテルなど男性目線の暴力性を表出する。
都市における精神構造も自由とは程遠いという指摘もある。映画にもなった山内マリコ氏の小説「あのこは貴族」には、上京した地方出身の若い女性が興味深く描かれている。
父親の男尊女卑から逃れたくて上京した主人公の女性。彼女は東京でお付き合いをする男性を見つける。しかも、彼は東京の名家出身。実はこれが悪夢だった。
彼の親族は男性も女性も中学から有名私立出身者ばかり。地方出身の主人公は好奇の目で見られる。都心には、「地方は異形の男尊女卑」という強いパターナリズム(権力や能力のある者が弱い立場の者に対して、弱い立場の者の意思を問わずに干渉・介入すること)が垣間見えるのだ。
都市交通の効率性と痴漢の関係性

都市のインフラについても、女性目線での改善の余地がある。同著において、日本女子大学教授の田中大介氏は都市交通の効率性と痴漢のトレードオフを紹介している。
都市における公共交通の発達は、当該都市における生産性を大きく決定する。人口が短時間で集合し、お互いの知を交換することで創造的な仕事が生まれるからだ。
しかし、公共交通の効率性追求は乗客同士の物理的かつ身体的密着を不可避とする。ここでも男性目線で構築された都市が、女性に対する暴力性を出現させる。
2017年に検挙された痴漢数の約3分の1が東京都だ。東京都の痴漢検挙数の80%が電車内だという。都市における交通効率改善の負の側面が置き去りにされている事例だ。
女性専用車両は21世紀に復活した。それでも痴漢検挙数は絶えない。女性専用車両だけでなく、さらなる踏み込んだ施策が、政府・公共交通事業者ともに必要ではないだろうか。
社会学の泰斗・見田宗介氏は、高度経済成長期の都市を「まなざしの地獄」と呼んだ。他人の視線から逃れられない社会空間としての都市に対する、極めて鋭い表現である。
男性一人を前提とした外食やサービス業、都市の名家に潜むパターナリズム、女性の快適性が置き去りにされた公共交通。女性にとっての「まなざしの地獄」は21世紀も続いているのではないだろうか。
女性目線の都市再設計が鍵を握る
現代の都市が抱える問題を列挙してきたが、現状をネガティブに捉えるだけでは意味がない。むしろ、これをどのようにプラスに転換していくかという発想が求められる。
喫緊の課題は、都市全体を男性目線から遠ざけることではないだろうか。
公共交通や商業施設、娯楽施設、ビル、住宅、自動車など、女性目線での改造投資を促進してはどうだろうか。
これは、ESGの「S」の視点による都市再設計とも言える。ひょっとすると、「令和の列島改造論」とも呼べるマクロ政策への止揚も可能になるかもしれない。
女性の住みやすさや働きやすさは、今後の日本にとって、十分に魅力的なソフトパワーになりうる。官民挙げて取り組むべき課題ではないだろうか。









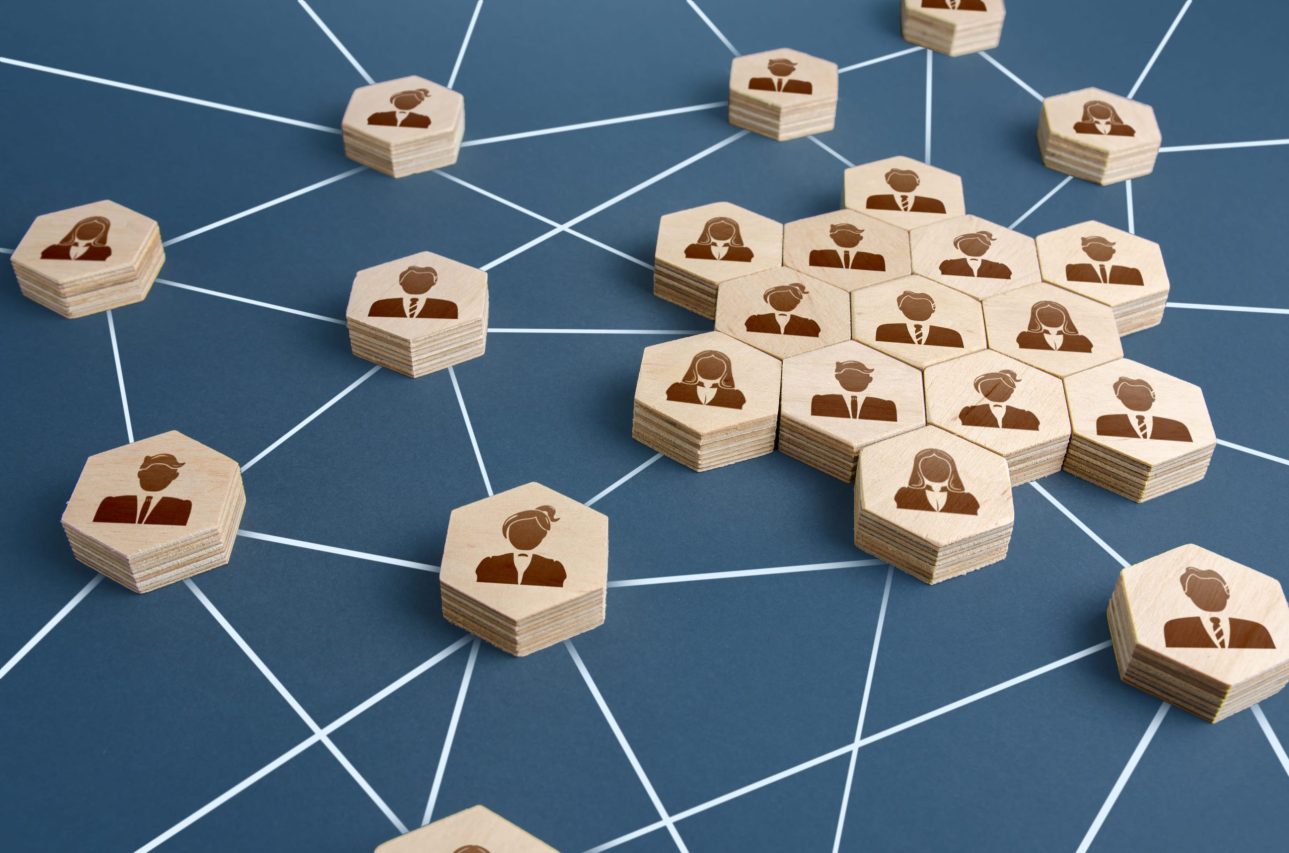












コメントが送信されました。