読了目安:12分
「G」(企業統治)を忘れていないか 日本の脆弱なESG
ここ数年、「ESG」投資という言葉がすっかりと普及した。しかし、E(環境)、S(社会)、G(企業統治)という3の視座が統合されるようになったのは、つい最近の話だ。日本では、「E」や「S」を過度に重視し「G」の軽視が懸念される。株主と経営者の死闘の末、「G」企業統治が醸成された米国の歴史を参考に、日本の企業統治について考えた。
本記事の関連書籍が出版されました。
「良い投資」とβアクティビズム MPT現代ポートフォリオ理論を超えて
-
発行日
-
2022年10月21日
-
著者名
-
ジョン・ルコムニク 著、ジェームズ・P・ホーリー 著、
松岡 真宏 監訳 月沢 李歌子 訳
-
発行元
-
日本経済新聞出版
粗野で剝き出しの資本主義を産み出した蘭・東インド会社

Sinclair CapitalのマネージングパートナーであるJonLukomnik氏が2021年に出版した『Moving Beyond Modern Portfolio Theory』を参考に、当時の東インド会社が抱えていた企業統治問題を見てみよう。
※「Moving Beyond Modern Portfolio Theory: Investing That Matters 」日本語版未発行
著者Jon Lukomnik , James P. Hawley 出版社Routledge
企業統治の話は、1602年に設立されたオランダの東インド会社にまで遡る。
同著によると、東インド会社の役員報酬は透明性がなく、株主のあずかり知らないところで決定されていた。
そもそも同社を設立した目的(最近の流行の言葉でいう「パーパス(purpose)」)も曖昧だった。オランダが国家として貿易増進やアジアへの影響力拡大を目指して設立された組織なのか、純粋に投資家に報いるための組織なのか。明確に示されていなかった。
現物による「配当」 育たない企業統治

適正な株主還元も実行されなかった。Isaac Le Maire氏という蘭・東インド会社最初の株主が、同社に対し、配当の未払いについてクレームをしたことがあった。クレームを受け、同社は確かに配当を支払い始めた。しかし、それは金銭ではなく、胡椒やナツメグによる現物の支払いだった。
粗野で剝き出しの原始的資本主義が、ビッグバンの如く400年前に始まった。同著によれば、その後380年間余り、近現代経営の伽藍ともいうべき会社(主に株式会社)という存在は、東インド会社のそれと似たり寄ったりで、本格的に企業統治に焦点が当たったことはなかった。
企業経営者はその地位に留まることを渇望し、それを実現するためのエコシステムをエゴイスティックに創造した。
企業をチェックする役割は政府だけに委ねられた。
それとて、企業経営者が、政府との間にご都合主義的な関係性を築くことで、チェック自体が骨抜きになった。企業経営者は、その地位が供与する社会空間で惰眠を貪り、寄生を続けた。
MPTと企業統治
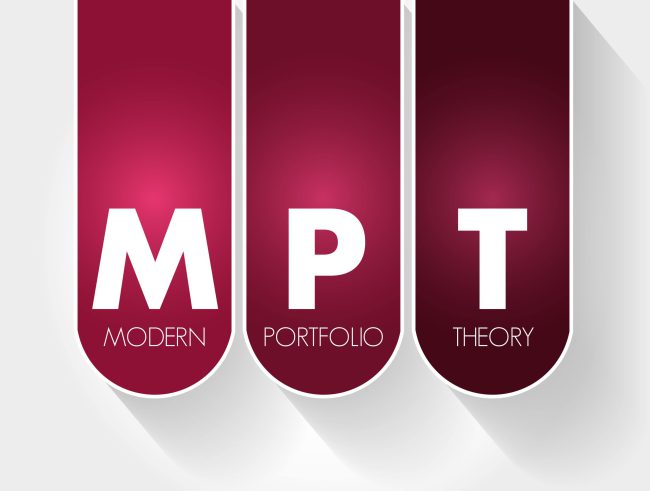
1952年Harry Markowitz氏が、現代ポートフォリオ理論(MPT:Modern Portfolio Theory)を発表した。MPTはその後の株式投資の理論的支柱となり、Markowitz氏は1990年にノーベル経済学賞を受賞した。MPTは、株式投資という人間の金銭欲を凝縮した社会的システムに、美しい科学性の衣をまとわせる十分な効果を発揮した。
MPTは数学的に各社の企業価値を算出するのに有用なツールだ。しかし、科学性を強調すればするほど、理論は現実と乖離する。
MPTには、企業統治の視点はすっぽりと抜け落ちていた。
理論の中では、企業統治は「モデル外の攪乱項」という扱いだった。MPTが株式投資の世界に広まっても、東インド会社以来の企業統治問題は相変わらずで、改善の兆しはなかった。
Lukomnik氏は、MPT全盛の現代に一石を投じようとした。理論と現実の乖離を埋めようとした。だからこそ、“MPTを超えて進もう”という意味で、『Moving Beyond Modern Portfolio Theory』という挑戦的なタイトルを付け、上述の本を出版したのではなかろうか。
投資家の機関化がパワーバランスを変えた

企業統治における大陸移動的な大変化は、投資家の機関化によって生じた。個人投資家ではなく、それらを束ねる役割・機能が台頭したことで、専制君主たる企業経営者と、投資家との間のパワーバランスの変化が始まった。
米国における投資信託の資金総額は1960~1965年の5年間で2倍となり、次の1965~1970年の5年間でも同様に2倍となった。
1974年にはERISA法(Employee Retirement Income Security Act)が制定され、企業年金の運用者に対して自らの企業統治の拡充が促された。その4年後の1978年には、税制優遇を含んだ401Kが導入された。
米国の株式市場において、1950年当時、機関投資家のシェアは僅か8%であり、個人投資家が92%を占めていた。
しかし、上述の政策を背景に、機関投資家のシェアは1981年には40%近くに上昇し、2017年には80%を超過した。Lukomnik氏は同著で叫ぶ。「資本家社会における力とは、資本を支配するもの次第だ」と。
株主軽視、グリーンメーラーと共生した企業経営者

現代における企業統治誕生のきっかけは、グリーンメール(greenmail)だ。
グリーンメールとは、特定の企業の株式を買い占め、それを企業側に高値で買い取らせることを目的にした一種の脅迫状だ。買い占めを行う主体をグリーンメーラーと呼ぶ。
脅迫状は英語で通常「ブラックメール」だが、ドル紙幣をイメージさせるグリーンという単語が使用された。
1980年代の米国ではグリーンメールが急増した。例えば、David Murdock氏が、Occidental Petroleumの筆頭株主となった事例が有名だ。Murdock氏は、市場で取引されている株価より42%高いプレミアム価格で株式を会社側に買い取らせることに成功し、194百万ドルを手にした。
グリーンメーラーと経営者は、敵対的ではない。むしろ、経済合理的な共生関係にある。
グリーンメーラーは、会社側に高値で株式を買い取らせることで収益を得る。経営者側は、会社のバランスシート上の現預金とグリーンメーラーの株式と交換し、グリーンメーラーに会社から出て行ってもらう。こうすることで、経営者側は会社内での自分の既存ポジションを確保し、高給を食み(はみ)続けるのだ。
グリーンメールを解決する過程で、唯一損をするのは株主だ。
グリーンメールの横行をきっかけに、機関投資家が立ち上がった。東インド会社の事例では個々の株主は非力だった。しかし、機関化が進展した1980年代の米国は、380年前のオランダとは明らかに異なった。
企業経営者と投資家の死闘
Quaker State Oil案件で名をはせたグリーンメーラーSaul Steinberg氏が次に選んだ大物ターゲットはWalt Disneyだった。
果たして、DisneyがSteinberg氏に巨額の株式買い取り費用を払ったことで、同社の株価は急落し、同社の株を保有していたカリフォルニア州職員退職年金基金(CalPERS:The California Public Employees’ Retirement System)は巨額損失を負った。
機関投資家がまとまる
当時、同州財務長官だったBig Daddyこと、Jesse Unruh氏が激怒し、事態が動いた。彼は、他州の財務長官と連携し、機関投資家評議会(CII:Council of Institutional Investors)を立ち上げ、株主利益の保護や企業統治の改善運動を開始した。
設立当時、CII加盟の年金基金総額は1,000億米ドルだったが、今では正会員で4兆米ドル、準会員で35兆米ドルとなっている。
CIIは、最初はグリーンメールのような企業への攻撃に対する防御に専心した。次第に、より積極的に企業経営に関わる提言を強め、「株主権利章典法(Shareholder’s Bill of Rights )」を公布した。悪名高いBoone Pickens氏やCarl Icahn氏らと格闘し、テレビのリアリティ番組さながら多くの米国民に話題を振りまいた。
1987年のCII会議におけるスピーチで、弁護士のIra Millsteinは「同業他社比で優位な経営をしている企業に投資する」ことを呼び掛けた。CalPERSのExecutive DirectorのDale Hansen氏は「家畜を動かす(move the herd)」ように投資先企業の収益改善を求め、動きが遅い企業を叱咤した。
マッキンゼーも当時、良好な企業統治の企業とそうでない企業の株価パフォーマンスを調査し、企業統治と株価との間に存する正の相関にお墨付きを与えた(この相関については反対の研究結果もある)。
暗闘の末、主権は株主に
1980年代を中心とした10~15年の暗闘を経て、ESG経営の一つであるG(企業統治)の主権が企業経営者から株主に禅譲された。東インド会社の設立から実に380年余りの時空を経て、ようやく「カエサルのものはカエサルに、神のものは神に」が実現された。
「G」(企業統治)の戦いを経験していない日本の弱さ

ESG経営のEやSも、40年以上前から指摘はされていた。TIAA-CREFのPeter Clapman氏は、S(社会)の観点からアパルトヘイトを続けていた南アフリカ製品のボイコットを提唱した。
Franklin Research and DevelopmentのJoan Bavaria氏は、E(環境)の観点からアラスカで座礁したエクソンのタンカーが引き起こした重大な環境破壊を問題視した。
しかし、これらEやSは当時、焦点として世界的な広がりを見せなかった。ESとGが相互に引力を持ちだしたのはそれほど遠い昔の話ではない。
歴史的に見ると、米国では圧倒的にGが焦点だった。
衆人環視の劇場型経済の中で、投資家と経営者の血みどろの激闘が行われた。激闘を通じて両者は切磋琢磨し、米国企業の収益性は飛躍的に高まり、世界中の投資マネーを惹きつけた。
翻って日本企業。米国で観察された苛烈なGの戦いはなく、投資家も経営者も研磨されていない。収益性も米国や諸外国に劣後している。市民革命を経験せずに獲得した民主主義は脆弱だ。Gの戦いを経ずに行きついたESG経営なるものも脆弱で、強靭性に欠ける。
企業統治強化、収益性引き上げが不可欠
日本でESG経営のEやSが強調されること自体、悪いことではない。
しかし、同時に、中途半端になっているGを強化し、収益性を諸外国並みに引き上げることを看過してはならない。EとSの試みがいかに蓄積されても、Gが不十分で収益性や成長力に乏しい企業には、人・モノ・金が惹かれることはないだろう。



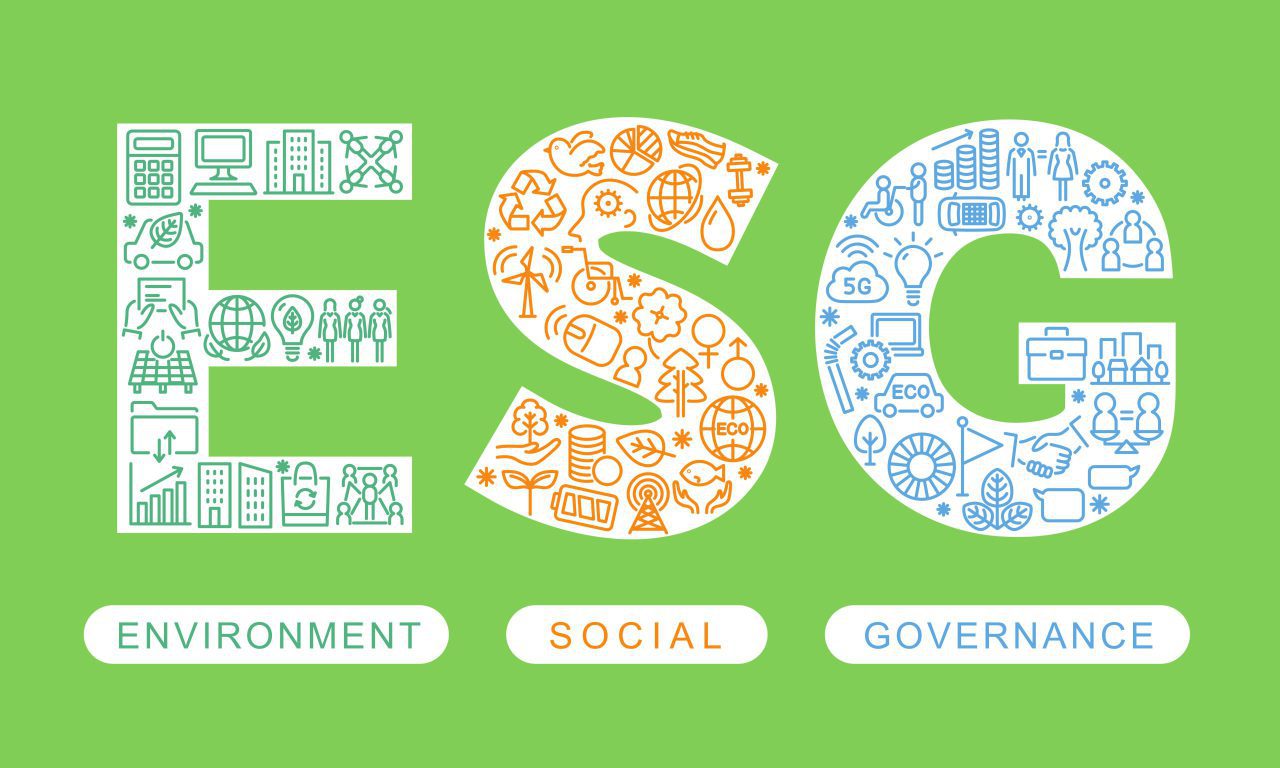



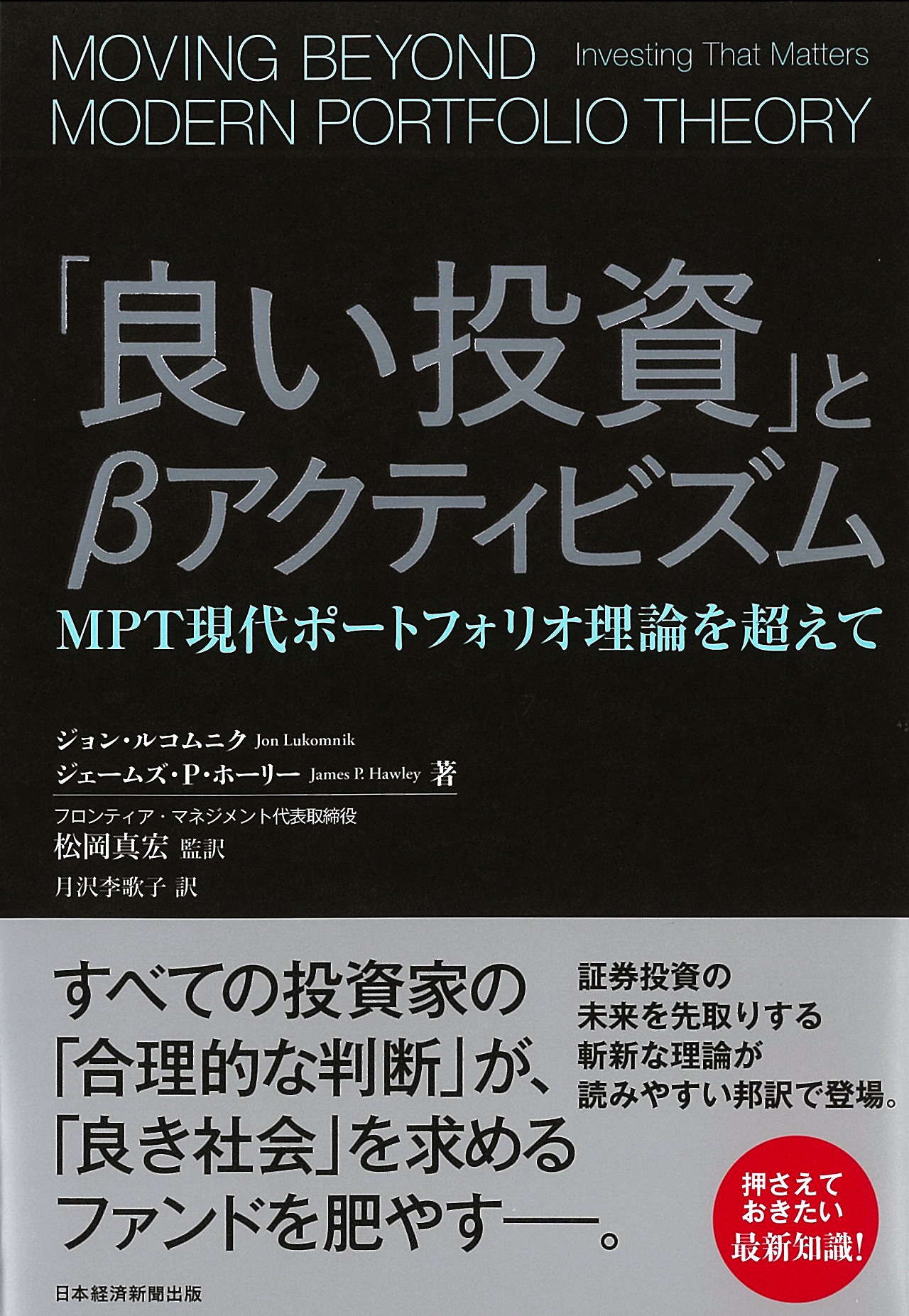















コメントが送信されました。