読了目安:6分
村上春樹さんから学ぶ経営③「創造する人間はエゴイスティックにならざるを得ない」
「村上春樹さんに学ぶ経営」の3回目になります。前回に続き今回のテーマも「差異化」「天邪鬼」「人と違う」です。それでは下記の一文から。
人と違う道
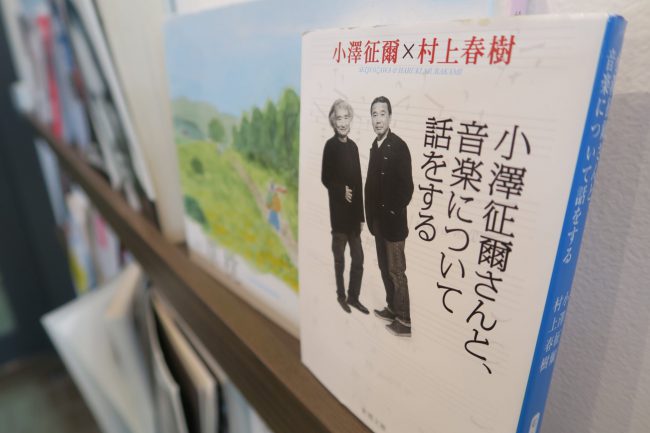
『ものを創造する人間は基本的にエゴイスティックにならざるを得ない、というとけっこう傲慢な物言いになってしまうが、それは好むと好まざるとにかかわらず、紛れもない事実である。いつもまわりを見まわして、波風を立てないように、他人の神経を逆なでしないように、常にうまい落としどころを考えながら生活を送っていたら、どのような分野であれ、その人には創造的な仕事なんてまずできないだろう』。
『小澤征爾さんと、音楽について話をする』(新潮社)からの引用です。同書は指揮者小澤征爾氏との対談集ですが、対談というよりは、「音楽が大好きな二人がウィスキーを傾けつつ、音楽を聴きながら音楽について語りあった」本です。音楽に関して門外漢の筆者は専門的なことは一切理解できませんでしたが、そんな人間が読んでも楽しいので、音楽好き、特にクラシック音楽好きの人にはたまらない一冊ではないでしょうか。
閑話休題。新しい技術・製品を開発するにあたっては、いわずもがなではありますが、人と同じことをやっていても無理です。このことを端的に言い表したのが、クラレや中国電力などの元社長にして篤志家としても知られる大原孫三郎氏の一言です。
「仕事を始めるときには、十人のうち二、三人が賛成するときにはじめなければならない。一人も賛成がないというのでは早すぎるが、十人のうち五人も賛成するようなときには、着手してもすでに手遅れだ。七人も八人も賛成するようならば、もうやらないほうが良い」(『大原孫三郎-善意と戦略の経営者』兼田麗子、中公新書)。
いかにして人と違う道を往くか?
現実には、皆が共通の目標に向かって開発をしている業界が多いように思います。その象徴的な事例はテレビです。大画面、画素数、低消費電力・・・その時々で訴えるポイントは変わってきましたが、結局は同じ土俵での競争だったと言えそうです。もちろん、開発の現場では差異化を必死に追及していたことは間違いないでしょうが、家電量販店に並べられている多くのテレビのメーカー名を隠したとしたら、消費者にはどのブランドかわかる人はいないでしょうし、もしかしたらプロメーカー関係者でもわからないかもしれません。
プロでも区別がつかないような製品であれば、価格競争しかないというのは当然のことでしょう。電波を受信して、映す――という基本構造が変わらない以上、当然ではあるのですが・・・。
同じロードマップを描いても…

一方、営業利益率を継続的に計上し、優れた企業として著名な企業に教えていただいた言葉で印象的であったのは、「皆が共有している『線形の』技術ロードマップでは差異化はできない」というものでした。
なるほどと私は膝を打ちました。多くの業界においては、業界全体で方向性が共有された技術ロードマップがあります。その産業に属している企業のすべてが同じ目標に向かって産業として努力します。これは、消費者からみれば効率的なシステムといえますし、業界全体が認知している技術開発ロードマップにのっとり黙々と技術開発に取り組むのは、修行僧のような美しさもあります。職人の世界といっても良いでしょう。
しかし、「共有されている」すなわち「線形な」技術開発では差異化は容易ではないことになります。同一の土俵での限定的差異化競争になってしまい、おそらく最終的には価格競争になってしまうということです。
顧客が欲してからでは遅い

そもそも、顧客(消費者)でさえ、自分が何を欲しているのかはわからないのです。かのウォークマンだって、量販店、メディア、社内での評価は低く、当初、月間販売台数は5000台に満たなかったとか。IBM初代社長トーマス・ワトソンが「コンピュータの需要は世界で5台」と言ったとされていることに関しては「史実ではない」との指摘もありますが、とはいえ、100兆円産業になるとは夢にも思わなかったことでしょう。
筆者が尊敬する複数の経営者は言っていました。「顧客の話を聞きに行け、でも聞くな」と。顧客が欲しいというようなものはもう遅い。顧客は同業他社にも同じことを言っているはずで、それではたいした利益は得られない。顧客の話を聞くことで、顧客が気付いていない需要を感じるセンスが重要である、という教えでした。
稀代の新「製品」開発者秋元康さんも企画会議では上記大原氏と全く同じ方針であることをインタニューで述べており(十人のうち一人が賛成するぐらいが良い)、また、著作の中では「予定調和を壊す。人は予想が裏切られたときに面白いと思う」「嫌われる勇気。わがままに生きる勇気。皆がおもしろいとおもう企画ほどつまらないものはない」と述べています(「秋元康の仕事学」、NHK出版)。
まとめ
同業他社と違うロードマップを歩んだり、消費者アンケートで言及されることのない製品開発に取り組むのは勇気が要ります。傲慢といわれようが、変人と思われようが、いかにエゴイスティックになれるか――。
▼村上春樹さんから学ぶ経営(シリーズ通してお読み下さい)
「村上春樹さんから学ぶ経営」シリーズ










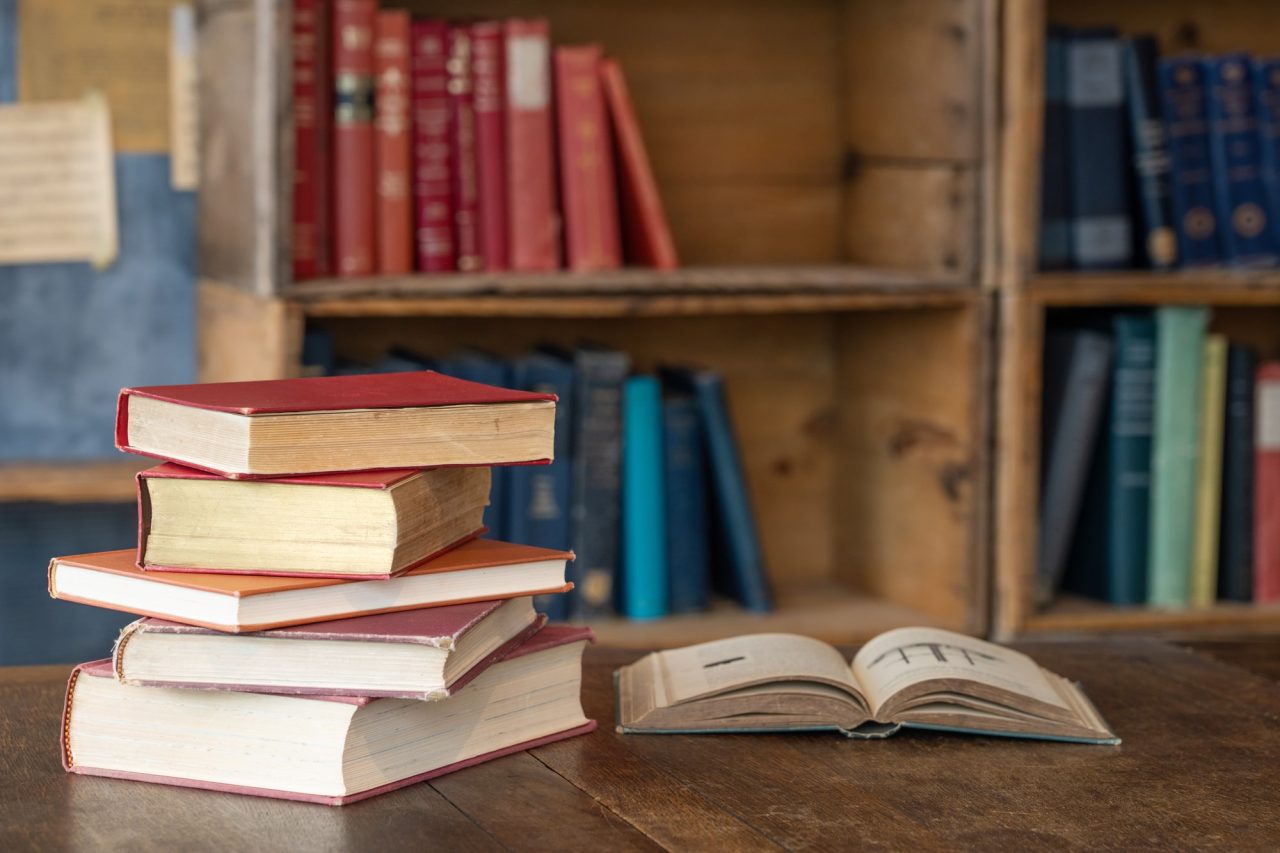










コメントが送信されました。