読了目安:9分
モチベーションの下降局面から脱却する方法
モチベーションというものは、自分でコントロールできないさまざまな要因によって上がったり下がったりすることがあります。
極端に言えば、3日続けて雨が降って傘を2回なくしたとか、飛行機に乗って広島に出張に行ったら濃霧で東京に戻った、みたいな天候のせいで下がることもあるくらい気まぐれなものです。あるいは善意を持った相手の傷つける言葉によってモチベーションが下がることもあります。
合理的に考えたいですが、感情なので、どうしようもなく下がったりします。もはや、避けられない=突発事故と覚悟を決めるべきかもしれません。避けられないことに対する対策として、アンガーマネジメントの活用が効果的と思いますので、対処法を紹介したいと思います。
モチベーションの上下で変わる仕事の成果や効率性

残念ながら?モチベーションが上がったときと下がったときでは仕事の成果や効率性は大きく変わります。モチベーションのアップはさらにイノベーションの創出につながり、組織全体のパフォーマンス向上に貢献します。目標達成意欲が高まり、集中力が増し、主体的に仕事に取り組むからですが、
営業職であれば顧客への提案に熱心になり、成約率が向上し、売上がアップするかもしれません。事務職であれば業務の効率化を常に考え、より良い方法を模索するため、業務効率が向上し、正確性も向上する可能性があります。
ベイン・アンド・カンパニーとプレジデント社が共同で実施した調査でも、モチベーションの高い社員の生産性はモチベーションが低い社員と比較して3倍近くになるとの結果でした。
※出典
“3人に1人”の不満社員を奮起させるには 成長ビジョンは「やる気」の原動力
https://president.jp/articles/-/23480
エンプロイーエクスペリエンスとは?従業員のエンゲージメントを上げる – 人事担当者のためのミツカリ公式ブログ
https://mitsucari.com/blog/employee_experience/
ですので、下がることを避けるというよりは、下がったら速やかに上げるための手立てを覚えておきたいものです。そもそもモチベーションが下がると、さらに加速するようにモチベーションが下がる要因に巻き込まれて、アリ地獄のような状態に陥ることがあります。気持ちも揺れ動き、仕事が手に着かない。このままの状況が続いたらどうしよう。すべてが、ネガティブなスパイラルに入りこみ、マイナスの状況が長く続く。
そんなアリ地獄にはまらないためにどうしたらいいのか? 重要なのはクールダウンすることです。モチベーションに踊らされている自分の気持ちを静めて、冷静に行動するのです。
すると、不思議と底をうって、モチベーションが上がるきっかけを見つけたりするものです。
モチベーション回復にも有効なアンガーマネジメント

クールダウンするための手法としてはアンガーマネジメントの対処法が参考になると思います。アンガーマネジメントは怒りという感情を上手にコントロールする方法のことです。
もともとは1970年代にアメリカで生まれた、怒りの感情を管理・コントロールするための心理トレーニングです。当初はDV加害者や軽犯罪者の矯正プログラムとして使われていましたが、その後、教育、ビジネス、スポーツなど、幅広い分野で活用されるようになり、日本でもメンタルヘルス対策として注目され、活用がすすんでいます。
職場には、避けられない突発事故でモチベーションダウンが起きやすい土壌が整っていると言えるかもしれません。社内コミュニケーションでも他者との比較や精神的な負担となる機会が増えて、自分自身の価値や立ち位置に対する不安が高まりがちです。
ささいな仕事のミスで「自分は損な役回りばかり」とか「ついてないな」と気持ちが沈んでしまう人が増えています。そんな状況からの脱却にアンガーマネジメントは有効と考えます。感情を制御することで、問題に適切な対処が可能です。自分の感情を客観的に捉え、冷静に対応できれば、結果として仕事が順調に回転し始めて、モチベーションが回復することになります。
では、アンガーマネジメントにはどのように取り組むか? 大きく三つのステップがあります。
1. 衝動のコントロール
頭のなかで1から6までの数字をカウントし、怒りの感情から意識をそらす
2. 思考のコントロール
許容範囲を広げて、怒りを感じる機会を減らす
3. 行動のコントロール
怒るという行動によって状況が変化・改善しないことを理解する
これは怒りをモチベーションが下がる感情に置き換えてみると、同じように有効と理解いただけるのではないでしょうか? アンガーマネジメントは、ただ単に怒りの感情を抑え込むものではなく、自分の状況を客観視することによって、怒りの感情をコントロールするための手法と言われています。
さらに怒りの感情をコントロールすることができれば、対人関係が円滑になるだけではなく、自身についての理解を深めることにもつながるとも言われています。感情が大きく揺れ動くモチベーションダウンの場面でも同じように活用して、対処してみてください。
怒りの六類型

最後に「アンガーマネジメント」を理解する上で、自分自身の怒りのタイプを把握しておくことは重要です。ここで日本アンガーマネジメント協会が提示している「アンガーマネジメント診断」による六つの怒りのタイプを紹介しておきます。前述のように怒りをモチベーションが下がる感情に置き換えてみてください。
●公明正大タイプ
正義感が強く、高い道徳心を持ち、ルールや秩序を重んじるタイプ。周囲から頼りにされ、リーダーシップを発揮することが多い。
しかし、規則を破る人や道徳に反する行為を見ると強いストレスを感じ、公共の場でも迷わず介入してしまうことが多い。自分の正義を絶対視せず、他人の価値観も受け入れる柔軟性を持つことで、怒りをコントロールしやすくなる。
●博学多才タイプ
向上心が高く完璧主義で、困難な状況でも物事をやり遂げる力を持っている。白黒はっきりさせたい傾向があり、明確な答えを求める。
そのため、優柔不断な人や不真面目な人、あいまいな意見に対して強いストレスを感じやすい。自分だけでなく他者にも高い基準を求めがちだが、中間の価値観も認める柔軟性を持つことで、怒りの感情を軽減できる。
●威風堂々タイプ
自信と気品を備え、どんな状況でも堂々と振る舞えるリーダー気質。行動力があり面倒見が良いため、自然と周囲から頼られる。一方でプライドが高く、自分は特別な存在だと考える傾向がある。
望んだ通りに事が進まなかったり、厳しい評価を受けたりすると怒りを感じやすく、時に傲慢(ごうまん)になることもある。自信過剰な部分や支配欲が短所となり得るが、他者の意見も尊重する姿勢を持つことが大切だ。
●天真爛漫(らんまん)タイプ
自立心が強く、思いや考えを素直に表現できるタイプ。好奇心旺盛で行動力があり、思い立ったらすぐに行動に移せるフットワークの軽さが特徴だが、自分の主張が通らない状況や行動を制限される場面で大きなストレスを感じる。
場をわきまえず発言してしまうこともあり、後先考えずに行動して周囲からは強引だと思われることも少なくない。他者の意見にも耳を傾け、時には自分の主張を抑える柔軟性を持つことが重要となる。
●外柔内剛タイプ
外見は穏やかなものの、内面では確固たる信念や価値観を持っているタイプ。自分の決めたことをやり通す意志の強さがある一方、その雰囲気から周囲から頼られることも多い。
自分のルールに反することや、したくないことを強制されるとストレスを感じ、ささいなことで怒りが生じることもある。自分の信条を少し緩め、他者の考えや客観的事実にも目を向けることで、怒りを軽減できる。
●用心堅固タイプ
慎重かつ客観的な判断を好み、物事に対して冷静に対応できる。警戒心が強く、人とは一定の距離を保ちながら関わる傾向がある。
また、周りに頼ることが苦手で、自分のプライベートに踏み込まれたり、パーソナルスペースに侵入されたりするとイライラしやすい。小さなことから他人に頼み事をして、少しずつ信頼できる人を増やしていくことで、怒りの感情をコントロールしやすくなるだろう。
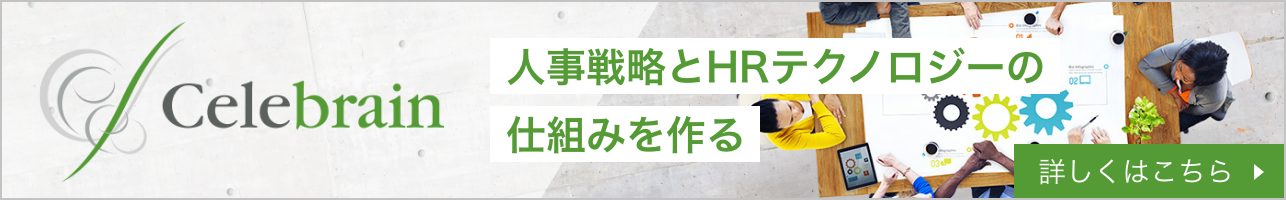







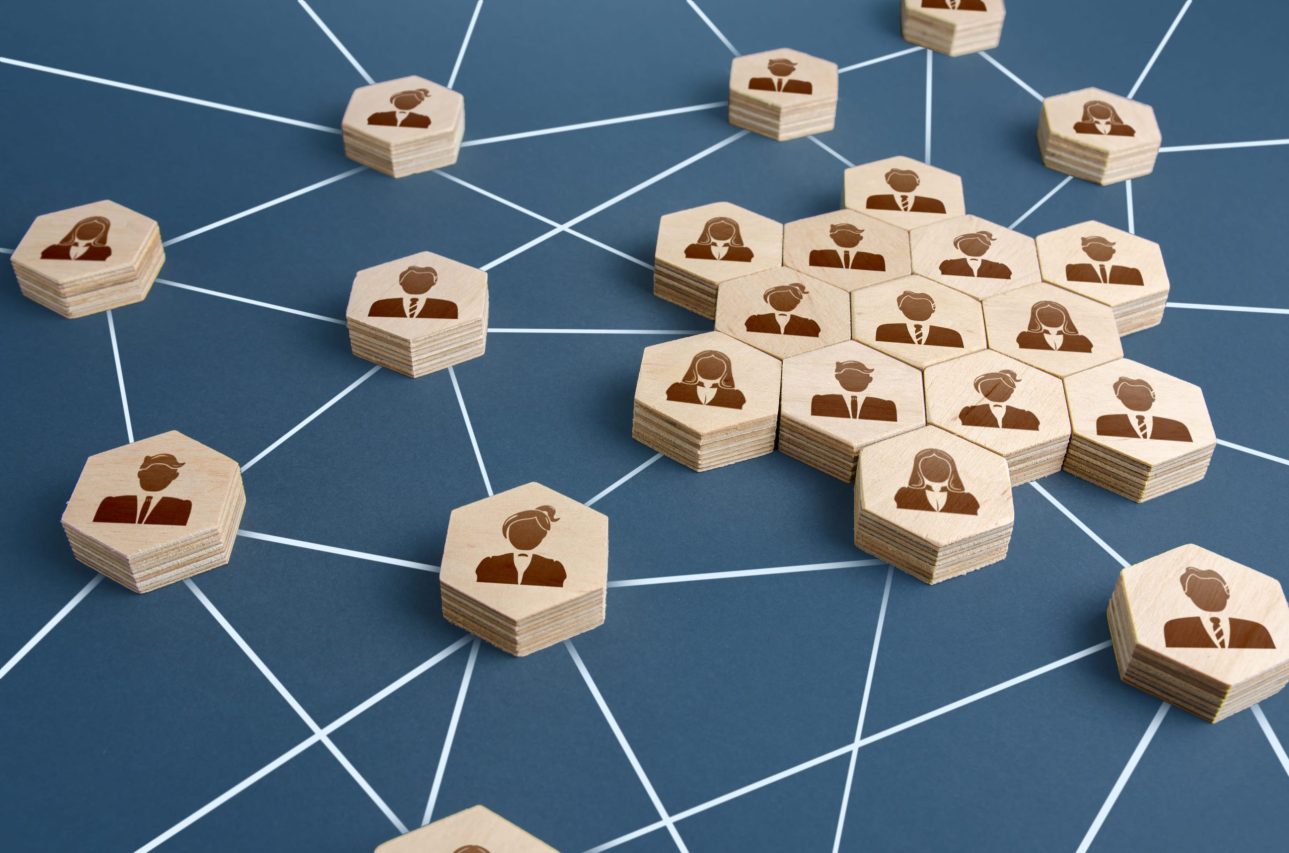













コメントが送信されました。