読了目安:8分
HR×AI活用の最前線 人的資本経営を支える新しい人事戦略
AI活用が加速するなか、人事部門でも採用・評価・育成などに導入が進んでいます。しかし「AIを導入したのに活用されない」という失敗例も少なくありません。なぜ現場に定着しないのか。その原因と、導入に成功する企業の共通点を探ります。
人事でAIは役立つのか?高まる期待とリスク

人事の仕事において、AIは本当に役立つのか? これだけAI活用が加速するなかで、否定的な意見も耳にします。その理由は、人事情報はアナログで“Black Box=属人的に管理するもの”と考えられてきたから。しかし、BlackBox化には、不正に発展したり社内連携を妨げたりするなどのリスクをもたらす可能性が高くなります。
「リスク回避」に加えて、「人事業務の質の向上」や「増加する経営からの要望に対する対処」も必要となり、「AI活用は必須」との機運になりつつあります。
こうした機運に呼応するようにHRテクノロジーの進化はめざましく、AIを活用した人事向けのソリューションも年々進化を遂げている状況です。
採用や評価、育成、配置、エンゲージメント分析まで、かつては属人的にしかできなかった領域が、今やアルゴリズムと大量のデータによって“再構成”されつつあります。
AI導入の落とし穴:活用されない現場の実態

ところが実際にAIを導入した現場は、手放しで成功している例ばかりではありません。特に多いのが「AIを導入したのに、結局現場で活用されていない」という課題です。
せっかく盛り上がりつつある状況が冷めてしまうのは残念なこと。現場での活用を加速させて、定着を進めるにはどうしたらいいのでしょうか?
例えば、あるIT企業では、採用の書類選考を効率化するために、AIが候補者を自動スコアリングするツールを導入しました。候補者の経歴やスキル、職務内容との親和性などを数値化し、選考の初期フェーズを自動化しようという試みです。
導入当初は人事部門内でも大きな注目を集めましたが、半年後の運用状況を確認すると、採用担当者の多くが「参考にはしているが、結局は自分の目で選んでいる」と語っていました。
理由を聞くと、「AIのスコアの根拠がわからない」「直感と合わないと不安になる」「上司に説明がつかない」という声が多数出てきました。AIによる判断結果が「Black Box」に見えてしまい、使いどころをつかめなかったのです。
最終的には、候補者全員に目視で確認し、「AIのスコアも確認はするが、ほとんど参考にしていない」という形に落ち着いてしまいました。
導入したのに活用されない3つの理由
このように、せっかくのツールも「現場が安心して使える仕組み」や「データに対する理解」がなければ、宝の持ち腐れになってしまいます。では、なぜAI導入がうまくいかない企業があるのでしょうか? 原因は大きく三つに分けられます。
- 導入目的が曖昧:
「はやっているから」「効率化したいから」程度の動機では、具体的な活用シーンが見えず、使われないまま終わってしまう - 現場が置き去り:
現場の声を拾わずにシステムだけを先行導入すると、浸透せず形骸化する - 運用設計が不十分:
誰がいつ、どの業務で使うのかが不明確なまま、ツールだけが導入されてしまう
加えて、「AIに判断を任せる」ことへの心理的な抵抗もあります。「AI活用」と聞くと、漠然と、人間の直感や経験が否定されるような感覚を持つ人も少なくありません。
特に評価や昇進といった“センシティブな領域”では、AIの判断が妥当なのか、説明責任を果たせるのかという懸念が強くなります。
AIを活かす鍵は“意思決定のサポート役”にある
確かに、AIには大きな可能性があります。人手では不可能な量のデータを処理して、パターンを抽出し、判断をサポートする力があります。しかしそれは、「活用されてこそ価値を持つ」という前提があることを忘れてはなりません。
今注目されているのは、「人が意思決定するための材料を、AIが用意する」という役割での活用です。AIが人間の代わりに全てを決めるのではなく、膨大な情報の中から意味のある選択肢や傾向を示し、それを人間がかみ砕き、判断する――そんな関係性が理想とされています。
ある中堅メーカーでは、社内のタレントマネジメントを刷新するために、AIによるスキルマッピングの仕組みを導入しました。従業員が入力した職歴や資格、業務内容、キャリア希望などの情報をもとに、AIが適性やスキルの関連性を分析し、配置や育成の判断材料としています。導入から3カ月後には、「この人はプロジェクトAとBの両方に関われそう」「このスキルを持った人は来期の重点育成対象になる」など、従来よりも客観的かつ具体的な人材配置の議論ができるようになりました。
成功事例に共通する「人とAIの分業設計」

前述の中堅メーカーの人事部長は、「AIが全てを決めるのではなく、“何を考えるべきか”を明らかにしてくれる」と語ります。このような成功事例に共通するのは、「AIありきではなく、課題ありきで人とAIの分業を設計している」ことです。
AI導入で本当に重要なのは、こうした“人”と“AI”の共存をデザインすることだと言えるでしょう。
現場に定着させる仕組みづくりの工夫
AIツールの導入がうまくいかない最大の要因の一つは、「導入したら自然と使うようになるはず」という過信にあります。現場が忙しい中で新しい仕組みを使いこなすには、それなりの時間や工夫が要ると理解する必要があるのです。
最初の数週間で「便利そうだとは思うけれど、なんとなく使わなくなった」という事態を防ぐには、現場ごとの業務フローや習熟度に合わせて段階的に定着させる仕組みを設計し、導入後の数カ月をどう支えるかの計画を立てましょう。
ある企業では、AIの導入と合わせて週1回の業務内フィードバックの場を設定しました。ここから、現場の「使ってみたからわかる疑問」を拾い上げ、活用の壁を一つずつクリアしていくという手法をとり、定着につなげたのです。
こうした「使いながら定着させる」プロセスをきちんと描けるかどうかが、生きた施策として成果につなげるための大事な取り組みになります。最初から一人で背負うのではなく、外部の専門家やベンダーに伴走してもらうのも戦略の一つです。
AIは“導入”より“使いこなす仕組み”が重要
人事部門にとって、AIの活用はもはや“チャレンジングな先進事例”ではなく、「向き合うべき課題」の一つです。
人的資本開示の義務化、副業・兼業の増加、離職率の上昇など、これまで以上に「データにもとづいた戦略的な人事」が求められる今、ツールの導入はあくまで入り口にすぎません。大切なのは、「導入したツールをどう“自社の武器”にするか」です。
そのためには、社内の業務フローを見直し、現場との対話を重ね、必要に応じて柔軟に仕組みを進化させていく必要があります。
「そのAI、本当に使いこなせていますか?」
人事部のあなた自身が、そう自問してみることが、AIと共存する第一歩になるのかもしれません。今後ますます加速するHRテクノロジーの波に備え、自社に合った“使いこなせる仕組み”を、今から整えていくことが求められています。
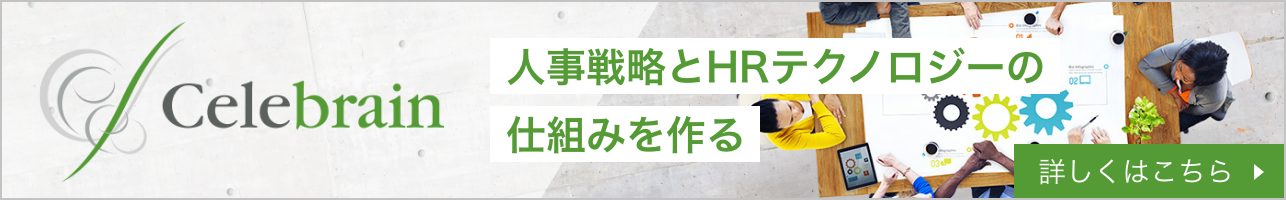






















コメントが送信されました。