読了目安:8分
ガバナンス不全 ~背景と処方箋~
組織(企業)活動が複雑化・グローバル化する中で、ガバナンスの重要性はますます高まっています。しかし、現場では「ガバナンス報告書は作成しているが実態が伴っていない」「ガバナンスを整備するには何をすればよいかわからない」といった声も多く、ガバナンス不全が顕在化するケースが後を絶ちません。そこで本稿ではガバナンス不全の克服に向けたアプローチについて述べてみます。
ガバナンス不全とは

ガバナンスとは、組織の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための、健全かつ継続的に運営される「仕組みとその実行」を指します。経営陣、特に取締役会が中心となって担うべきものであり、会社法やコーポレートガバナンス・コードなどでもその役割が明示されています。取締役会は、企業理念の確立や戦略の方向付け、リスク管理体制の整備などを通じて、企業グループ全体の健全な運営を支える責務を負っています。
ガバナンス不全とは、経営陣のメッセージが現場に浸透せず、ネガティブ情報が報告されない、あるいは放置されるなど、監督機能や内部統制、情報開示、企業文化などが機能不全に陥っている状態を指します。
この状態が続くと、不正多発のみならず、従業員離職、取引先離反、倒産に至ることもあります。他に、M&A後の文化や業態の違いによるコミュニケーション等の障壁も、ガバナンス不全の一因です。特に、急成長企業や新規事業、海外子会社、オーナー企業など、物理的・心理的距離がある組織では、ガバナンス整備そのものが後回しになる傾向があります。
また、ガバナンス不全は「守り」のほころびだけでなく、「攻め」の足かせにもなります。経営目標の未達となる背後にガバナンス不全が潜んでいることがあります。
ガバナンス不全を減らすには

では、ガバナンス不全を減らすためには何をすればいいでしょうか。最初の一歩は現状分析です。どこに課題があるのかを明らかにし、経営陣に「気づき」を与えることが出発点となります。現状分析は特定のテーマに絞って集中的に分析する場合もありますし、制度面や運用面、組織文化面などの切り口からなるべく網羅的になるように分析する場合もあります。以下は切り口の例です。
制度:組織の基本的な枠組みやルール
運用:制度に基づき、実際にガバナンスを機能させるプロセス
組織文化:組織に根付く価値観や行動様式
外部環境:組織外からの要請や変化に対する対応
戦略:組織の戦略や経営目標達成との整合
なお、現状分析にあたっては、組織の「ガバナンス成熟度」の視点を取り入れることもあります。成熟度モデルは一般的な標準モデルはありませんが、現状の成熟度によって分析すべき領域や施策の優先度を変えるなど、組織の統治体制の整備状況や運用レベルを段階的に捉える枠組みとして活用することがあります。

不正が多発した組織を分析すると、ノルマ必達の過剰なプレッシャーがある、内部通報制度が機能していない、けん制ができていないなどの課題があります。その他、子会社における損失の原因が「現地任せ」による放任状態であったり、事業部門からの楽観的な報告を管理部門が十分に検証できていなかったりするなどの課題も浮き彫りになりました。そもそも内部監査では事務不備監査しかしておらず、組織の問題が見落とされている、あるいは議論すらできていない状況です。
そこでガバナンス不全に対しお勧めしたい処方箋の一つが内部監査の高度化です。従来の事務不備監査から、リスクベース監査に進化すると様々な課題の発見が期待できます。リスクベース監査とは、最もリスクの高い領域にリソースを集中させることで監査の効率性を高める手法であり、リスク評価と監査を通じて、組織のリスク管理体制も強化します。
ただし、リスクベース監査の留意点がいくつかあります。まず、経営陣がリスクベース監査の意義を十分に理解していないと、監査の実行や改善提案が軽視されるおそれもあります。監査結果の可視化や経営層との対話を通じて、理解と支援を得ることが重要です。
現場との信頼関係が築けていない場合、監査が形式的になり、実効性を欠く恐れもあります。こうした状況を防ぐには、対話型の監査や現場との協働を重視する姿勢が求められます。
リスク評価が主観的になりやすく、重要なリスクを見落とす可能性があるため、データ分析やAIの活用など客観性を補完する手法を導入することもあります。
監査部門に高度な専門性が求められるため、スキルや経験の不足が障壁となります。こうした課題に立ち向かうためには継続的な教育・研修や外部専門家の活用が有効です。
戦略策定時などでも助言できる機能を持つ監査への転換も有効です。特に、組織の成長局面や外部環境の変化、M&Aのタイミングでもガバナンス不全は発生します。
ガバナンスは整備して終わりではありません。日頃から「この状況下で、このガバナンスで経営目標の実現は可能か?」「その実現を阻害しているリスクは何か?」「自社やグループのどこかに不全が起きていないか?」など経営陣が監督し、経営企画部や監査部門においても情報を提供する体制を整えておくことは大変有効です。その上で、リスク対策を講じ、ルールを見直し、場合によってはガバナンスそのものを見直すなど状況に応じ適応させていくことが重要です。

ガバナンス体制の整備・改善を進めた事例の紹介
最後に、ガバナンス体制の整備・改善を進めた企業の事例を紹介し、改善プロセスの要点を整理します。
A社では、急速な事業拡大により管理部門の体制が追いつかず、属人的な運営が常態化。法務・人事・経理などの基本規程が未整備で、内部統制が機能していませんでした。
現状診断とリスク評価を実施し、組織規程や決裁権限規程、購買管理規程などを整備。運用フローやマニュアルの導入、モニタリング体制の構築を通じてガバナンスを定着させました。その結果、業務の透明性が向上し、従業員の意識も変化。企業の信頼性が回復し、外部ステークホルダーとの関係も改善されました。
B社では、海外子会社との情報共有が不十分で、事業部門からの報告が楽観的すぎるという課題がありました。本社と子会社間で共通のモニタリング指標を設計し、外部環境を含めたリスク要因を定量的に把握する仕組みを導入。報告内容の客観的な検証が可能となり、経営判断の精度が向上しました。
C社では、旧経営陣による不正が発覚し、買収後のPMI(Post Merger Integration)において内部統制・コンプライアンス体制の再構築が急務となりました。J-SOX導入支援、内部監査体制の整備、規程類の改定、グループガバナンスの見直しなどを通じて再発防止策を実行。短期間で枠組みを整え、現場への伴走支援を通じて、ガバナンスの再構築を実現しました。
事例に共通するのは、「現状を正しく把握すること」「改善策を制度と運用の両面から定着させること」です。ガバナンス整備は一過性のプロジェクトではなく、継続的な改善と組織文化への浸透が不可欠です。経営陣が主導し、現場との対話を重ねながら、組織全体で取り組む姿勢が求められます。
ガバナンスの高度化は、企業の信頼を守るだけでなく、持続的な成長を支える戦略的な取り組みです。今こそ、ガバナンスで「守り」を固め、「攻め」へと転換することで、組織の未来を支える基盤を再構築してみてはいかがでしょうか。







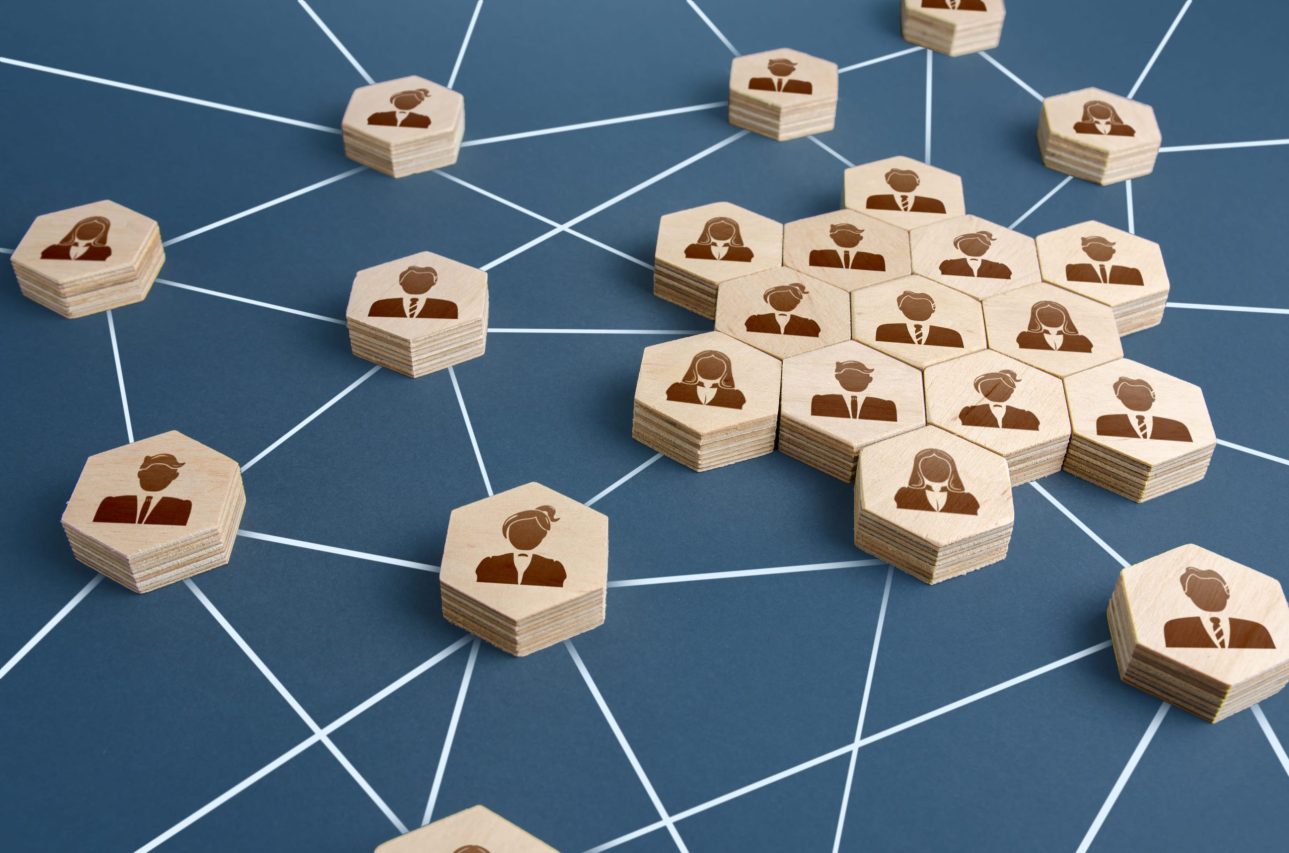














コメントが送信されました。