読了目安:9分
「人的資本の開示義務化」で現場担当者が直面している課題への対応策【事例つき】
人的資本の開示が義務化されて3年目に入りました。人手不足、離職などの人事課題が増加傾向にあるなかで、義務化の対象となった大手企業の経営企画・人事部門には、対応策の指針を示すことが求められています。まず何から手をつけたらいいのでしょうか?
企業の担当者が直面している課題とは

「人的資本に関する取り組みを検討している。実行と見える化に取り組んでほしい」。このようなオーダーを経営者から受けた経営企画・人事部門の悩みを聞く機会が増えています。しかも、取り組みに関して、自社としてのオリジナリティーを示せるようにしてほしいとの要望があるケースも。人的資本の開示において必須である「女性管理職比率」「男性育休取得率」「男女間賃金格差」の改善に向けた取り組みだけでは、他社との差別化にならないといった発想からなのでしょう。
オーダーを受けた立場からすれば、大いに頭を悩ませるところ。何が差別化になるのでしょうか?
「エンゲージメントの把握」が重要
いろいろと考えていくと、あるべき姿として「エンゲージメントの把握」にたどり着く場合が多いのではないでしょうか? エンゲージメントという言葉は、今やビジネス界では広く知られた概念です。もともとはマーケティングの分野で、自社とクライアントとの深い関係性を示す言葉として使われていたのが、近年ではこの考え方が人事の分野にも応用され、「社員と企業の関係性」を示す重要な指標として注目されるようになりました。
例えば、パナソニックは統合報告書において、従業員のエンゲージメント調査の結果を詳細に開示。あるいは楽天グループも人的資本開示の一環として、社員のエンゲージメントに関するデータを積極的に公表しています。
エンゲージメント調査に取り組む企業は今後増加する

データに基づく分析から、課題を明らかにする。その課題に優先順位をつけて、高いものから取り組んでいく。こうした動きに向かって、まずはエンゲージメント調査に取りかかろう……というのが人的資本開示3年目の現状のように見受けます。でも、エンゲージメント調査であれば行っている企業が大半ではないか?と思ってしまいそうになりますが、エンゲージメントに関する情報を開示する企業はまだ半数。調査自体を行っていない企業が随分とあるのです。
ただ、エンゲージメントの把握を行う企業は今後限りなく増えていくことでしょう。エンゲージメントは、人的資本の開示に向けた、ベースとなる指標です。これがないと、何から手をつけていいのか、自社としてのオリジナリティーを考えるすべが見いだせないからです。
調査結果が問題の改善につながらないケースも
前提として、エンゲージメント調査は、社員が会社に対して愛着や誇りを持ち、高い意欲を維持し続けるために何をしたらいいのか、明らかにすることが目的です。ところが調査をした結果大きな問題に直面する可能性が高く、調査したものの、そこで止まっているケースも多く見受けます。
それはどうしてでしょうか? 想像以上に低いスコアが出てしまうためです。
近年、日本企業全体として、このエンゲージメントの低さが問題視されています。アメリカのギャラップによる2023年版の世界的なエンゲージメント調査でも、日本は145カ国中最下位で、「エンゲージしている社員」はわずか5%という結果でした。
「仕事で期待されていると思えない」「成長を後押ししてくれる人がいない」
など、惨憺(さんたん)たる結果に意気消沈し、調査結果を正面から受け止めず、データを放置してしまう企業も少なくありません。
例えば、ある製造業の中堅企業では、エンゲージメント調査で「職場環境への満足度」が低いとの結果が出ました。しかし、人事部門は「最近、組織再編があったから参考にならない」としてこの課題を棚上げしてしまいました。その後も改善施策は行われず、社員の不満が蓄積し、離職率が上昇する事態に。こうした対応は非常にもったいないと言わざるを得ません。
調査結果が低スコアだった場合の対応策

調査結果が低かった場合、それを「伸びしろ」と捉えるべきです。その結果について「なぜそうなったのか」を問いかけ、原因を追究することこそが重要です。
例えば、あるIT企業では「人材育成環境」のスコアが著しく低いとの調査結果が出ました。当初、人事部門は管理職の部下育成能力の不足が原因だと考えていましたが、管理職へインタビューを行ったところ、業務負荷が高く、育成に時間を割けないという実態が判明。この問題に対し、管理職業務内容の整理・改善を行った結果、翌年にはスコアが大幅に向上したという事例があります。
具体的には、書類作成・管理職同士の会議などで時間の使い方が非効率的になっている部分があったので、記載内容を簡便にしたり、会議の回数や時間を減らしたりするなどの取り組みを実施。結果として、部下と向き合う時間が2割以上増やせるようになったとのことです。
人的資本に関する取り組みで大事な2つの考え方
では、どのような点に注意して人的資本に関する取り組みに着手するのがよいのでしょうか。2つのポイントを紹介します。
部門単位で小さく始めてみる
全社的な大規模施策に取り組むことは理想ですが、それには多大な労力と時間が必要です。そのため、まずは着手しやすい部門単位での取り組みから始めることがおすすめです。
例えば、ある中堅企業ではエンゲージメント調査で「協力体制」のスコアが低いという結果が出ました。そこで部門単位でワークショップを開催し、各メンバーの専門性や役割分担を明示することで、相談しやすい環境づくりを実施。その結果、協力体制が構築され、エンゲージメントスコアも向上しました。
「1on1面談」など既存の取り組みを見直す
新しい施策を導入する必要がない場合もあります。
例えば、「1on1面談」の仕組みが形骸化している場合、それを改めて活性化させるだけでも効果が見込めるでしょう。既存の年間研修計画内で、課題に対応できる場合もあります。
このように、小さな工夫や既存リソースの活用からでも、エンゲージメント向上につながる可能性は十分にあるのです。あるいはエンゲージメントスコアの低い点に対して、以下の取り組みなどを起案・実行すると本気度が伝わり、エンゲージメントの向上は加速することでしょう。
- ライフスタイルに合わせた環境の提供(テレワーク・フレックスタイム制度など)
- 社内コミュニケーションツールの導入(社内SNS・ランチミーティングなど)
- 褒めるイベントの実施(表彰式など)
「人的資本に関する取り組み」の成功事例3選

エンゲージメント調査を正面から受け止めて、果敢に取り組んだ企業の事例を紹介します。
- ・サイボウズ
- 調査からわかったこと:価値観は多様化している
取り組み事例:自由な勤務形態(週3勤務、時短勤務、在宅・地方勤務など選択可能) - ・メルカリ
- 調査からわかったこと:心理的安全性の重要性
取り組み事例:パルスサーベイ(アンケート調査)で社員の状態を常に把握 - ・花王
- 調査からわかったこと:社員の内向き思考
取り組み事例:社内公募制度(自ら手を挙げて別部署に挑戦できる仕組み)
エンゲージメント向上は、一朝一夕で実現できるものではありません。まずは調査結果を正面から受け止め、「伸びしろ」として前向きに捉える姿勢が重要です。さらに、データを深掘りし、部門別・在籍期間別など個別施策に落とし込むプロセスこそ鍵となります。
まとめ
取り組みの姿勢と経過を開示し、改善を繰り返すことこそ、人的資本の重要性を感じている経営姿勢と言えるでしょう。
日本企業全体としてエンゲージメントは低い状況ですが、それだけ改善余地も大きいわけです。「愛着や誇り」を持つ社員を増やし、生産性向上や企業価値向上につなげていくためにも、一歩ずつ着実に取り組んでいきましょう。
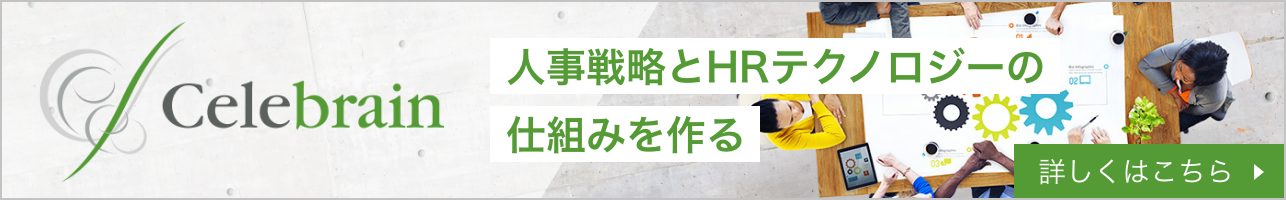





















コメントが送信されました。