読了目安:7分
昭和のマネジメントはなぜ問題? 令和の時代に合わせた発言方法
昭和なマネジメントとは、上司が「家長」のように部下の生活に深く関与し、長時間労働や精神論、飲みニケーションを重視するスタイルです。当時は終身雇用や年功序列が前提で、部下の自律性よりも組織の画一的な統制を優先し、変化への対応が遅れがちでした。今回は昭和なマネジメントについて考え、令和の時代に合わせた適切なマネジメントや発言方法を探ります。
「昭和」という言葉には、よい印象もある

昭和という言葉にはいい意味での郷愁を感じる人も多いと思います。昭和歌謡や、昭和の高度経済成長の勢いなど、元気があり、満たされていなかったけど希望があった。少子高齢化など閉塞感を抱える日本の現状と比較するとよりよく思えるのか、「あの頃はよかった」「できれば、戻りたい」と叫んでいる人をスナックでみかけたことがあります。
叫ぶまでいかなくても、よい印象を抱くのはその時代を生きた人だけでなく若い人からも聞く話です。SNSなどでは昭和レトロブームが広がっており、当時の歌謡曲や文化に共感するZ世代など、若い人々の間で人気を集めています。
昭和のマネジメントは長期的なメリットがあった
シニア世代にとっては嬉しい話ですが、昭和のマネジメントについては「勘弁して欲しい」との意見が大半。ここから当時のマネジメントを考えていきたいと思います。否定的な意見があったとしても、利点があったから行われていたのは間違いありません。
まず、当時は終身雇用を前提としていたので、企業は社員の長期的なキャリア形成に投資しやすく、専門的な知識やスキルを社内に蓄積できました。社員も会社への忠誠心や一体感を強く持ちやすく、組織全体の目標達成に向けた協力体制が築きやすいという側面がありました。また、年功序列のもとで、年齢や勤続年数によって序列が明確になるため、社内の人間関係の調和が保たれやすい面もあったでしょう。
昭和のマネジメントが徐々に排除されている理由

ところが時代が令和になると利点が弊害に変わっていきました。テクノロジーの進化により年齢と市場価値が必ずしも比例しなくなっています。20代でも即戦力として活躍する希少なエンジニアや、新しいビジネスを生み出す人材が増えています。その結果、年齢や勤続年数で評価される年功序列制度では、「不公平だ」と感じる人が増え、モチベーションの低下や離職につながるリスクが高まります。
同時に人材の同質化や組織の硬直化によって新しいアイデアや多様な価値観が生まれにくい状況になりがちです。それ以外にも多様な働き方やワークライフバランスの推進の弊害になるなど、時代の変化とともに不要な考え方に変わっていきました。当然ながら企業もその問題に気づき、昭和なマネジメントは排除する動きが進んでいます。
気をつけていても、昭和のマネジメントと思われる可能性
ところが、排除したつもりながら、若手社員からすれば昭和なマネジメントとみられていることが幾つもあるようです。具体的なケースを紹介していきます。
上司から「無理しなくてもいい」と言われたら、どんな気持ちになりますか? 肩の力が抜けて、楽になる人が大半かもしれません。でも、逆にモチベーションが下がる人もいます。
例えば、責任感が強く、仕事もできると評判の高いCさん。上司から「ちょっと厄介な仕事を誰かにお願いしたいのだが、できる人はいないか?」と、投げかけがありました。Cさんは「自分がやります」と手をあげ、前向きに仕事に取り組みました。ところが、頑張るCさんを見た上司からの一言は「無理しなくていい」。その言葉を聞いて、Cさんの気持ちはガクンと下がってしまいました。「大変な仕事を引き受けたのだから無理して当たり前。そんな言い方をするなら頼まないでほしい」と思ったわけです。つまり、同じ言葉を投げかけても相手の受け止め方は異なります。さらにいえば、相手が矛盾を感じた瞬間に、モチベーションの低下は避けられません。
昭和は矛盾も容認されていた時代
矛盾とは、前に言ったことと後に言ったこととが一致しないこと。一般に、理屈として二つの事柄のつじつまが合わないことを指します。そんな矛盾に気づかないのは時代遅れ=昭和な考え方なのかもしれません。
昭和では矛盾のある発言が多少は容認されていた気がします。具体的には会社の上司や、立場が上の人であれば、矛盾のある発言でも、許容されていました。「真意はどこにあるのか?」と周囲が意図をくみ取ろうとしてくれていたのです。でも、徐々に許されなくなり、部下から「矛盾していませんか?」と指摘される場面も増えました。その結果、こうしたタイプの上司は徐々に姿を消しています。
朝礼暮改な発言が周囲にマイナスの影響を与える

昭和のマネジメントはついには絶滅してしまったと言い切りたいところですが、まだまだ、職場で横行してます。
私が取材した会社では、社長がある週に「お客様からの要望には何でも応える姿勢を示してほしい」とメールを送信。その理由は感動した本に顧客第一主義と書かれていたから。
ところが翌々週には別のメールで「お客様の要望にすべて応えては商売にならない。できないことをきっぱり断る勇気を持ってほしい」と指示を出しました。断ることの重要性をうたった本を読んで共感したためのようです。現場の若手社員に話を聞いたところ「やる気なくなりますよね」と嘆く声がありました。随分とモチベーションが下がってしまったようです。いわゆる、朝令暮改な発言ですね。
どうして、そんな発言をしてしまうかと言えば、その時々で「よかれ」と感じているからですだけど、その発言を聞いた人が混乱することには気を留めていないのです。このままでは、周囲にマイナスの影響を与え、自分の印象も悪くしてしまうので、改善すべきです。
矛盾に気づくための2つの工夫
ならば、どうしたらいいのでしょうか? いくつか方法をご紹介します。
一つめは発言をする前に一呼吸置いて思考する癖をつけることです。矛盾に気づける可能性が高まります。
二つめは自分の発言と行動の理由を共に記録しておくことです。自分の行動と理由と一緒にメモしておくことで、同じような場面でどう対処すればいいのかわかります。
矛盾のある発言をなくしていくと、当然ながら一貫性のある発言をする人として評価されるようになります。そのことは、自分にとっても大きなプラスです。例えば、周囲からの信頼が高まる。発言の説得力が増す。さらには物事を極める力が身につくと言われています。昭和から令和の時代に合わせた発言を心がけたいですね。
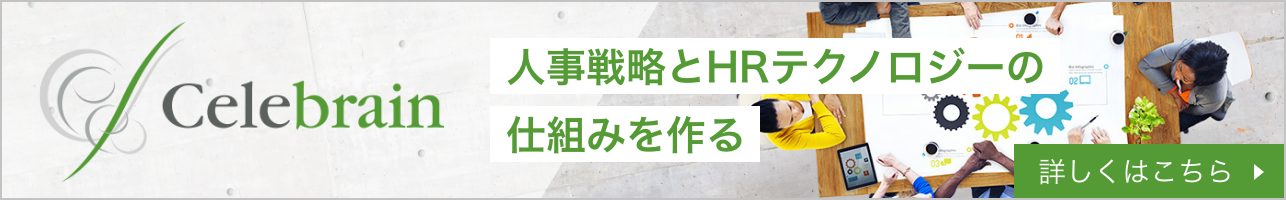






















コメントが送信されました。