読了目安:8分
村上春樹さんから学ぶ経営⑳ おじさんは石とだって話ができるじゃないか
五輪に関するネット上の匿名での投稿(すなわち本音)をみると高評価が多く、無事に終わって本当に良かったと思います。ゆくゆくは二つの五輪(オリンピックとパラリンピック)の統合と、差別をなくした上で「WeThe15」ではなく「WeThe100」(弱みが全くない人など存在しません)の実現を期待したいところです。
弱みの改善よりも強みの強化

二度目の引用となる

サヴァン症候群と呼ばれる方がいます。「一般的な基準」では知的ハンデをもちながら、特定分野で並外れた才能を持つ人々のことです。たとえば、街並みの航空写真を数秒見ただけでビル群のガラス一枚一枚まで寸分たがわぬ模写をできたり、数百年間ものカレンダーを全て記憶できたり、音楽を一度聞いただけでそらで完全に演奏できたりする―――といった驚異的な才能を見せる人のことです(注1)。映画にもなった『レインマン』はサヴァン症候群の物語です。
引用した文章では、石や動物と会話はできるけれど文字は読めないナカタさん。ありがちな物語でしたら、「勉強して文字が読めるようになって、皆でパーティーを開いて祝福、ところが、翌朝おきてみると動物の言葉が理解できなくなっていた」という結末でしょう。世界から特別な才が失われたことになってしまうのです。文字が読める人は世の中にいくらでもいますが、石と会話ができる人はナカタさんしかいないのです。
経営資源は機会に使え

ホシノちゃんは一味違います。動物や石と話ができる強みに焦点をあてるのです。弱みがない企業、人など存在しません。誰しも日々悩みます。学校でも「5」の教科をより良くするよりも「1」の教科を改善する指導がされるように、人間も企業も弱みがどうしても気になってしまいます。
しかし、弱みを改善しても「普通」になるだけで競争力にはなりえません。弱みを改善するよりも強みをさらに強くすることに時間を使う、もしくは逆転の発想で弱みを強みに変えるほうが有意義ではないかと思います。このことをかっこよく言えば、P・F・ドラッカー「経営資源は問題ではなく機会に使え」になります。
多次元を思える能力
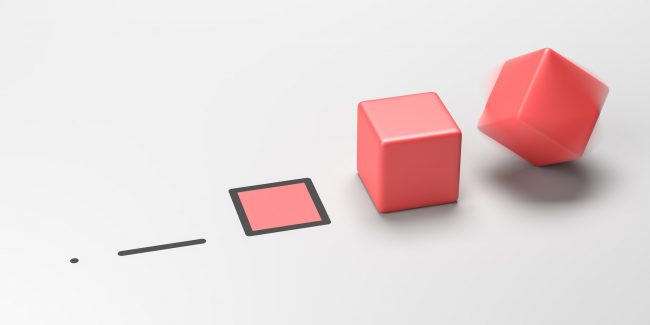
弱みは強みでもある華麗な事例があります。我々は空間3次元(もしくは、アインシュタインの洞察により「時空4次元」)の世界に住んでいます。3次元世界の住人である私たちは4次元世界を想像できません(4次元の絵を描けません)。一次元に住む生物が二次元を、二次元に住む生物が三次元の世界を説明できないのと同じことです。
しかし、驚くべきことに4次元を思い描くことができる人がいるのです(注2)。球体(野球のボールでもサッカーボールでもなんでも)の表面を、破ったり穴をあけたりすることなく裏と表をひっくり返すことができることを、天才数学者スメールが証明しました。そんなことを証明できること(そもそもそんなことを考えること)自体が凡人には理解不能ですが、証明したスメールもその工程を視覚的に思い描くことはできなかったのです。
それをやってみせたのはベルナール・モラン。盲目の天才数学者です。我々は3次元の世界を経験してしまっているがために、4次元を想像する力を持っていないのですが、既成概念に汚染されていないという強みを発揮した事例と言えるのではないでしょうか(ちなみに、ネットで「球面裏返し」と打ち込んでみると動画が見られます・・・が、実際の動画をみても理解できません)。
また、弱みが長所になることもあります。恐ろしい災禍をもたらしたサリドマイドは、その後、癌の薬として使用されています。サリドマイドは血管の育成を妨げるため、(成人と異なり、血管が新しく作られる)胎児に甚大な影響が出てしまったのですが、逆に、さかんに細胞分裂をし血管をつくるがん細胞だけを選択的に破壊することができるためです。
企業経営でも強みが重要
企業経営も同じではないでしょうか。ささやかですが最近面白い事例がありました。トマトを甘くするために水やりを減らすと、黒ずんだトマトになり破棄するしかなかったそうです(「尻腐れ」と呼ぶそうで、ハロウィーンのカボチャの赤黒版のような怖い見た目になり、おいしそうには見えません)。
悩んだ挙句思い切ってスター・ウォーズにちなんで「闇落ちとまと」という名前をつけたら手に取ってもらえるようになり、実は尻腐れのほうが甘いということが認知され、大ヒットになりました。黒ずんだトマトを無理に綺麗にしようする(弱みを改善する)よりもずっと洒落ています。
下位企業の弱みを強みに変える戦術

米国のレンタカーAvisも面白いです。1960年ころ、一位のHertzに大きく引き離され苦戦していた同社。その広告文がしゃれています(シリーズ広告で、以下はその一つの拙訳です)。
でも、それって朗報ではないですか?
だって、TVCMを打つのにいくらかかるかご存知ですか?
ナント15,000ドル。
15,000ドルには、高速道路、晴れ渡った空、クールな自動車、魅力的な女の子、おしゃれな音楽のための代金が含まれています。そしてもちろん、それらを放送するためのお金も必要ですよね。
残念ながらAVISにはそんなお金がありません。
私達は所詮業界二位なので。
私達が有するのは、十分な量の車と、お客様をお待たせしない十分なカウンター、そして、礼儀正しい従業員。
私たちは全てを持っています、TVCM以外は。
どうでしょうか?なかなか粋な戦術ではないでしょうか。弱み(規模)を受け入れ、強み(おもてなし)を際立たせる。このキャンペーンによりエイビスは黒字転換したそうです(注3)。
追随できない強み
弱みがない企業・人など存在しません。そして、弱みを改善しても普通になるだけ。
同時に、強みがない企業・人も存在しません。強みを誰も追随できないものにすること。
人においても企業においても大切なことと考えます。
[1] たとえば、D.A.トレッファート『なぜ彼らは天才的才能を示すのか』(草思社)。
[2] ジョージ・G.スピーロ『ポアンカレ予想―世紀の謎を掛けた数学者、解き明かした数学者 』(ハヤカワ文庫)等参照。ちなみに、最先端の理論物理学「超弦理論」によれば、宇宙は10次元でできている可能性があるそうです(例えば大栗博司氏『大栗先生の超弦理論入門』(ブルーバックス)。ドラえもんの世界ですね。
[3] 直近の3か月の業績は、売上高2371百万ドル、税前利益486百万ドルと立派な業績です。
▼村上春樹さんから学ぶ経営(シリーズ通してお読み下さい)
「村上春樹さんから学ぶ経営」シリーズ








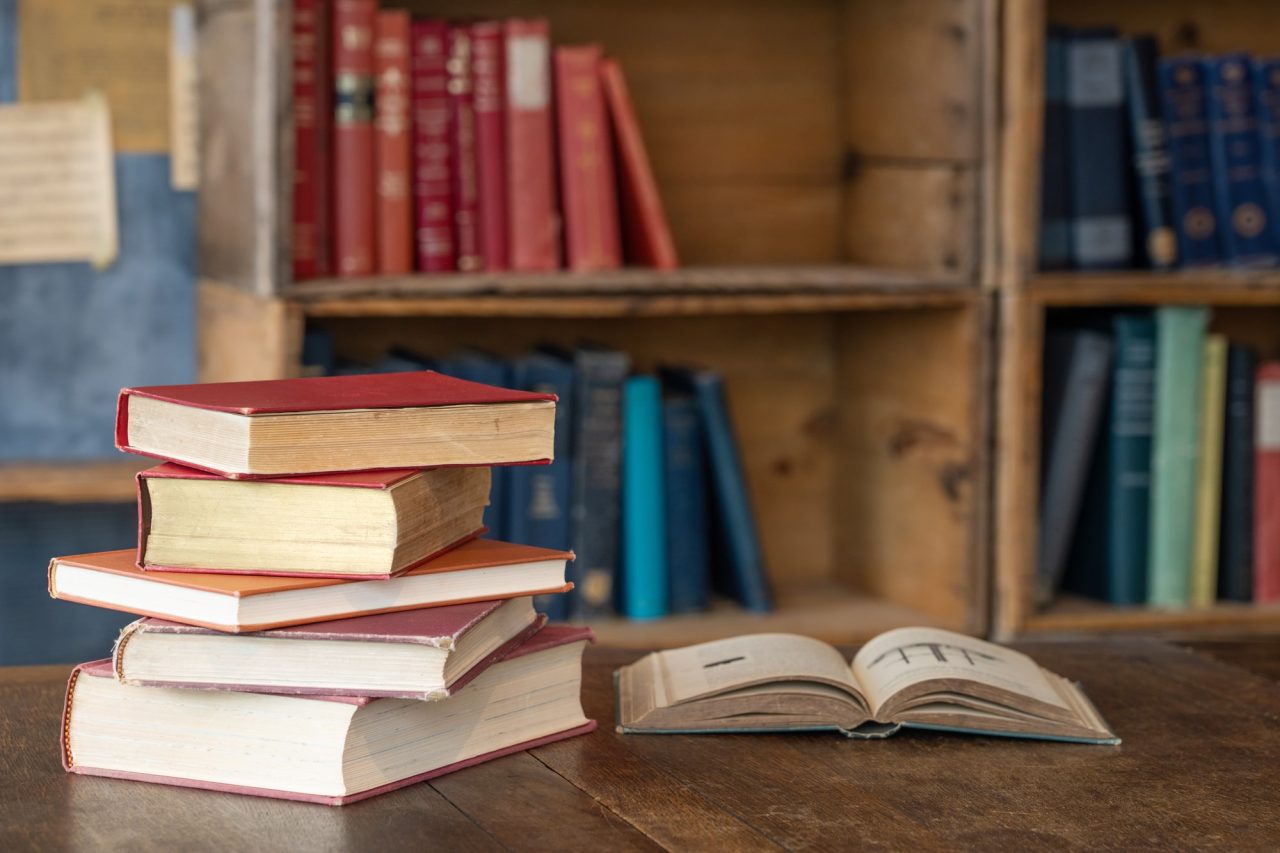












コメントが送信されました。