読了目安:9分
都心の空室率上昇 オフィス市場は大競争時代へ
東京都心部のオフィス空室率が、上昇している。新型コロナウイルスの影響で、オフィスの需要が減っている事に加え、東京から地方へ人口が流出している。2030年ごろまでに再開発や新しいビルの竣工が相次ぐことも影響し、オフィス市場は大競争時代を迎えている。
「需給均衡点」空室率5%を上回る
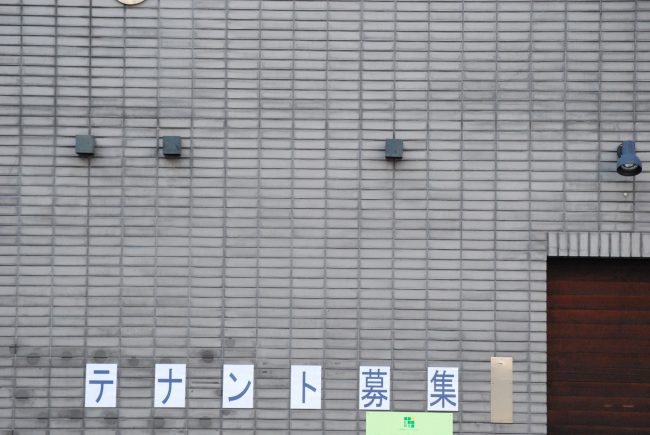
三鬼商事の調査によれば、東京の都心5区の2021年11月の空室率は6.35%で、1年前の2020年11月の4.33%から約2ポイント上昇した。一方、平均募集賃料は坪当り20,686円で、1年前の22,223円から6.9%下落した。
オフィス市場では空室率5%が「需給の均衡点」とされており、現在の空室率はそれを上回っている。
東京は転出超過のトレンドが続く

2020年の国勢調査によると、経済活動の主な担い手となる生産年齢人口(15~64歳)は約7,508万人で、ピークだった1995年の約8,716万人から13.9%減少した。とはいえ、日本全体の人口が減っても、地方から東京への人の流入が続けば東京のオフィス需要は安泰だった。
しかし、人口一極集中が続いていた東京は、2020年5月に初めて人口が転入超過から転出超過に転じ、それ以降も転出超過のトレンドが続いている。テレワークの拡大により東京から地方への移住が増えた結果と推測される。東京と地方の経済力の格差を考えると、東京からの人口流出が長期間続くとは思えないが、東京一極集中に歯止めがかかりつつあることも確かと思われる。
即ち、人口動態から見た東京のオフィス需要は頭打ちになりつつある。
古い中・小型ビルで空室率上昇
新型コロナウイルスの感染増加を機にもたらされた景気低迷、および在宅勤務の拡大を機に、一部の企業でオフィス床を縮小する動きがあること、等が空室率上昇の背景にある。ただしどのビルも同じペースで空室率が上昇している訳でもない。
好立地で築年数の浅い大型のハイグレードなビルを多く保有・管理する大手不動産会社の9月末の空室率は、三井不動産の首都圏オフィス(単体)が3.9%、三菱地所の丸の内が3.27%、住友不動産が5.6%で、いずれも市場平均より低めに推移している。
築後年数を重ねた古いビルや中・小型のビルで空室率が顕著に上昇していることがうかがえる。
コロナ前の計画が続々竣工

今後数年で見ると、供給圧力が強まる。
森ビルの推計によれば、大規模オフィスビルの供給量は、2021年の61万m2に対して、2022年は49万m2、2023年は145万m2,2024年は93万m2,2025年は120万m2と増加する。
コロナ前から始まった大規模プロジェクトの多くが、竣工を迎えるためだ。
今後の景気動向次第だが、2023年にかけて空室率は更に一段高いレベルにまで上昇する可能性も否定はできない。そうなれば、たとえハイグレードなビルであっても市況悪化の影響を受けざるを得ない。
供給は2030年頃まで高水準
2023年から2025年にかけてのみならず、2020年代後半も供給圧力は大きい。
というのも、この時期に日本橋一丁目中地区、芝浦一丁目プロジェクト、Torch Tower、八重洲二丁目中地区、内幸町一丁目街区等の延床面積300,000m2を超える大規模プロジェクトが続々と竣工するからだ。
また竣工時期は未定だが、森ビルが中心となって進める六本木五丁目プロジェクトも2030年前後に竣工する可能性がある。これらの大規模プロジェクトに加えて、昭和40年代から50年代にかけて建てられた築50年前後の当時の大型ビルの建替えが、この時期に少なからず竣工すると推定されるため、2020年代を通じて供給は高水準で推移すると予想される。
「オフィスは不要」になるわけではない

コロナ禍で在宅勤務を含むテレワークが急速に普及したのは周知の事実である。業種・業態や職種によって違いはあるものの、テレワークの導入によって業務に大きな中断や支障や不都合は出なかった企業は多い。そこで、今後、社員が集まって働くスペースとしてのオフィスは不要になるとの議論、即ち「オフィス不要論」が一部にみられた。
しかし、現実のビジネスでは、オフィス不要論の流れにはなっていない。
日本生産性本部の2021年7月の雇用者(自営業者等を除く)調査では、テレワーク(自宅での勤務、サテライトオフィス・テレワークセンター等の特定の施設での勤務、モバイルワークを含む)の実施率は 20.4%で、雇用者に占めるテレワーカーの割合は約2割であった。
一方「自宅での勤務で効率が上がったか」との質問に対して、「効率が上がった」「やや上がった」との回答は50.2%で、「効率は下がった」「やや下がった」との回答も49.4%あり、テレワークに対しては肯定的な見方ばかりではない。
直近1週間(営業日ベース)の週当たり出勤日数の質問に対しては、「3~4日」「5日以上」が57.6%で、コロナ禍が始まった初期の2020年5月の30.6%から増えており、この1年強でオフィスへの回帰が進んでいることがわかる。
社員の一体感を醸成したり、アイデア創出を促したりするためにも、リアルなコミュニケーションは重要だ。
本社オフィスや拠点オフィスの需要がなくなることはないと考えられる。
一方で働き方の多様化は進む

最近はテレワークの部屋を確保するために、より広い郊外の一軒家を購入する層が高水準で推移している。
イオンモールは10月に名古屋で商業施設とオフィスを一体化した複合商業施設をオープンしたが、今後首都圏の郊外で同様の事例が出る可能性が高い。
また大手デベロッパーは、通常のオフィスビルの供給に加えて、シェアオフィスやサテライトオフィスの供給も加速している。
JR東日本や東京メトロは、駅の構内にシェアオフィスを設置している。即ち、供給面からテレワークをサポートする動きが続いている。
このような動きに誘発されて、在宅勤務やサテライトオフィス/シェアオフィスでの勤務およびモバイルワークと拠点オフィスでの勤務を組み合わせた就業形態を採用する企業が今後も増える可能性が高い。
メタバースによるバーチャルオフィスが普及
更にテクノロジーの進化もテレワークをサポートする。Maasや自動運転車が実用化してくると、移動時間そのものが、まとまった仕事の時間としてカウントされ得る潜在性がある。また仮想空間上にバーチャルオフィスを構築し、社員は在宅のままバーチャルオフィスに毎朝“出勤”するシステムを取り入れている会社も既にある。メタバース(オンライン上の共有型仮想空間)の普及によりこの流れは加速する可能性が高い。
オフィス市場は大競争時代

少子高齢化が進んだ日本は、移民を受け入れない限り、人口動態的には需要は伸びない。
一方で働き方の多様化は今後も進み、テレワークが従来型のオフィスワークをじわじわと侵食する。ただし本社機能や拠点機能を持つオフィスのニーズがなくなるわけではない。
そのように需要が推移する一方で、供給は少なくとも今後10年高水準で推移する。それらが意味するところは、市場全体の空室率は、バブル的な景気浮揚による例外的な時期を除けば、需給の均衡点といわれる5%を超えて推移するだろうということだ。
その結果、ビルオーナーの間で、現状を上回る熾烈なテナントの奪い合いが行われる可能性が高い。その中でも、変化するテナントの設備ニーズやESG-SDGsのニーズに対応できるビルは、立地するエリアの平均と比べて高い入居率かつ高い賃料を実現できるだろう。
大競争時代は始まったばかり
資金力やブランド力や大きな事業規模を持つビルオーナーはこのような「勝ち組」のビルを多く保有する傾向がある。一方、築年数を経た古いビル、特に中・小型のビルの中には、値段を下げてもテナントが埋まらないビルも増えるだろう。埋まらなければ用途転換するか、売却するか。それらの見込みもなければ長期間空き家として放置される例も出てこよう。大競争時代はまだ始まったばかりである。























コメントが送信されました。