読了目安:8分
モチベーションを左右する「運の捉え方」〜損な役回りを得な機会に変える思考法〜
仕事で「自分は運が悪い」と考え、モチベーションが低迷している人は少なくありません。しかし、一見「損な役回り」に見える状況でも、視点を変えることで新たな可能性が見えてきます。モチベーション向上につながる思考法を探ります。
運の捉え方で分かれる成功と低迷

これまで「自分は運がいい」から「仕事で成功できた」と周囲に発信し、キャリアアップを実現した人物に、たくさん遭遇してきました。
運の良さを実感する人
例えば、広告会社で営業職をしていたSさんは、急に誘われた食事会で隣の席に座った人物から大きな仕事を受注するなど、偶然の産物の積み重ねで高い評価を得て、営業部長に最短で昇進しました。「実力ではなく、環境に恵まれただけ」と運の良さを周囲に語ることが多いのですが、その運が尽きることなく、高い評価を得る状態が継続しています。
周囲からすれば、うらやましい存在となっています。当然ながらモチベーション高く、仕事に邁進(まいしん)をしているので、この状況は続いていくのでしょう。周囲から見ていても、うらやましい状況と言えます。
不運を嘆く人
一方で逆の状況に陥って、モチベーションの低いまま、仕事が低迷している人もいます。そうした人は「自分は運が悪い」とか「損な役回りばかり」とネガティブなことを周囲に発信する傾向があります。
低迷から脱却したいなら、前向きに発想を変えて「運がいい」と思い込めばいい気がしますが、当事者からすれば、簡単なことではないのでしょう。これまでの様々な経験でモチベーションが下がる場面にたくさん遭遇してきたことで、その状態を当たり前と考えてしまうのです。
確かに確率的に考えて、損な役回りになり意欲が下がる状態に置かれてきた人はいるかもしれません。例えば、食品メーカーのマーケティング担当をしているPさんは自分が担当すると問題に遭遇することが頻繁に起き、TVの報道番組で「申し訳ございませんでした」と謝る場面にも数回登場するくらいの境遇でした。
逆に自分から引き継いだ仕事が急激に好調になり、自分よりも役職で上の立場に出世した同僚もいるようです。自分はおみくじでも凶ばかり。占いをすれば厳しい境遇にさらされる運命と示される。
だから自分の仕事による成果に期待していないのです。「モチベーションが変に上がっても、それ以上に下がる状況に遭遇する可能性が高いから、平均的に低い状態をキープしています」と不思議な信念を教えてくれました。
モチベーション曲線から見る実態
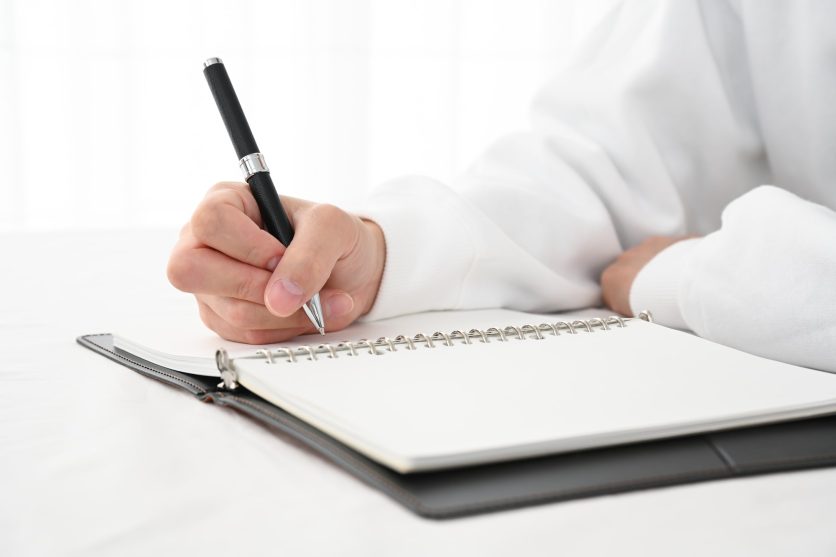
このような人はモチベーションを上げるすべはないのでしょうか? 対策を考えてみたいと思います。
こうしたモチベーションの上げ下げを理解するための手法として、モチベーション曲線の作成があります。モチベーションの源泉を知るために行う、自己分析の手法の一つで、横軸を期間、縦軸を(モチベーションの)高さとして、上下を書いてみることです。例えば、社会人1年目のモチベーション曲線を書いてみるとして、
4月:入社間もないため緊張しながらも、期待からモチベーションが高い状況
5月初旬:研修が始まると、うまくいかないことが発生して大幅にダウン
5月下旬:現場に配属されて、素敵な先輩が教育担当になりダウンから上昇
6月:取引先で失礼な対応をして、上司から指導が入り、どん底にダウン
ずっとモチベーションが高い人はやはりいません。それなりに下がった時期を経験するものです。ところが下がりっぱなしの人には時折遭遇します。
なぜ下がりっぱなしかと尋ねると、前述のような不遇さを語ってくれます。ある意味でモチベーションが下がった状態を甘んじて受け入れるための口実とも言えます。
おそらく、相対的には不遇な人はいるかもしれません。でも、それなりに仕事で成果を出したいのであれば甘んじているだけでなく、モチベーションが上がる要因を思い出し、上げる努力をしてほしいと願います。
「損な役回り」の再定義
さらに言えば、損な役回りと思っている状況が周囲から見れば、そうではない。仕事の成果につながる可能性を秘めていることはよくあります。
例えば、前述のような謝る場面が多かった時期を経験したことでクレーム処理の専門性が高いと思われて、その分野では社内で高い評価を得る存在になっていました。
ただ、その評価の意義を本人は深く認識していません。本人は、損な役回りなのでと嘆くのですが、周囲からすれば、それなりの恵まれた状況と思われていました。
同じように損な役回りと思ってモチベーションを下げ続けている人は、その状況でも自分が得ていることがないのか? その得たことで次につながる機会を得られるのではないか? 振り返って、探っていただきたいと思います。
例えば、プロスポーツ選手でレギュラーになれずに、ずっと控え選手でしたという人がいます。しかし、控え選手だった経験から早期にリタイアする選手の気持ちを理解してセカンドキャリアのビジネスを立ち上げて成功を収めています。
要するに、自分が損だと思ってきた役割や境遇、体験などを見直して、得したことに置き換えられないか? 考えてみてください。例えば、周囲からの光が当たらなかった仕事でも成果を出せていれば、注目度が低かったことでノビノビと仕事に取り組む(得した)機会になったと考えることもできます。
バーベキューから見える適性

少々脱線しますがバーベキューをしたときに手をあげて行った仕事により適性がわかるといいます。ですので、新入社員研修でバーベキューに行き、新入社員だけで自由に行わせて、先輩社員たちは見学するだけです。
そうすると、ご飯を炊く人、肉を焼く人、皿を洗う人など、どの仕事を希望するか、そして仕事ぶりはどうか?で営業職に向いている、あるいは管理部門で業務改善の仕事を任せてみようなどと各自の配属先の判断基準が見えてくるようです。
ちなみに周囲からは損な役回りに見える皿洗いとかごみ捨てなどに手をあげてしっかりやり切れる人は、その役割をこなせることを見越して、適任と思える配属先が決められたりします。
「損」を「得」に転換して広がるキャリアの可能性
つまり、損な役回りに見えていても、それほど損ではない。各持ち場として期待される仕事が与えられるのです。周りから見たら損な役回りの人は、一番ではないかもしれないけれど、実はそれなりにその役回りを選ぶ人を非常に高く評価する傾向があるんです。
それはバーベキューから見えることだけではなく、世の中の仕事で損な役回りに見えるが、実はそれなりに得な役回りというのが結構あります。
先ほどのクレーム対応の仕事や、社内で中核と呼べない事業部門の仕事など、損のように見えます。しかし、高い専門性を磨けたり、小さな組織の場合は経営と近く仕事ができたりといった、得なこともたくさんあったりします。
できれば、損だと思い込んでいる仕事や役割を得なものに置き換えられないか? 試してみてください。得に思えてくると、モチベーションが下がる頻度が随分と減るはずです。
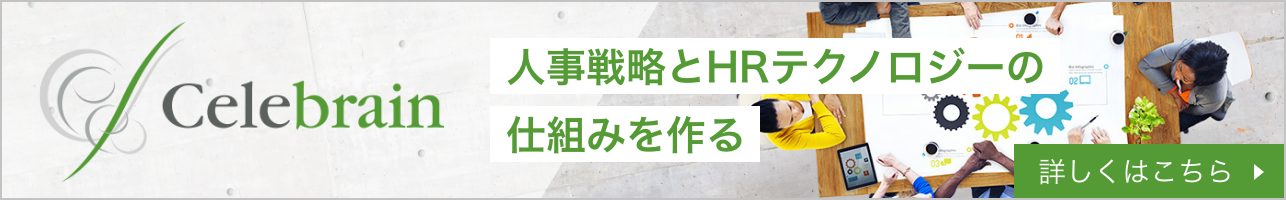







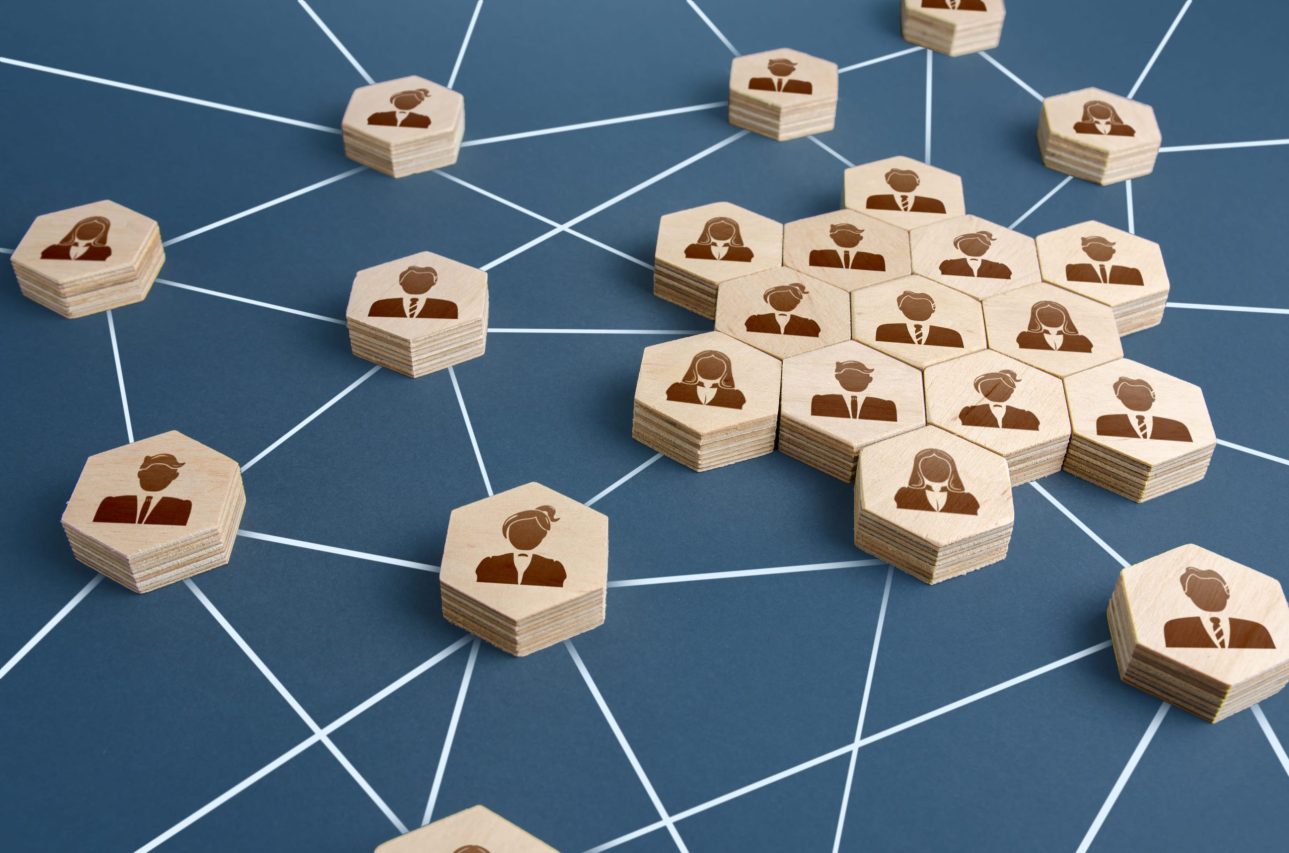













コメントが送信されました。