読了目安:15分
「危機時のリーダー」は今の日本に存在するか。ヒトラーやスターリンと渡り合った“フィンランドの英雄”に学ぶリーダー像
ロシアによるウクライナ侵攻が長期化し、混迷を深めている昨今。今から約100年前の20世紀前半においても、ロシアの前身であるソ連から度々侵攻を受けた国家がある。フィンランドだ。フィンランドはソ連の侵攻を受けながらも、国家として独立を維持した。そのとき、フィンランドを率いていたのがカール・グスタフ・エミール・マンネルヘイム将軍である。本稿では、マンネルヘイム将軍から学ぶべき危機時におけるリーダーシップについて紹介する。
はじめに

急激な円安傾向の継続やロシアのウクライナ侵攻に伴う化石燃料や食品原料の高騰など、経営環境の変化が激しくなっている現在、企業経営の難易度は一層上がっているのではないだろうか。
こうした状況を乗り切るためには、経営者が自社のビジネスモデルを見つめ直し、大胆な企業変革を行うことが必要である。そのときに必要な経営者のリーダーシップは、平時の経営のリーダーシップではなく、危機時の経営のリーダーシップだろう。
平時と危機時の経営のリーダーシップは、それぞれで大きく異なる。平時の経営では、あらかじめ事業戦略と計画を策定し、それを実行する「着実な実行力」が経営者としての重要な資質となる。
一方、危機時の経営では、自社を取り巻く経営環境の変化が著しいため、一度策定した事業戦略と計画は臨機応変に変更していく必要がある。さらに場合によっては大胆なビジネスモデルの変革を実施する必要もある。このため、「思考の柔軟性と大胆な決断力」、そして「社内の人間を説得するためのコミュニケーション力」が経営者としての重要な資質となる。
危機時のリーダーシップを学ぶ上で、第一次世界大戦から第二次世界大戦にわたって、フィンランドという小国の独立性を守ったカール・グスタフ・エミール・マンネルヘイム将軍(以下、「マンネルヘイム」という)は、ソ連とドイツという二大強国の狭間で苦闘しながら、厳しい環境を乗り切った偉大な人物である。彼のリーダーシップは企業経営においても参考となる部分が多いため、彼のリーダーシップがどのように培われたのか、植村英一(1992)著『グスタフ・マンネルヘイム : フィンランドの“白い将軍』(荒地出版社)で記された内容を交えて、生い立ちから振り返りたい。
生い立ち~軍人生活

マンネルヘイムは1867年6月、事業家で劇作家でもあった父と、事業家の娘だった母との間で生まれ、7歳のときにヘルシンキの学校へ進学した。しかし父の経営する会社が破産すると両親は離婚。マンネルヘイムは叔父のアルベルトに育てられた。
その後、叔父の家計の悪化とマンネルヘイムの学校での素行の問題から、マンネルヘイムは軍人教育を行うフィンランド幼年学校に入れられることになったが、素行の問題から再度学校の退学を余儀なくされた。このため、マンネルヘイムはフィンランド軍への入隊が望めなくなり、ロシア帝国陸軍への入隊を目指すこととなった。そして20歳となる1887年、ロシアのニコラエフ騎兵学校に入学することができた。
同校の卒業後は、黒龍連隊に2年間入隊した後、目標としていたシュバリエ―ル近衛騎兵連隊に入隊。本格的に始まったロシア帝国陸軍の軍人生活で、マンネルヘイムは長らく近衛騎兵として勤務した。日露戦争(1904年)、第一次世界大戦(1914)には前線で参加し、指揮官として活躍。マンネルヘイムは、比較的順調に昇進し、1917年には中将に進級、3個の師団で構成する第六騎兵軍団長にまで昇任したという。
祖国フィンランドの独立戦争

1917年2月のロシア革命(2月革命)以降、ロシアではウラジーミル・レーニンが率いるボリシュヴィキ(左派団体)が勢力を伸ばし、8カ月後の1917年10月、再びのロシア革命(10月革命)でソビエト連邦社会主義共和国を樹立した。
これに対し、マンネルヘイムの祖国であるフィンランドはロシア革命後の1917年12月に独立を宣言。ソ連も一旦はこれを承認した。
このときマンネルヘイムは、武力革命を行ったボリシュヴィキの危険性を熟知していたようで、フィンランドが今後ソ連に脅かされる危険性を予見し、独立と同時にフィンランドに帰国。マンネルヘイムはフィンランドのために尽力する道を選んだのだった。
独立をめぐり、フィンランドでは政府軍と親ソ連・共産党系の赤衛軍の間で激しい内線が勃発。マンネルヘイムは、帰国後すぐに政府軍の軍事委員会のメンバーとなり、その後総司令官に就任した。
しかし政府軍と言っても、それまでロシア帝国の支配下にあったフィンランド政府には、熟練された兵士は整備された兵器はない。
マンネルヘイムにとって、その強化が急務だった。マンネルヘイムは、ドイツから帰国した軍人を政府軍人の教官に任命し、兵士調達のための徴兵法の制定を推進。また、ドイツから兵器の調達も実施した。加えて、マンネルヘイムは、首都機能を一時的にヘルシンキから農耕地区の小都市ヴァーサに移転することを決めた。この施策で、ソ連軍の支援を受けた赤衛軍がヘルシンキを占領した後も、政府軍は体制を十分に整えて反抗の機会を伺うことができたため、最終的な政府軍の勝利に繋がったとされている。
マンネルヘイムのポリシーと挫折

マンネルヘイムは、
「大国に依存したり、その政策に便乗したりすることは、それに背を向け、あるいは刃向かうことと同じくらい危険である」
というポリシーを持っていたという。
小国であるフィンランドが生きる道は、大国と適切な関係性を維持しつつ、独立性を保つことであり、大国に依存体質となると小国が生き残る道はないということを経験則から学んでいたのである。
ところが、そうしたマンネルヘイムのポリシーに反して、政府軍はドイツ軍に援軍を要請。政府軍が勝利した後も、盲目的に親ドイツ政策を採用していたため、マンネルヘイムは、しばらくの間フィンランドを離れていたという。
その後、第一次世界大戦でドイツが連合国に対し降伏をする状況に至り、急きょフィンランド政府から呼び戻されたマンネルヘイムはフィンランドの執政(首相)に着任した。
マンネルヘイムは、敗戦国ドイツと協調したフィンランドに対する汚名返上を図るべく、イギリスやフランスを訪問して外交を精力的に行うとともに、共和国としての憲法制定にも尽力した。
だが、その後に開催された大統領選挙では敗退しマンネルヘイムは、その後約13年間にわたりフィンランド政府の表舞台から消え、引退生活を送ることになった。
公職への復帰~冬戦争

1930年代になると、スターリン率いるソ連とヒトラー率いるナチス・ドイツが勃興し、その両国間に挟まれたフィンランドは、その独立性を維持していくのに困難な状況を迎えていた。
そうした中、フィンランドのスヴィンヒューヴド大統領は1932年、65歳になったマンネルヘイムを軍事委員会の委員長として招き、陸軍元帥という称号を与えた。
マンネルヘイムは、委員長就任後にしばしば海外へ出かけて大国の軍事技術の実態を観察し、その近代的戦術法の動向を把握することに時間を割いた。その上で、フィンランドが置かれている難しい国際情勢を分析し、小国としてフィンランドの採るべき戦略は武装中立であることを改めて認識したという。
大国であるソ連やドイツのいずれかに依存する戦略は、安心感を与えるものであるが、小国に抜き差しならぬ束縛と義務を負わざるを得ない危険を生じさせるものだったからこそ、マンネルヘイムは中立を維持することが重要と考えた。一方で、「自らを守る事のできない国を、一体どこの国が守ってくれるのか」という考え方から、小国であっても自国の武装強化は不可欠と考えたのだった。
ドイツが1939年9月にポーランドの侵攻を開始すると英仏がドイツに宣戦布告し、第二次世界大戦が勃発した。次いで、スターリン率いるソ連が、バルト三国(エストニア・ラトヴィア、リトアニア)に相互軍事援助条約を強制するとともに、同国などの領地内に軍事基地の設置を進め、フィンランドに対しても、領土の交換要求を行った。
ソ連とフィンランドは、1932年に不可侵条約を締結していたものの、ナチス・ドイツの侵攻を恐れるスターリンは、ソ連第二の都市レニングラード(現在のサンクトペテルブルグ)に近接しているフィンランドの軍事的価値が高いとみて、再三にわたり国境の移動を要求した。
これに対しマンネルヘイムは、圧倒的な軍事力を有するソ連との紛争を回避するために、相当程度の譲歩をすべきという立場でフィンランド政府に進言。しかし、不可侵条約の存在に安心を寄せていたフィンランド政府はこの要求を拒絶した。
案の定1939年11月、ソ連は、フィンランドとの不可侵条約を破棄し、フィンランドの侵攻を開始し冬戦争が始まった。マンネルヘイムは、この時すでに72歳になっていたが、やむなくフィンランド国軍の総司令官の就任を受諾し、全軍に対し、以下のように呼びかけた。
「指揮官の自信は成功の第一条件である。諸君は私を知っている。私はあらゆる階級の諸君が死に至るまで任務を果たすことを知っている。私の自信はそれである」
「我々は我々の家族のために、我々の信念のために、そして我々の祖国のために戦おうではないか」
フィンランド国防軍は、軍人数や武器の数量でソ連に太刀打ちはできなかった一方で、訓練された優秀な将校と兵士が存在し、フィンランドの特殊な地形と気候に応じたゲリラ戦法である「モッチ戦法」を得意としていた。
そのため、冬戦争の序盤戦は優勢に進めることができたが、マンネルヘイムはフィンランドの戦力が絶対的にソ連に劣っていることを冷静に認識し、また、連合国軍の英仏の軍事支援も当てにならないと判断した。そこで、ソ連に善戦している状況のうちに、ソ連との講和を進める道を模索するのが得策と考えた。その結果、フィンランドは1940年3月に、厳しい条件ながら国としての独立性を維持できる内容でソ連との間で講和条約を締結することができたのだった。
継続戦争~第六代大統領就任

冬戦争が講和によって終結したものの、ソ連はその後もフィンランドに対し追加的な要求を突き付けていた。依然としてソ連の脅威が続くなかでフィンランドは次第にドイツ軍との協調路線に傾斜した。
ナチス・ドイツはソ連への侵攻を企図しており、その点でフィンランドに同盟関係を求めてきたのだった。
そのときマンネルヘイムは、あくまでフィンランドの独立性の維持のためにソ連と戦うのであって、ソ連の侵攻を目的とした協調ではないことを明言。このため、フィンランドはドイツとの間で、一切の協定書や文書の作成を正式に行うことなく、軍事的な協調路線を事実上遂行したのである。
この方針は、マンネルヘイム自らの「小国は大国の政策に依存したり便乗したりしてはならない」という信条に反するものと認識していたが、ソ連に対抗するための、「最低限必要な防御手段としての協調」ということで、難しい国家の舵取りを行っていた。
ドイツのソ連侵攻後、ソ連はフィンランド領内に駐留していたドイツ軍とフィンランドの施設や都市の爆撃を開始。マンネルヘイムは当初、ソ連が早期に崩壊するのではないかと考えていたが、形勢は真逆となり、ソ連に侵攻したドイツ軍は1942年から徐々に撤退を余儀なくされていった。この状況から、マンネルヘイムは、政策を180度転換し、早期に継続戦争から離脱する道を模索することを決断した。
ドイツとの協調路線の責任者であったフィンランドのリチ大統領が1944年に退陣すると、新たにマンネルヘイムが第6代大統領に就任。戦争からの離脱交渉役という難しい役割を担うこととなった。
マンネルヘイムはソ連との休戦交渉の結果、ソ連からはドイツ軍の撤退を始めとした厳しい条件を突き付けられたもののそれを応諾し、フィンランドは1944年9月にソ連との間で休戦協定を締結した。
マンネルヘイムのリーダー像

マンネルヘイムが発揮した「危機時のリーダーとしての資質」は、以下のようなものだったと考えている。
①大局観と先見性
マンネルヘイムは、小国フィンランドの実力と、ソ連やドイツといった大国の実力との力関係を把握しつつ、ベストなタイミングで和平交渉を行うことで、フィンランドの議会制民主主義の体制による自由と独立を守ることに成功した。
そのとき、
「小国は大国の政策に依存したり便乗したりしてはならない」
「自らを守る事のできない国を、一体どこの国が守ってくれるのか」
という大局的な考え方を念頭に、判断を行っていた。
②情報収集力、決断力(慎重な検討と大胆な決断)、柔軟性
独立戦争のときにヘルシンキを一旦撤退し、小都市ヴァーサに首都機能を移転させ形勢を立て直すというマンネルヘイムの決断は、極めて大胆かつ冷静な判断であり、それが功を奏して政府軍に勝利をもたらした。
また、ソ連とドイツという大国間に挟まれた小国のフィンランドが、ドイツとの協調路線からソ連との講和を図りドイツと敵対するという戦略に転換させた大胆かつ柔軟な判断は、フィンランドの独立を守るための究極の判断であった。なお、マンネルヘイムはこれらの大胆な判断を行う前に、その優れた情報収集力と情勢分析力を駆使して、慎重な検討を行っていたという。
③コミュニケーション力
マンネルヘイムは、フィンランド国軍の総司令官就任の際、すべての軍人に対し、
「指揮官の自信は成功の第一条件である。諸君は私を知っている。私はあらゆる階級の諸君が死に至るまで任務を果たすことを知っている。私の自信はそれである」
「我々は我々の家族のために、我々の信念のために、そして我々の祖国のために戦おうではないか」
と呼びかけ、鼓舞したという。危機時においては、部下の力を最大限発揮させるためにも、一体感と使命感を醸成するようなコミュニケーション力がリーダーに必要となるだろう。
最後に
マンネルヘイムは、大国に挟まれた小国フィンランドの特性を理解しながら、難しい舵取りを行った英雄である。
日本もフィンランドと似ている点がある。しかし、今の日本にマンネルヘイムのような「危機時のリーダー」はいるだろうか。
国家だけではなく、企業でも、将来に備えて大胆な事業変革を担えるような「危機時のリーダー」の育成を行うことが重要といえそうだ。
ジャレド・ダイアモンド(2019) 『危機と人類(上)』 日本経済新聞社
植村英一(1992) 『グスタフ・マンネルヘイム : フィンランドの“白い将軍』 荒地出版社







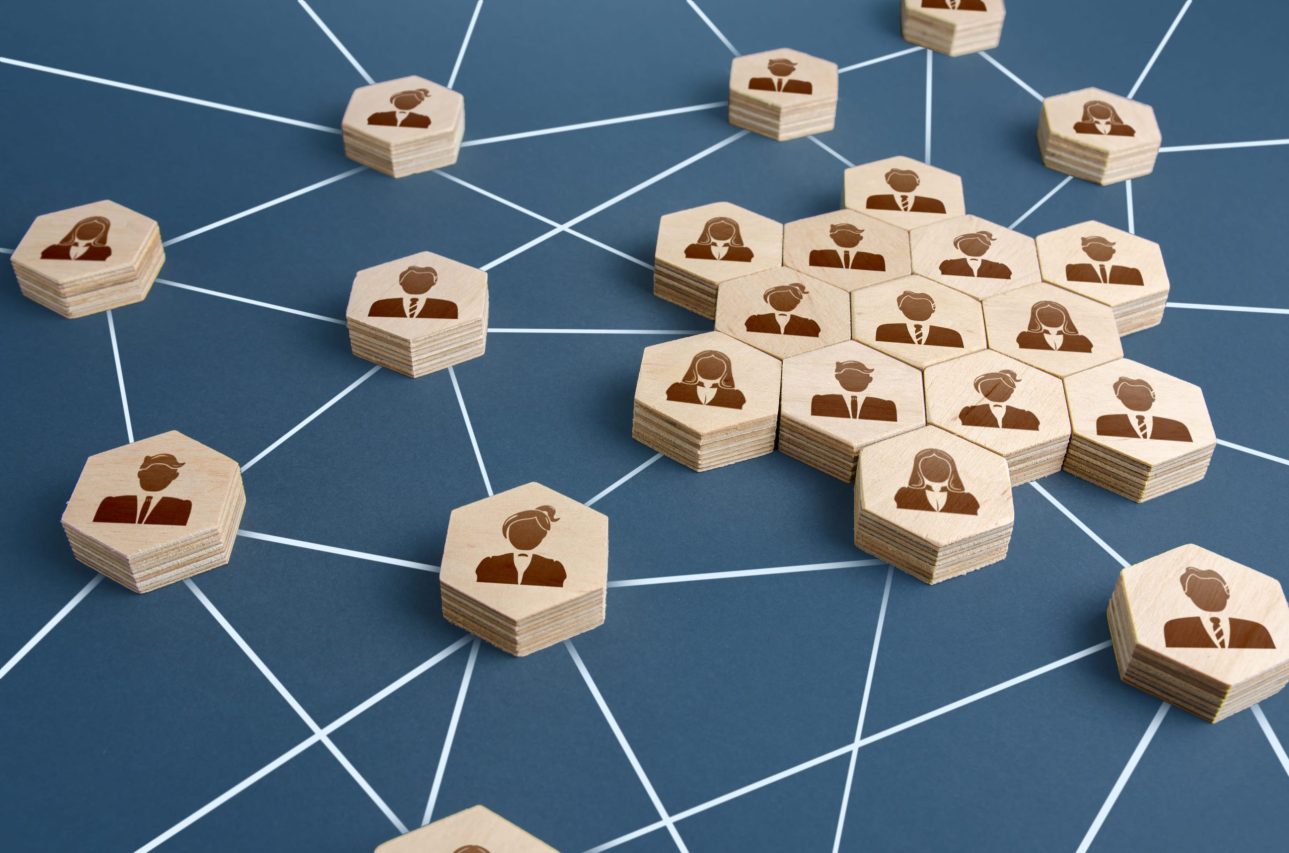















コメントが送信されました。