読了目安:8分
リーダーに求められる「良い朝令暮改」とは
「朝令暮改」という言葉には、意見や指示が頻繁に変わることで周囲を混乱させるというネガティブな印象がつきまといます。しかし現代のビジネスでは、柔軟性や迅速な対応力としてポジティブに捉える動きも見られます。リーダーには、単なる「朝令暮改」ではなく、説明責任を伴った「良い朝令暮改」が求められています。
本記事では、「朝令暮改」の歴史的背景や職場での実例を交えながら、ネガティブな側面とポジティブな活用法の違いを探り、リーダーに必要な改善策を考えます。
朝令暮改の語源

朝令暮改は、意見や指示がすぐに変わって振り回される、あてにならないという、ネガティブな意味合いを含む言葉です。方針や指示が「朝令暮改」だと、「昨日はこう言っていたから、その通りに動いたのに…」と、周囲の人が戸惑ったり、モチベーションが下がる原因にもなったりします。このため、基本的には朝令暮改は悪い意味でとらえられてきました。
語源は中国の歴史書である『漢書』です。紀元前180年の頃、当時、文帝という皇帝が前漢を治めていましたが、定める法律は、頻繁に変わるため、民は振り回され、苦しみました。
そこで、文帝の部下が皇帝を戒めますが、戒める時に使った言葉が「朝令暮改」の由来と言われています。
朝令暮改のネガティブな側面
朝令暮改について、悪い意味として職場で指摘されることがあります。悪い意味の朝礼暮改を紹介します。
責任感が高くて、仕事ができると評判も高いSさん。上司は会議で「無理だと思う仕事にも果敢に挑戦する意欲を大事にしてほしい」と発言していたのを聞いています。
そんなタイミングに「ちょっと厄介な仕事を誰かにお願いしたいのだが、できる奴はいないか?」と、本社の広報から依頼が舞い込みました。Sさんは「自分がやります」と手をあげ、前向きに仕事に取り組みました。
ところが、頑張るSさんを見た上司からの一言は「無理しなくていい」。その言葉を聞いて、Sさんの気持ちはガクンと下がってしまいました。翌週の会議で上司は「自分のキャパシティーを超えるような仕事を受けることは控えて欲しい」と発言しました。
人事部から時間管理で残業が多いなどの指摘があって、方針を180度変えたことが背景であるようです。Sさんのモチベーションは大きく下がり、元気のない姿を見受けるようになりました。
朝令暮改で矛盾をはらんでいると相手が感じれば、モチベーションが下がるのは当たり前です。矛盾とは、一般的に、理屈として二つの事柄のつじつまが合わないことを指します。
朝令暮改の矛盾に気づかないのは時代遅れ?

そのような矛盾に気づかないのは時代遅れ=昭和な存在なのかもしれません。昭和には矛盾のある朝令暮改といえる発言が多少は容認されていた気がします。具体的には会社の上司や立場が上であれば、矛盾のある発言でも、許容され、真意はどこにあるのか?周囲が深く考えてくれました。
ところが、最近は「矛盾していませんか?」と突き上げられるようになり、存在は減少傾向です。ついには絶滅してしまったと言い切りたいところですが、職場で跋扈していたりします。
取材した会社の社長が「お客様からの要望には何でも応える姿勢を示してほしい」とメールを配信しました。その理由は感動した本に顧客第一主義と書かれていたからだといいます。
ところが翌々週には「お客様の要望にすべて応えては商売にならない。できないことをきっぱり断る勇気を持ってほしい」とメールを配信しました。断ることの重要性を謳った本を読んで共感したようでした。
現場の若手社員に話を聞いたところ、「やる気がなくなりますよね」と嘆く声が上がりました。彼らのモチベーションはかなり下がっているようでした。いわゆる「朝令暮改」のような発言が原因の一つだと思われます。
なぜそのような発言をしてしまうのかといえば、その時々で「これが良い」と感じて行動しているからでしょう。しかし、そうした発言を聞いた人たちが混乱する可能性については、あまり意識されていないようです。このままでは、周囲にマイナスの影響を与えるだけでなく、自分自身の印象も悪くなってしまうため、改善する必要があります。
ならば、どうしたらいいのでしょうか?幾つか方法をご紹介します。一つめは、発言をする前に思考する癖をつけることです。思考する習慣をつけることで、矛盾に気づく可能性が高まります。
二つめは自分の発言を行動の理由と共に記録することです。自分がした行動を理由と一緒にメモしておくことで、同じような場面などでどう対処すればいいのかわかります。
矛盾のある発言をなくしていくと、当然ながら一貫性のある発言する人との評価に変わっていきます。そのことは、自分にとってプラスのことがあるはずです。例えば、周囲からの信頼性が高まり、発言の説得力が増します。また、極める力が身につくと言われています。極める力とは、経験を重ねることで、課題解決の能力が高まり、どのような状況でも成果が出せるということ。周囲からみて大いに頼れる存在と言えます。昭和から令和へと移り変わりました。時代に沿った発言を心がけたいですね。
経営者が朝令暮改を推奨する理由
さて、前述したように時代の変化で朝礼暮改を肯定する動きも出てきています。ビジネスにおいてよく使われる、臨機応変と同義語として捉えてのことなのでしょう。例えば、あるニュースが舞い込んだときに、すぐに対応してルールの変更を行った上司がいたとします。
昨日とは違ったルールを急に掲げた時には「言っていることが、コロコロ変わる」と批判的な声があがるかもしれませんが、柔軟で、スピーディーな判断と称賛を得る可能性の方が高いと思います。
ちなみに活躍中の経営者に限り、朝令暮改の傾向があると言われています。代表的な経営者として思い出したのは元セブン&アイ・ホールディングスの会長兼CEOの鈴木敏文氏です。自身の経験に基づき、こうあるべきという仕事に対する姿勢のなかで、朝令暮改を推奨している発言をされています。
鈴木氏に限らず、同様の意見で仕事に取り組んでいる経営者は多いのではないでしょうか?知人のベンチャー企業経営者も「朝令暮改こそ重要な発想」と断言されていました。
、どうして朝令暮改を推奨するのでしょうか?それは、視座の高さに起因していると思われます。視座とは、物事を見る姿勢や立場のことです。この視座が高いと広く世の中の動きをみようとして、変化を刻々と観察します。結果として「右だ」と言っていたのが、前言を撤回して「左だ」と大転換してしまったりします。
こうした発言と、その発言に戸惑う社員の様子を何回も見てきました。ただ、この前言撤回が会社の成功を導く瞬間にも遭遇すると、戸惑いながらも「ついていこう!」と納得し、朝令暮改は正しいこととされている会社は、少なくないように感じます。こう考えると、朝令暮改が推奨される場面があるのかもしれません。
ただ、1つ大事にしていただきたいことがあります。それは、変わったことを速やかに伝え、周知徹底し、可能な限り、変わった理由や背景を説明することです。このようなことを実践する人が、いい意味での朝令暮改の使い手と言えるでしょう。
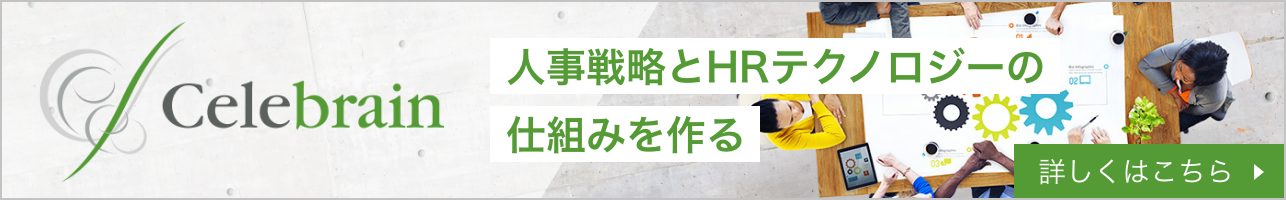





















コメントが送信されました。