読了目安:5分
人類の英知⑫ (4/4) 人類史上最も美しい理論
相対性理論の最終回となります。アインシュタインの相対性理論は、人類史上最も美しい理論と称されます。宇宙の本質を解き明かし、科学の枠組みを変えました。本記事では、相対性理論の意義と、知られざるエピソードを振り返ります。
▼人類の英知(シリーズ通してお読み下さい)
「人類の英知」シリーズ
相対性理論を理解できなかった?ノーベル財団

アインシュタイン博士はノーベル賞を受賞していますが、その対象は相対性理論ではありません。
1905年はアインシュタインにとって(人類にとってと言っても過言ではないと私は思います)奇跡の年と呼ばれます。いずれもノーベル賞受賞に値する三つの理論――特殊相対性理論、光電効果、ブラウン運動――を発表したためです。さらには、1915年〜1916年にかけて一般相対性理論を発表しました。
ノーベル財団は50年たつと選考記録を公開することになっており、アインシュタインは1910年から1922年までほとんどの年でノーベル物理学賞の候補になっていました。世界の物理学者から多くの推薦が寄せられていたのです。しかも、1919年には、アインシュタインの一般相対性理論を裏付ける観測がなされ(皆既日食を利用して、光が屈折することを証明した歴史的な観測)、新聞の1面を華々しく飾り、博士は世界的に時の人となっていました。
ノーベル財団は1921年のノーベル物理学賞は該当なしとしていましたが、1922年になって、1921年のノーベル賞をアインシュタインに授与すると発表しました。しかし、受賞対象は特殊相対性理論でも一般相対性理論でもなく、光電効果でした。ノーベル財団は相対性理論を信じられなかったが、アインシュタインに何もしないわけにはいかない……と判断したのかもしれません。
博士はノーベル財団に不満であったのでしょう。ノーベル賞受賞講演では、博士は光電効果ではなく相対性理論について話をしたのです。光電効果も画期的な理論ですが、やはり相対論にはかないません。
とはいえ、ノーベル財団を責めるのは酷かもしれません。それほど画期的であったということですし、万が一間違った理論に賞を贈ってしまっては取り返しのつかないことになりますから(実際、長いノーベル賞の歴史のなかで、そのようなことがあります)。
アインシュタイン「人生最大の失敗」

本連載の前回で書いたように、アインシュタインは、自身が創った方程式に「宇宙項」と呼ばれる項目を足しました。自身の方程式は宇宙が動的であることを示していたのですが、アインシュタインは宇宙が動的であるはずがないと考え、静的になるように恣意的(しいてき)に手を加えてしまったのです。
博士は宇宙項を足してしまったことを人生最大の誤りであったと嘆いています。それはそうでしょう、『宇宙項』を加えなければ宇宙が膨張しているという世紀の発見までも博士の発見になったのですから!
常識に挑戦し続けることの困難さ
一般相対性理論をいち早く理解した天才物理学者エディントンは、のちに、インドが生んだ天才チャンドラセカールがブラックホールの存在を予言したときに完全に否定しました。
アインシュタインは、自身もその成熟に貢献しながら量子力学に強く抵抗しました。
過去の本連載においては、天才数学者クロネッカーが奇才数学者カントールの無限理論を糾弾したことを紹介しました。
独創的な理論を生み出した天才が次の独創には反発する。常に独創的であることは(もしかしたら経営者においても、常に優秀であることは)難しいことなのかもしれません。
まとめ
さて、これまで特殊および一般相対性理論についてみてきました。
特殊相対性理論は、
- 法則の相対性(慣性系のみ)、光速の不変性の二つの公理が基礎
- 時間と空間を統一、エネルギーと物質を統一
一般相対性理論は、
- 法則の相対性(慣性系、非慣性系問わず)、等価原理(重力と加速は同じ)の二つの公理が基礎
- エネルギーと時空を統一
そして、100年超かけて、ありとあらゆる実験においてその正しさが確かめられてきました。
すなわち、相対性理論は、宇宙を表現する壮大な理論であると同時に、優れた理論の条件――より少ない公理に基づきより多くのことを説明し、そして反証に耐える――を満たす点においても称賛される理論と言えます。







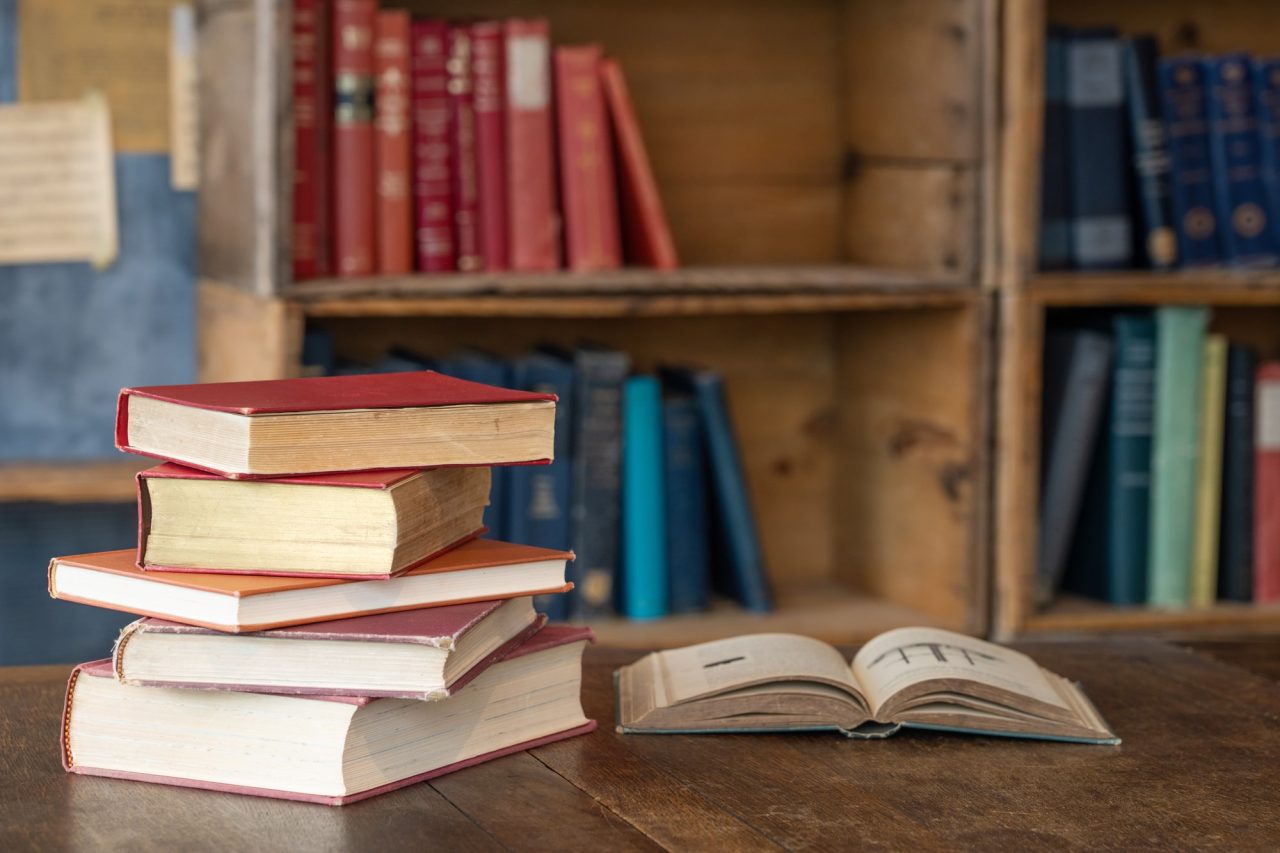













コメントが送信されました。