読了目安:6分
中長期の成長を実現する役員報酬制度設計に必要な視点と戦略
経営環境が急速に変化する今、役員報酬制度の見直しが多くの企業で急務となっています。市場のグローバル化に加え、法改正などよって、コーポレートガバナンスの要件も高度化しており、従来の報酬設計では経営課題の解決が十分に図れないケースが目立っているのが現状です。
経営責任や成果への対価をどのように報酬体系へ落とし込むべきか、自社の持続的成長と人材確保の観点からも、制度再構築への関心が高まっています。役員報酬制度を適切に設計するために、外部のコンサルティング企業の専門知識を活用する企業が増加しています。
役員報酬制度と従業員向け人事制度との違い

役員報酬は、取締役や監査役などの役員が、その責任や役割を果たすことへの対価として支払われるものです。
社員から役員に昇格するケースも多く、一部の企業では従業員と同じような基準で報酬を決めていることがあります。しかし、役員にはより大きな責任が求められ、雇用が保障されているわけではありません。
そもそも、成果に対する報酬の考え方も従業員とは異なって当然です。
役員報酬制度について、通常の社員向け人事制度との違いはどこにあるのでしょうか?
役員報酬は、会社法や税法上の取り扱いが社員の給与とは異なるため、法務・税務的な観点でも設計上の留意点が異なります。
また、役員の報酬は業績や企業価値とより連動した報酬体系とすることが求められており、経営戦略上の目標達成や投資家を含むステークホルダー全体との利益共有といった、より大きな視点での設計と運用が必要になってくる点が、社員向けの人事制度と大きく違います。
特に、外部株主がいる企業や株式公開をしている、または株式公開を目指す企業については、ステークホルダーとの利益共有を意識した報酬設計は必須と言っても過言ではないでしょう。
具体的には、月次の固定報酬、業績連動金銭報酬、自社株式や新株予約権を用いた株式報酬それぞれの額やバランスをどう考え、報酬総額の適切な水準を設定するのか、また、業績連動報酬や株式報酬はどのような支給条件を設けるのか。これらを経営戦略上の目標達成へのインセンティブ付けやステークホルダー全体との利益共有といった視点で十分な検討を行う必要があります。
日本企業に多い「代表取締役に委ねられる」役員報酬決定
では、日本企業における役員報酬・株式報酬はどのような水準・環境にあるのでしょうか? 日本企業の役員報酬は、欧米諸国に比べて低い水準にあると言われており、政府や東京証券取引所はこの点を問題視しています。グローバルで優秀な経営者を獲得・維持できない企業が多いということであり、ひいては日本企業全体の競争力低下にもつながると捉えているからです。
そのため、2016、2017年度に役員報酬に関する法改正が行われており、譲渡制限付株式と言われる現物株式を報酬として支給する制度の法的論点が明確化されたほか、業績連動報酬として損金算入が可能となる要件が緩和拡大されるなど、特にインセンティブ報酬の導入がしやすくなっています。また、東京証券取引所もコーポレートガバナンス・コード(CGC)において、役員報酬として業績連動報酬や株式報酬の導入検討を求めています。
その一方で、この機に乗じた根拠のない役員報酬の増額、いわゆるお手盛りで報酬額を決定することには警戒感を示しており、役員報酬の決定プロセスについて、報酬委員会の設置を含めた、社外役員その他外部の視点を取り入れた報酬設計を行うことが求められるようになってきました。
結果としてお手盛りでない状況にするため外部の専門家を活用する企業が急増しています。
これまで日本の企業では、役員報酬額の決定が代表取締役の判断に委ねられていることが多く、体系を定期的に見直す企業は少数でした。前年の報酬額を基準に、業績に応じて金額を増減させるケースが多かったのです。
インセンティブ設計とデータ活用で実施する定期的な報酬制度見直し

しかし、人材・報酬を取り巻く環境マーケットが大きく変化する昨今、このような報酬体系と運用では、優秀な経営人材を外部から獲得することは困難となり、また自社の優秀な役員が流出するリスクも高まってしまいます。
元々いた役員の報酬水準とはかけ離れた金額で新たな役員を迎え入れるといった対応もあり得ますが、場当たり的な対応を重ねた結果、役員間での不和や反発 ハレーションを引き起こすといったリスクも当然生じます。
そのため、報酬相場マーケットのデータをインプットした上で、自社の経営を任せるに足る人材を維持し、適切なインセンティブ付けをするためには、報酬の水準や構成、その詳細な内容をどう定めるべきか、制度として設計をして定期的にアップデートしていく動きになりつつあります。
役員報酬制度の構築に欠かせない外部専門家の知見
最後に役員報酬設計でよく起こる問題点について紹介します。よく起こりがちなのは、これまでの報酬水準にとらわれすぎるという点です。当然今までの報酬から大きく変動するとなると、下がる場合は生活給的な観点で困る方もいますし、上がる場合は企業のP/Lへの影響を懸念するといったこともあるでしょう。
もちろん設計の際にはそういった点を考慮すべきであり、場合によっては段階的に報酬額を変化させるような経過措置的な仕組みを取り入れることもあります。ただ、今の報酬水準に強くこだわりすぎてしまうと、制度を改定する意義が失われてしまいます。
そのため、中長期的に企業価値を伸ばすには、どういった報酬体系であるべきか、という視点をぶれない軸として持ち、短期的な影響を許容範囲にとどめるための仕組みも必要に応じて検討するといったスタンスが必要になります。こうした問題の対処を内部だけで行うのは大変。やはり、外部の専門家を活用して問題が起きないようにしていきましょう。
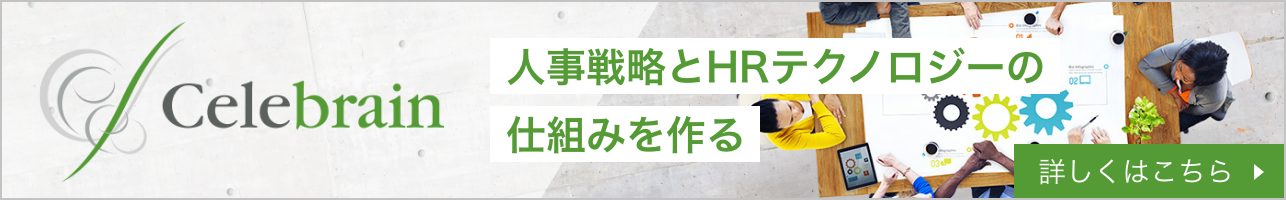







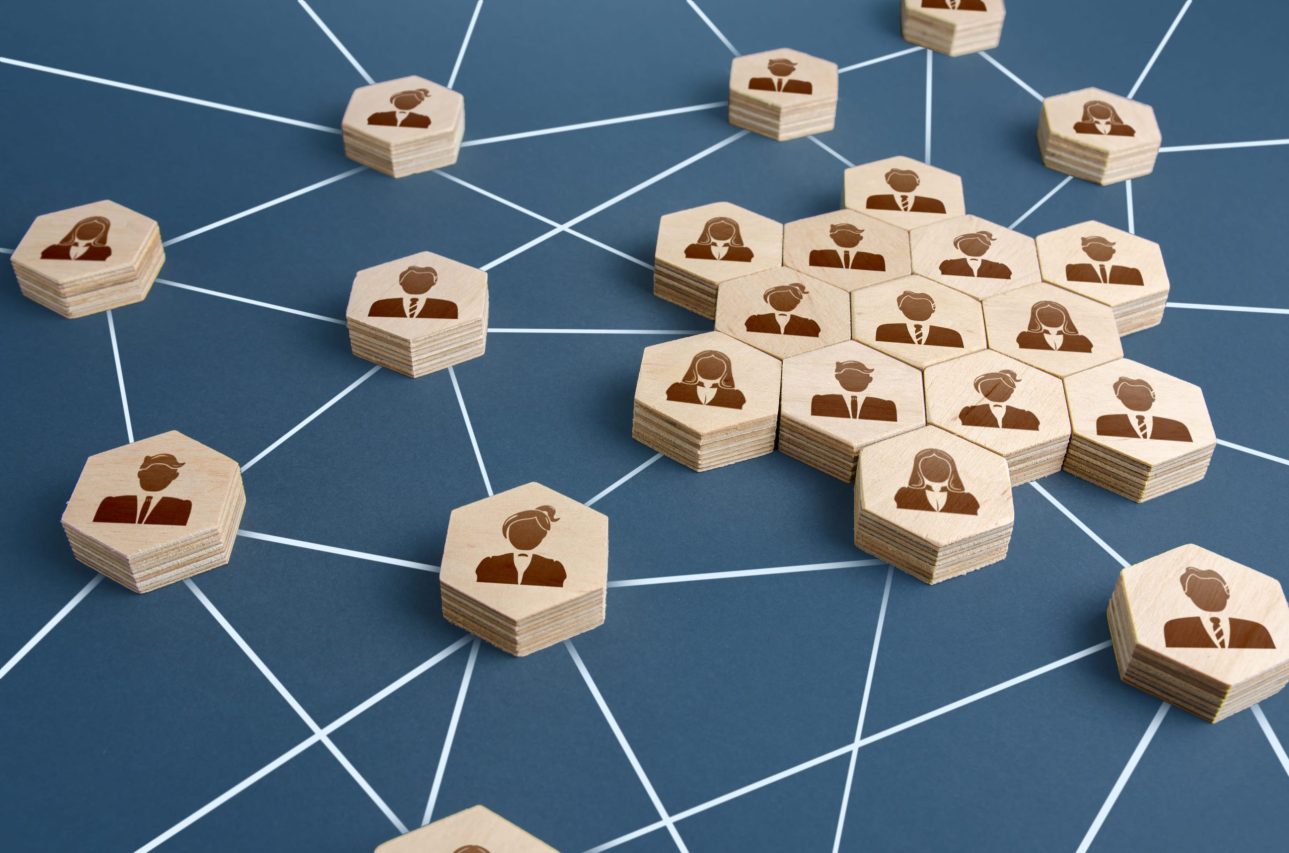













コメントが送信されました。