読了目安:8分
人類の英知⑦~特殊相対性理論「道は星に聞く」
雑誌TIMEは、1999年12月31日号において、アインシュタインを「20世紀の人 person of the century」に選出しました(*) 。20世紀を生きた人間は100億人程度でしょうか。100億人から選出された一人。すごいことです。21世紀の人は誰になることでしょう。アインシュタインを超える人は今のところいないように思いますが、あと76年、スゴイ人が出るでしょうか。
さて、人類が創った3大理論――最も反常識的な特殊相対性理論、最も美しい一般相対性理論、最も神秘的な量子力学――を紹介していきたいと思います(学校で体系的に学んだことはなく、一般書の読みあさりによるものに過ぎず、厳密なものではありません)。
第1回は特殊相対性理論です。先日の日本経済新聞「交遊抄」には、AGC平井良典社長は学生時代、相対性理論に憧れて学者を目指したとありました。
▼人類の英知(シリーズ通してお読み下さい)
「人類の英知」シリーズ
道は星に聞く

学生時代、地下鉄に乗った時に見た広告に驚いたことをよく覚えています。
「道は星に聞く」
カーナビゲーションシステムの広告でした。すごいなあ、と思いました。地上約2万㎞に打ち上げられた衛星がリアルタイムで地上の車の場所を把握し、道案内ができる。そんなことが本当にできるのだろうかと思いました。それから三十余年。現在では、精度数メートルのカーナビゲーションが手のひらのスマートフォンに標準搭載されています。これは驚くべきことです。
カーナビゲーションは極めて多くの技術の結晶で、イアン・スチュアートの良書『世界を支えるすごい数学-CGから気候変動まで-』によれば、カーナビには少なくとも七つの数学の知見が使われているとありました。
- 衛星を軌道に乗せるための計算
- 三つ(理想的には四つ)の衛星が常に見えている軌道の計算
- 衛星までの距離の計算
- 三角法と軌道データによる現在地の認識
- 運動による時間の遅れの補正(=特殊相対性理論)
- 重力による時間の遅れの補正(=一般相対性理論)
- 最適ルートの探索(=巡回セールスマン問題)
この七つのなかで、相対性理論がなかりせばどうなるでしょうか?
時間は速く動けば動くほどゆっくり進みます(特殊相対性理論)。衛星は4km/秒の速度で飛んでいるため、1日に7マイクロ秒遅くなります。一方、時間は重力が強いほどゆっくり進みます(一般相対性理論)。衛星が受ける重力は地上の重力よりも弱いため、1日に45マイクロ秒進みます。
この二つを差し引きすると1日に38マイクロ秒、すなわち0.000038秒進みます。
大したことないじゃないかと思われるかもしれませんが、衛星と地上がやり取りをするのに使う光の速度は30万㎞/秒ですので、1日に12㎞もずれてしまうことになり、海に落ちてしまうのです。そう、特殊相対性理論、一般相対性理論なくしてはカーナビは実現できないのです。
この偉大な理論がどのようにして生まれたのか、これから数回に分けて書いていきます。
相対性理論の始まり ~ アインシュタイン少年の疑問

アインシュタインは16歳の時に、「光が光を追いかけたらどう見えるだろうか?」との疑問を持ちました。言い換えるとこうなります。鏡を手にして光の速度で移動したら自分の姿が見えるだろうか?……私たちが鏡で自分の姿を見られるのは、光が自分にあたり反射する→鏡にあたり反射する→自分の網膜に達するからです。
しかし、鏡をもった自分が光の速度で動いてしまうと、自分の姿にあたり鏡に向かって進む光が鏡に届かない、すなわち、自分の姿が鏡に映らなくなる、そんな不思議なことがありうるだろうかと悩んだのです。
通常、速度は相対的です。高速道路で自分の車が100km/時で走っていて、隣の車も100㎞/時で走っていれば、隣の車は止まって見えます。逆に、100km/時どうしですれ違うと、隣の車は200km/時で走っているように見えます。誰しも日常的に体験することです。
音も同じです。音は空気を媒体として進み、その速度は300m/秒程度です。救急車が自分にむかってくると速度が速くなり=波長が短くなり=音が高く聞こえ、遠ざかると速度が遅くなり=波長が長くなり=音が低く聞こえます。いわゆるドップラー効果です。
同じように、光も、空間を満たしている何か(「エーテル」と名付けられていました)を媒体として進み、その速度は音速同様に変化すると考えられていました。
マイケルソン・モーリーの歴史的実験
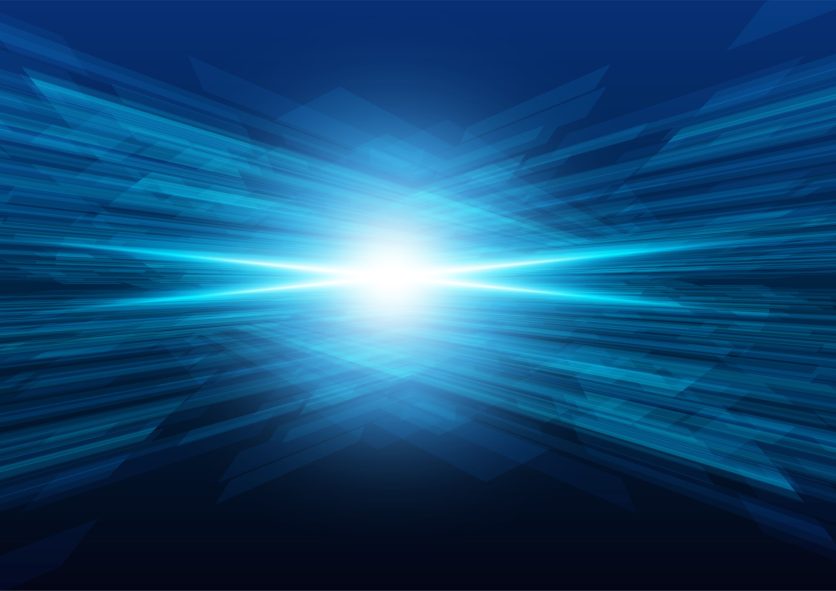
光速を知ることは人類の長年の願望で、多くの実験が行われました。素朴なものは、ランプを持った人間が離れて立ち、そのランプを点灯・消灯させ、光速を測ろうという実験でした。もちろん、それではとても計測不可能です。
実質的に初めて光速を計測したと言えるのはフィゾーです。高速回転させた歯車の溝をシャッターにするという独創的な実験で3.13×108m/秒と推定しており、1849年としては驚異的な結果と言えます。
そして、光の本質に迫る実験がマイケルソン・モーリーの実験です。地球は30km/秒という信じられない速度で太陽に対して公転をしています(太陽系も回転しているので、より大きな視点でみれば、さらに高速で動いているとも言えます)。
光が音と同じように何かを媒体としているのであれば、公転と同じ方向・逆方向・垂直方向の光速は異なるはずで、マイケルソンとモーリーは、公転方向と垂直方向の光速を厳密に計測する実験を行いました。
しかし、この2方向の光速に違いが見つからなかったのです。その解釈として、計測精度が足りないからだ、物質が縮んだのだ、などと意見が挙がりました。
しかし、アインシュタインは違いました。ならば、その事実を受けいれるべきではないか、光速は何も影響されない一定の速さを持つのではないか。光が光を追いかけてもやはり光速で進むのではないか。光の速さは絶対であり、時間や空間が相対的なのだ、と逆転の発想をしたのです。
次回以降、この逆転の発想がどのようにして驚愕の理論につながったのか――時間はなぜ遅れるのか、空間はなぜ縮むのか――、そして、アインシュタインはなぜ涙を流したのか、について書きます。
*20世紀の100人――「政治家」、「芸能・芸術」、「起業家」、「思想家」、「象徴」の五つの範疇からそれぞれ20人――選出されています。一例として、政治家(ネルソン・マンデラ、モーハンダース・ガンジー、ヒトラー、毛沢東)、芸能・芸術(ビートルズ、チャーリー・チャプリン、ボブ・ディラン)、起業家(盛田昭夫さん!、ウォルト・ディズニー、ビル・ゲイツ)、思想家(アルバート・アインシュタイン、クルト・ゲーデル、エンリコ・フェルミ)、象徴(チェ・ゲバラ、マザー・テレサ、ヘレン・ケラー)。
参考文献(今回と次回)
『相対性理論-時間と空間,そして重力の常識を変えた革命的大理論-』 ニュートンムック
ブライアン・グリーン 『宇宙を織りなすもの――時間と空間の正体』 草思社
イアン・スチュアート 『世界を支えるすごい数学-CGから気候変動まで-』 河出書房新社
松原隆彦 『図解宇宙のかたち-「大規模構造」を読む-』 光文社
松原隆彦 『宇宙とは何か』 SB新書
松原隆彦 『宇宙はどうして始まったのか』 光文社
松原隆彦 監修/深澤伊吹 著『相対性理論-図解苦手を“おもしろい”に変える!。大人になってからもう一度受けたい授業-』 朝日新聞出版
福江純 『100歳になった相対性理論-アインシュタインの宇宙遺産-』 講談社
福江純 『「超」入門相対性理論-アインシュタインは何を考えたのか-』 講談社
福江純『よくわかる相対性理論(ゼロからのサイエンス)』 日本実業出版社
真貝寿明『現代物理学が描く宇宙論』 共立出版
真貝寿明 『ブラックホール・膨張宇宙・重力波 一般相対性理論の100年と展開』 光文社
菅野礼司/市瀬和義 著『相対性理論-天才・アインシュタインは何を考えていたのか?-』 PHP研究所








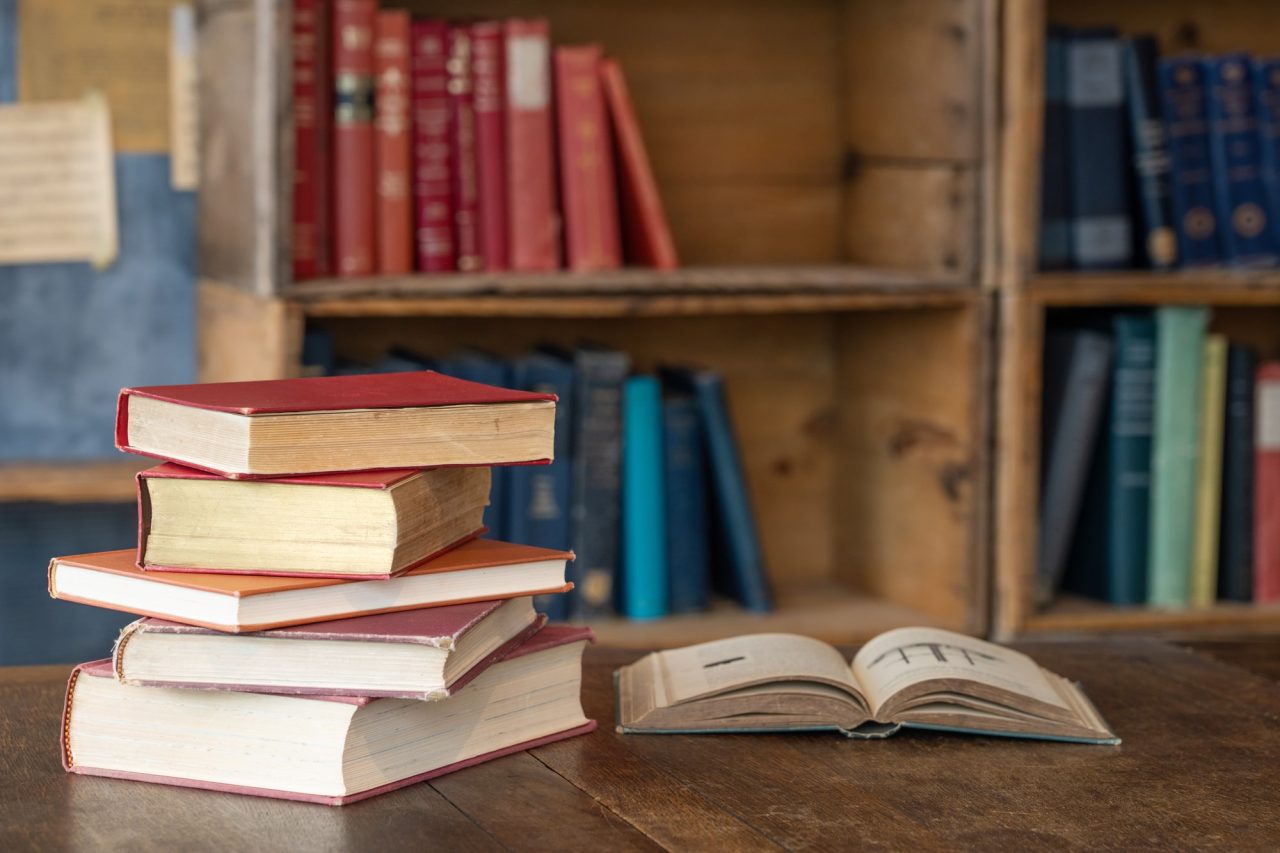












コメントが送信されました。