読了目安:13分
レピュテーションマネジメントとは? 企業の評判を守る重要性や具体的な手法について解説
システム障害や食品への異物混入、粉飾決算といった企業の不祥事は度々発生し、社会から注目を浴びることになります。いかに優れた事業戦略を推進したとしても、企業の評判が失墜すれば売上や株価への影響は免れないでしょう。つまり、企業にとっては外部からの目を気にしながら事業活動を続けなければなりません。そこで、評判を管理する手法である「レピュテーションマネジメント」に注目してみましょう。当記事では、レピュテーションマネジメントの基本的な知識や近年より高まる重要性、「攻め」と「守り」の2種類に分けた具体的な手法や事例などについて解説します。
レピュテーションマネジメント(評判管理)とは?管理の対象についても
レピュテーションマネジメント(reputation management:評判管理)とは、文字通り評判を管理して企業の社会的信頼やブランドイメージを維持・向上させる活動です。
レピュテーションマネジメントがカバーするのは、広告や広報活動などの通常のコミュニケーションに加え、突発的に起こる不祥事や風評被害も含まれます。
誰からの評判を管理するのか
企業の周囲には多くのステークホルダーが存在し、評判のほとんどはそのステークホルダーに委ねられます。
レピュテーションマネジメントにおいて特に注意するべきステークホルダーは下記の通りです。
- 企業の社会的信頼やブランドイメージに関心の強い社員
- 製品やサービスの品質に安心・安全を望む消費者と取引先
- CSRを望む個人・団体や地域社会
- 発言力のあるインフルエンサー
- 株主や機関投資家
主に評判は外からの目によって決まりますが、企業としても内側から積極的に介入して、自社が望む評判を構築する必要があります。
さらに、ステークホルダーごとに企業に望むものが違えば効果的な対応の仕方も違うため、アプローチは柔軟に変えなければならないでしょう。
レピュテーションマネジメントはなぜ必要なのか?
企業の評判は、株価や売上に影響を与える可能性があります。製品不具合やシステム障害の多い企業に対し、消費や投資などの行動に抵抗を感じる人は少なからずいるでしょう。
とくに近年ではインターネットやスマートフォンが普及し、誰もがSNSで情報を発信している時代です。レピュテーションマネジメントの重要性はより高まっています。以前の情報発信者はマスメディアが中心でしたが、今では情報の取り扱いに関して専門的な知識のない人でも、多くの人に向けて情報が発信できるようになりました。
つまり、情報の真偽が確かめられる前に、事実にそぐわない風評被害が瞬く間に広まってしまうリスク(レピュテーションリスク)が増加しているのです。
こうしたリスクに速やかに対応できなければ、いわゆる「炎上」を免れるのは難しいでしょう。評判は良くも悪くも非常に強い影響力を持つため、レピュテーションマネジメントはどの企業においても急務の課題といえます。
レピュテーションマネジメントの攻めと守りについて
レピュテーションマネジメントには、複数のアプローチが存在します。
大別すると、好評を味方にする「攻め」のマネジメント、そして悪評を相手にする「守り」のマネジメントの2種類です。それぞれのアプローチについて詳しくみていきましょう。
「攻め」のレピュテーションマネジメント
「攻め」のレピュテーションマネジメントは、もともと好感度に問題のない企業が、そのイメージの維持・向上のために行う活動です。
この活動では、ステークホルダーとの平常時のコミュニケーションや、一貫した企業理念に基づいたブランディングが主に重要となります。
コミュニケーションやブランディングは、日常的な広報活動やSNSを用いた情報発信などの積み重ねが基盤となり、周囲からのポジティブなイメージに繋がります。
ただし、過剰な演出や見せかけの活動は逆効果になるおそれがあるため、あくまで「ユーザーから企業が見られているありのままの姿」を意識しましょう。
「守り」のレピュテーションマネジメント
「守り」のレピュテーションマネジメントは、自社の評判の低下(レピュテーションリスク)に対する幅広い活動です。
観点としては、レピュテーションリスクを中心として、「未然の防止」「発生時の緊急対応」「事後的な回復」の3つに分けられます。
未然の防止
まず、何がレピュテーションリスクとして考えられるのかを把握しておかなくてはなりません。
リスクを洗い出したら、事前に緊急時を想定した危機管理体制を構築しておく必要もあります。
とくに、自社の従業員による不適切な行動や発言、インターネット上での書き込みなどによるリスクには注意しましょう。
アルバイトスタッフを含めて、従業員全員が常にレピュテーションマネジメントを意識して行動できるよう、教育を徹底するのも重要です。
発生時の緊急対応
レピュテーションリスクの最も大きな振れ幅は「発生時の初動」であり、ここでリスクをいかに抑えられるかが決まります。
風評被害や不祥事によって自社にネガティブなイメージがついてしまった際の緊急対応には、ステークホルダーに対する情報公開や謝罪会見などの緊急時のコミュニケーション(クライシスマネジメント)が求められます。
対応時には相手に不安を感じさせる態度をとらないよう、出席者全員が落ち着いて同じ返答ができるように準備しておきましょう。
事後的な回復
初動のダメージを食い止めた後は、そこから徐々に評判を回復させるために継続的な活動を行わなければなりません。
評判を向上させる点では、攻めのレピュテーションマネジメントと同様に平常時のコミュニケーションが重要となります。
ただし、風評被害や不祥事が起きた後という事実を踏まえた活動を意識しましょう。
レピュテーションマネジメントの具体的な実施方法
続いて、レピュテーションマネジメントの具体的な実施方法について紹介します。
専門企業への依頼
レピュテーションマネジメントを効果的に実施するためには、専門企業への依頼が最も安心できる方法です。専門企業は多くの事例を扱い、独自の知見や技術を持つため、スムーズな対応が期待できます。ただし、レピュテーションマネジメントは組織のリーダーや一部の担当者だけの仕事ではありません。専門企業に任せるだけでなく、従業員全員がその知識や技術を学び、企業全体で理解し吸収する姿勢が重要です。
従業員の教育
従業員の行動や態度が原因でネガティブな評判を被るケースも存在します。従業員の社外での不適切な行動や発言によって企業のネガティブな評判を招くリスクがあるため、全従業員に対するレピュテーションマネジメントの教育が重要です。アルバイトスタッフを含む全員を対象にし、社員一人ひとりがいつどこで見られているかを意識し、常にコンプライアンスを遵守する行動を取ることを意識付けましょう。
加えて、企業自体も従業員に対してストレスの少ない労働環境を提供し、採用時に個人の行動や態度を考慮するなど、企業としての努力と工夫を行うことが不可欠です。レピュテーションリスクに強い企業体質を構築し、社員の意識改善を通じて企業の全体的な評判を向上させることが可能となります。
危機管理体制の構築
「守り」のレピュテーションマネジメントでは、不祥事が発生した際の迅速かつ確固たる対応が生命線となります。企業は潜在的なレピュテーションリスクを事前に把握し、それぞれのリスクに対する緊急時の危機管理体制を構築することが不可欠です。緊急事態に対応する準備を整えることで、企業はいつでも迅速に行動することが可能になります。
また、不祥事に対応する際には、メディアを通じての情報開示も重要です。会見などでの発言は、顧客や取引先に対する説明の手段として機能し、悪評を鎮静化させることが期待されます。そのため、出席者全員が一貫した返答を行えるよう、十分な準備が求められます。不祥事が発生した際にも、ピンチをチャンスに変えることができるよう努めましょう。
レピュテーションマネジメントの事例
レピュテーションマネジメントによって、信頼を回復した企業と、失敗してしまった企業の事例を紹介します。
ジョンソン・エンド・ジョンソン社の成功事例
レピュテーションマネジメントの成功事例としては、アメリカの製薬会社であるジョンソン・エンド・ジョンソンが「ビジネス史上最も優れた危機対応」として評価されています。この事例は、1982年9月に起きた「タイレノール事件」が発端となります。
タイレノールとは、ジョンソン・エンド・ジョンソンを象徴する鎮痛剤の商品名です。この事件では、当時タイレノールを服用したシカゴ周辺の人々が次々に突然死を遂げ、7名もの犠牲者が出てしまいます。
タイレノール事件は全米を震撼させ、ジョンソン・エンド・ジョンソンの社会的信用は失墜し、ついには破産寸前という状況になりました。
しかし、当時のCEOであるジェームズ・パーク氏は自社の責任について言い逃れをせず、新聞やテレビなどのメディアを通して「アメリカの消費者にタイレノールを一切服用しないこと」という旨の警告を発信し、およそ2,200本の商品を自主的に回収したのです。
被害者たちに起きた突然死の原因は最終的に明らかにならなかったものの、迅速な対応と莫大なコストにより、事件発生の2ヶ月後には事件前の売上の約80%まで回復させています。
さらに、当社のコンプライアンスに対する意識の高さが社会に評価され、現在に至っても理想的な対応として記録に残っているのです。
ワンダー社の失敗事例
大手デリバリーピザチェーン・ピザーラのフランチャイズ経営をしていた有限会社ワンダーは、レピュテーションマネジメントの失敗によって、破産した企業です。
2013年、従業員が衛生上問題のある行為を動画に撮り、SNSに投稿。この投稿は瞬く間に拡散され、大きな騒動を引き起こしました。従業員教育が不足していたことが、このレピュテーションマネジメントの失敗の原因とされています。
レピュテーションマネジメントには評判以外の点でもメリットがある
レピュテーションマネジメントは、企業の評判に関する点以外にも副産物的なメリットがあります。
主に考えられる2つのメリットについて詳しく解説します。
消費者の潜在的なニーズを真に理解できる
レピュテーションマネジメントを実施していると、企業側が想定する内容とはかけ離れた消費者のネガティブな意見と直面することもあります。
これに対して目を背けずに真摯に対応していれば、消費者が本当に求めている「潜在的なニーズ」を知るきっかけになり得るのです。
消費者のニーズを深く把握できれば、新たな商品開発に役立ったり、サービスをより洗練させられるため、結果的に自社の利益に繋がります。
無関心層をファンにできる
不祥事や風評被害が広まると、良くも悪くも企業に注目が集まります。
注目する人々のなかには、これまでその企業に無関心だった層も含まれるでしょう。
そのため、対応次第では今まで自社に無関心・もしくは否定的なイメージを持っていた人の態度を、好意的な態度へと変えていくことができます。
ジョンソン・エンド・ジョンソンのように、社会を震撼させるレベルの事件が起きたとしても、適切なレピュテーションマネジメントを行うことで、以前よりも評判を高められる余地があるのです。
レピュテーションマネジメントを導入して顧客と良好な関係を
企業の売上や株価を左右する評判は突然変動する可能性があり、個人の意見を自由に発信できる現代ではより高まります。
レピュテーションマネジメントにおいては、平常時にステークホルダーとの良好な関係を築き、また緊急時のリスクマネジメントを盤石に備える姿勢が重要となります。
事態はいつ起きるかわからないことを念頭に入れつつ、企業は周囲からどう見られているかを意識した活動を心がけましょう。



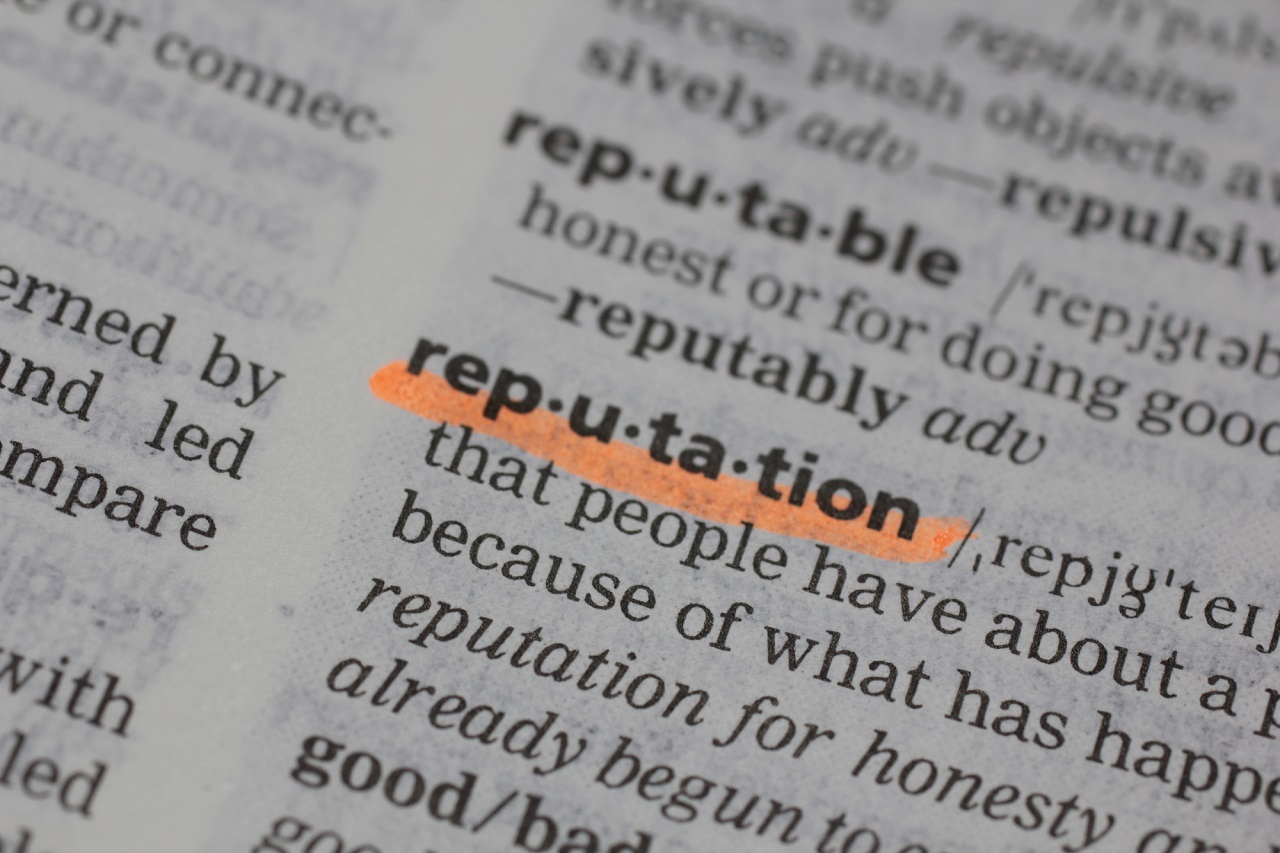


















コメントが送信されました。