読了目安:9分
若手社員の早期離職は「オンボーディング」が解決のカギ
近年、少子化も背景に若手社員の早期離職が深刻な問題となっています。 この問題を企業が解決する手段の一つとして、「オンボーディング」という取り組みがあります。
本記事では、このオンボーディングの意味や導入の現状、具体的な施策、実施期間などについて説明します。
少子化で深刻化する若手社員の早期離職

厚生労働省の調査によると、新卒社員(新規大卒就職者)の約12%が「1年以内」に、32%が「3年以内」に離職。企業にとっては、採用・教育コストの損失に加え、組織の持続可能性や生産性の低下にもつながる大きな課題です。
若手社員の早期離職は今に始まった話ではありません。2000年代初頭から、景況感の良い時期には同じようなパーセンテージで離職が起きていました。ただ当時は、「離職が起きても大きな問題ではない」「さらに採用して人材確保をすればよい」と経営者は考えていたように思います。この時期には人材系企業に勤務していましたが、離職増加は大きなビジネス機会の拡大とさえ考えていたかもしれません。
ところが、状況は変わってきました。少子化が加速して、離職をカバーする人材確保は困難な状況になってきています。20代の人口は20年で30%以上減少、この傾向はさらに加速すると想定されています。
企業が若手社員の確保のために人材を募集しても応募は皆無。人材紹介のエージェントに相談しても紹介がない。そんな現状に頭を抱えている経営者もいるでしょう。こうした状況への危機感が広がり、離職防止に向けて注目度が高まっているのが、オンボーディングという取り組みです。次で、詳しく紹介していきたいと思います。
オンボーディングとは

新たな社員(新卒・中途含む)として迎え入れた人材に早く会社になじんでもらい、早期戦力化するための仕組みとして注目度が高まっているのがオンボーディングです。一律の入社研修とは別に実施されます。
元々、オンボード(on board)は「船の上」を意味し、自分たちの船に新しく乗組員を迎えるときの言葉としてオンボーディングという言葉が使われていました。それが会社に社員を新しく迎え入れることの比喩として広まったのです。
オンボーディングの実施状況
現在、その実施率は60%を超える状況に。1,000名以上の大手企業では9割近くが実施するまで、当たり前の取り組みになってきています。中堅以上の社員の方にとってはなじみが薄くても、若手にとっては当たり前の制度と言えるかもしれません。
そもそも、どうしてオンボーディングの仕組みが、人事業界で注目を集めているのでしょうか? 前述したような離職防止に対する意識が大幅に高まってきたことが要因の一つです。人材サービス会社による調査でも、定着率向上に対する積極性を示した企業は過半数を超えており、「新規の人材採用が困難のため」という答えが上位に来ています。
人材不足と採用がなかなかうまくいかない状況や、採用にかける労力やコストを踏まえたときに、オンボーディングに力を入れて問題を解決しようとしていることがわかります。
新しいのは中途採用への導入
オンボーディングは、新卒よりも中途採用で新たな取り組みとして行われるケースが多いようです。その理由は、新卒の教育では導入済みであったりするから。日本企業の大半で新卒社員の受け入れに対しては用意周到さが見られます。
「新卒が初めて社会に出たときに受け入れた会社として、責任がある」との認識から、内定者フォローや、入社後の様々な手続き、新卒社員研修や個人面談など、比較的手厚い対策がなされていることが当たり前となっているようです。
一方で、中途社員に対しては新卒社員と異なり、「即戦力」として見る向きがあるので「それくらいはできて当然」「教えなくてもできるはず」という雰囲気が社内に漂っているケースが大半ではないでしょうか?
特に創業間もないベンチャー企業や中小企業では、会社がやや大きくなり始めたときに、創業者や創業メンバーとの思いや感覚のズレから「中途社員の短期離職」が起きる傾向がありました。それを防ぐための効果的な手法として、オンボーディングが注目され、取り組み事例があちこちで紹介されるようになったのです。
例えば、あるIT系ベンチャー企業では、若手社員の中途採用と入社後の受け入れが、各部門の管轄となっていました。その結果、「企業に対する帰属意識が育ちにくい」という課題が生じて、早期離職率は高止まり状態となっていたのです。その解決策として、全社共通のオンボーディング施策を導入。若手社員が部門の垣根を越えて自由に会話できるチャットルームを開設するなどの取り組みにより、離職率は低下したそうです。
ただ、ベンチャーだけでなく、大企業でも早期離職は大きな問題になりつつあります。オンボーディングへの注目度は、ベンチャー企業にとどまらず、高まりが出てきています。
オンボーディングを進める3つのステップ

具体的には、どのようなプロセスで取り組むものなのでしょうか? オンボーディングは、①入社前、②入社初日、③入社後数カ月~1年の期間で適用される仕組みで、主に次のような3つのステップを踏みます。
①入社前の情報提供
入社後の流れについて事前に内定者に通知したうえで、入社手続きに必要な情報を提供し、疑問に思っていることをクリアにします。相手の不安を払拭するのと同時に、入社後の手続きをスムーズに行えるようにしておくのです
②入社初日のコミュニケーション
ここが一番重要なポイントかもしれません。入社後、いかに早く会社に適応して、戦力になってもらうか。そのカギは入社初日にあります。入社者は期待と不安の中、出社してくるわけですので、その気持ちを踏まえ、うまく軌道に乗せる必要があります。
役員や人事との公式面談、業務説明、会社で仕事を進めるうえで必要な情報提供(社内のシステムや諸手続きの方法など)、各部署への紹介など、あらかじめプログラムを組んでおき、スケジュールに沿って進めます。配属先の上司や同僚に限らず、他の社員を巻き込むことも重要で、ランチは先輩社員が連れて行ってざっくばらんな話をしたり、懇親会を設定して社内のネットワーキングを行ったりします。
この際にとても重要なのが、歓迎ムードです。システムにログインした際にお祝いのメッセージが表示されたり、最初にメールを受信すると社長からのメッセージが表示されたりするなど、ちょっとした工夫で「歓迎ムード」を出せるでしょう。
③入社後のフォロー
配属先で仕事をうまく進めるために、まずは次のようなオンボーディングが実施されます。
-
配属先の上司との面談を通して、期待されている役割や目標を明確する
-
部署全体の状況やスケジュール、課題の説明をする
-
困ったときに助けてくれるメンターを紹介する
その後は仕事に取り組んでみて、どのような成果を出し、貢献できているのか、1カ月~数カ月単位で個人面談を行います。抱えている課題や今後の目標なども共有し、お互いの認識をすり合わせます。こうして社員としての定着が見えてくると、オンボーディングは完了です。
効果的な振り返りにはシステムやツールの活用も検討を
オンボーディングがうまく機能すると、職場に対する満足度が向上して離職防止につながります。
具体的に満足度が高い状況かを把握するには調査が必要なので、アンケート形式で現状把握を行い、満足度が低ければ、オンボーディングの取り組みを見直すことで、改善につなげる流れとなります。
最近は取り組み状況を明らかにするため、システムを導入する企業が増えています。中途採用を毎月のように行う企業となれば、時間差でオンボーディングも毎月のように行うことになります。抜け漏れなく行うためのチェックの観点からも、システムを活用することは効果的でしょう。継続的に行うことで、離職率の改善や生産性の向上につなげます。事業方針や経営方針に変更があっても継続していきましょう。
最後に、こうしたオンボーディングの徹底を継続するためにも、システムの活用が効果的と言えるでしょう。いわゆるタレントマネジメントシステムに搭載された機能や専門のツールなどを活用することで、関係者の業務の効率化や次の施策につなげる課題の洗い出しが進めやすくなります。人事部門とシステム部門が連携して、持続的に取り組んでいくことをお勧めします。
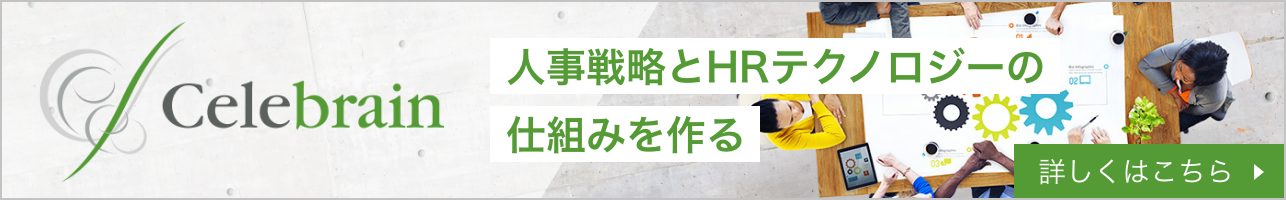





















コメントが送信されました。