読了目安:7分
なぜM&Aの多くが失敗するのか?カギは人事PMIにあり
近年、日本でもM&Aが増加しています。M&Aを成功させるには、PMI(Post Merger Integration)がキーポイントとなります。PMIとは、M&Aにおいて統合効果を確実にするための、統合プロセスとそのマネジメントのこと。投資先の企業統合はニュースでも頻繁にみかけるようになり、PMIという言葉は随分と認知されるようになりました。今回はPMIのなかでも人事領域の「人事PMI」について紹介していきたいと思います。
M&Aを成功に導く統合プロセスとは

企業統合の領域としては、経営戦略(ビジョン、戦略、ビジネスモデル、マーケティングなど)、管理体制(組織、業務管理、人事制度など)、運用体制(業務、システム、従業員意識など)と多岐にわたります(HRプロから)。M&Aは、企業の成長戦略として有効な手段ですが、PMIが不十分だと、期待した効果が得られないばかりか、統合後の混乱や従業員のモチベーション低下を招き、企業価値を毀損(きそん)するリスクもあるのです。そのため、PMIはM&Aを成功させるための重要なプロセスと位置づけられています。
PMIは、一般的に以下の四つのプロセスで構成されます。
1. 基本統合方針の策定:
M&Aの目的、統合の範囲、統合後の組織体制などを決定します。
2. ランディングプランの策定:
統合後の具体的な行動計画を策定します。
3. 100日プランの策定:
最初の100日間の行動計画を策定し、早期に成果を出すための施策を実行します。
4. 統合の実施と効果検証:
このようなプロセスに基づいて統合を実行し、定期的に効果を検証して改善策を実施。
M&Aの件数は急激に伸びており、日本全国でこうした取り組みに関わる専門家も増えている状況です。法務・会計などのほか、人事領域もメンバーに加えていただき、統合効果を出すために奔走する状況が続いています。
人事PMIの必要性と人事制度統合の考え方

M&AにおけるPMI(買収後の経営統合プロセス)の成功確率は、一般的に約30%と低いとされています。M&A全体の成功率も20~40%程度とされており、PMIの成否がM&Aの成否を大きく左右することがわかります。
PMIを成功させるために重要なことは早期に着手すること。M&Aの検討段階からPMIを意識し、早めにプロセスに着手することが重要です。続いて、社員の理解を得ること。不安や反発を解消し、積極的にPMIに参加してもらうべきです。さらにM&A後の状況は変化するため、柔軟に対応できる体制を構築する発想をもつべきでしょう。
このように早期スタートから100日くらいの期間で企業統合をすすめていくわけですが、人事PMIは経営戦略に基づき人事戦略を明確にし、その人事戦略に基づき人事制度をはじめとした各種施策を行う実行部分のこと。前述のPMIの成功率が低い代表的な理由として、組織文化の衝突、人材の流出、想定シナジーの未実現が挙がります。考えてみると、要因はすべて人に起因することで、企業統合における人事領域の取り組みの重要性を示しているのではないでしょうか? まさに人事PMIに取り組まなかったことで痛い目をみたケースがいくつもあり、重要性を痛感するようになったと言えるのでしょう。
お問い合わせ状況を鑑みても人事PMIの依頼が増えてきています。その理由を伺うと以下のような回答が返ってきました。
1.シナジー効果の最大化:
M&Aで期待されるシナジー効果(コスト削減、売上増加など)の実現において、異なる企業文化を融合させ、エンゲージメントを高めるには必須。
2.リスクの最小化:
社員の離職、モチベーション低下、組織間の対立などを早期に発見し、対策を打つことで組織の安定化が実現できる。
痛い目をみたからなのかはわかりませんが、人事PMIは企業統合で効果を導くには重要な取り組みと認識されていることがよくわかります。具体的な施策で目玉となるものの一つが人事制度の統合。異なる人事制度を一つにまとめることで、組織の効率化、従業員のモチベーション向上に加え、法的な問題を回避できます。
ただし、統合=人事制度を必ず統合しなければならないのかと言われるとそうとは限りません。会社ごとの異なる制度を併存させるケースもあります。背景にあるのは買収先となる企業が条件として人事制度などを変更しないことを提示して、買収元が了承している場合。ただ、統合しないことで「コスト」「社員のモチベーション」「人材活用」の三つの観点でさまざまな問題が生じる可能性があります。統合効果を高めるためには、可能な限り人事制度の統合は検討すべきと言えます。
人事制度統合を成功させる実践ポイント

統合の方法は大きく三つあります。
(1)買収元企業の制度に合わせる
(2)双方を組み合わせて制度を改定する
(3)新人事制度を構築する
いずれのパターンとするかはM&Aの内容・目的で変わってきますが、買収元の企業規模が大きく、同業界の場合には(1)。同規模・異業種同士の場合には(2)か(3)を選ぶケースが多かったと思います。これは企業間の力関係と社員の納得性を天秤にかけながら判断した結果なのでしょう。ここからは人事コンサルタント視点での重要なポイントを二つ紹介します。
1.人事制度と組織のギャップを分析する
現行で運用されている人事制度に給与水準や配置の偏り、職位のばらつきや職位ごとの権限委譲状況といった、人と組織にマイナスに作用しやすいギャップが潜んでいるケースがよくあります。M&Aはマイナス要因を是正するいい機会と言えます。各企業の強みを生かしつつパフォーマンスを最大化できる「あるべき姿」を定めて人事制度の改定に取り掛かるべきです。
2.制度作りとカルチャー作りの両面から取り組む
統合後の組織がシナジーを生むには、企業や仕事に対する社員のエンゲージメントを高め、モチベーションを維持できる環境が欠かせません。人事制度や組織作りとあわせて、企業ビジョンの共有や、パフォーマンスをたたえる文化の醸成といったソフト面の環境作りも同時に実施。「新しいカルチャー」を育むことで組織や人材の一体感を高め、企業が成長するための基盤を作ることが重要です。
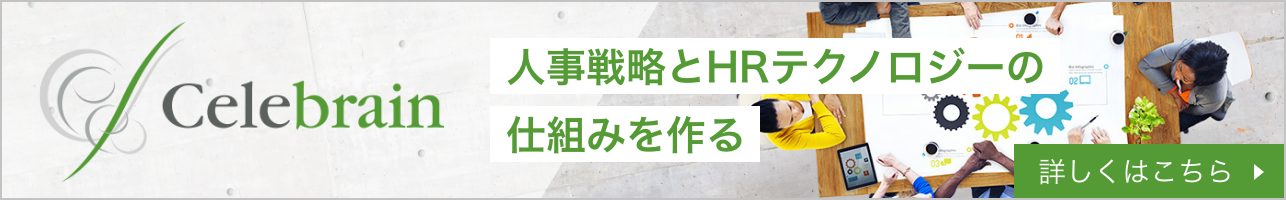






















コメントが送信されました。